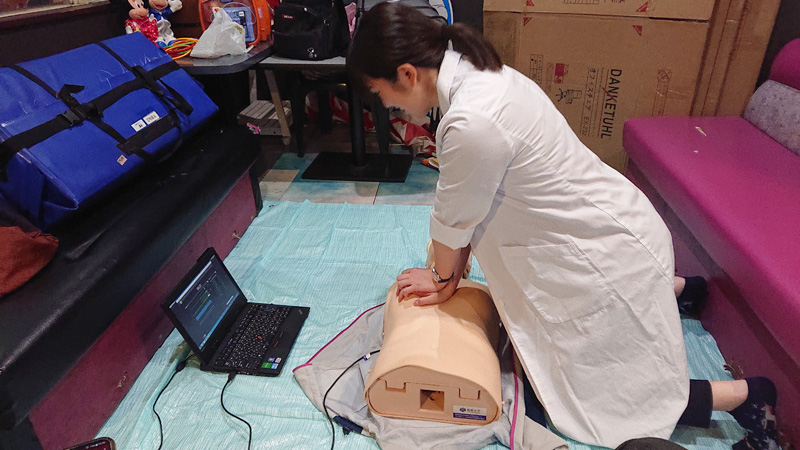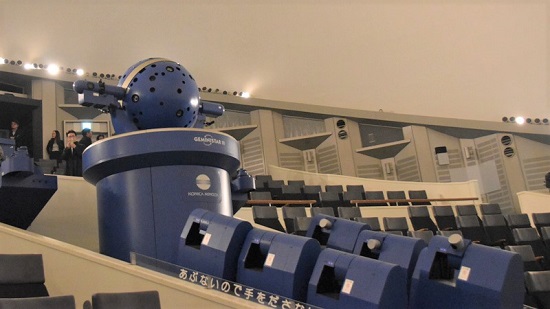【橋立多美】私たちの日常は誰かの働きで支えられている。つくる、運ぶ、売るなど、さまざまな場面の向こうにたくさんの人の仕事がある。どんな人がどんなふうに働いているか、シリーズで紹介する。
初回は、人々の生活に身近な宅配サービスを提供し続ける、宅急便クロネコヤマトのセールスドライバー加登谷文之(かどや・ふみゆき)さん(37)。
ヤマト運輸(本社東京)つくば平塚支店のつくば研究学園センターに所属。市中部の東光台とその周辺地区の配達と集荷を担当している。入社して7年になる。土浦市在住。
「気は優しくて力持ち」を地でいく。会った瞬間、自然な笑顔とあいさつで相手の緊張を解きほぐす特技の持ち主。初めはこわもてだった人とも数回配達するうちに会話を交わすようになるという。「笑顔はうつると思う」
荷物1個当たりの重さの上限は30キロだが「30キロは重いうちに入らない」と言い切る。2011年の東日本大震災を機に重い飲料水の配達が一気に増えた。
配達先がエレベーターのない集合住宅の上階で、たどり着いたら不在で運んだ荷物を1階まで降ろすこともある。「今年から筋力をつけようとスポーツジムに通い始めた。階段で息が上がらなくなった」と話す。
毎日150個以上の荷物を配り、集荷は100個前後、不在で再配達するケースは多い日で30件ある。早く届けてあげようと無意識に小走りになる一方で、勤務時間内にその日の配達と集荷を成し遂げると達成感を覚えるそうだ。
全国安全大会で優勝
忘れられない日がある。ヤマト運輸は全社の安全意識や運転技術の向上を目的に、10年から毎年「全国安全大会」を開催している。県大会と関東大会を制した勝者が全国大会に出場する。加登谷さんは12年の関東大会で2位になり、全国大会出場を逃した。
翌年のリベンジを誓い、休日は家にこもって全国大会競技種目の学科試験に向けて知識を蓄えた。迎えた第6回全国安全大会は鈴鹿サーキットで開かれた。学科と日常点検整備、運転実技を競い、マニュアル車部門の優勝ドライバーに輝いた。16年10月17日のことだった。「自分の名前が読み上げられて号泣した」と振り返る。
全国優勝ドライバーの名に恥じぬよう働く加登谷さんに、妻は「セールスドライバーはあなたの天職だね」と声をかけた。妻からの最高の誉め言葉だったと照れながら笑顔で語った。
担当エリア内の道路は路地裏まで入社後1カ月で覚えたという。交通弱者にやさしい運転を心がけ、通学路など子どもがいる道路は徐行を怠らない。
黒ネコのマークを見つけた児童たちが笑顔で手を振ってくれたり、幼児が近づいてくることもある。「我が家の子どもは大きくなったから小さい子がかわいくて。ありがとうの思いを込めて運転席の窓から子どもたちに手を振る」そうだ。
ヤマトファンをもっと増やしたいという加登谷さん。荷物と一緒にまちに笑顔を運ぶ。