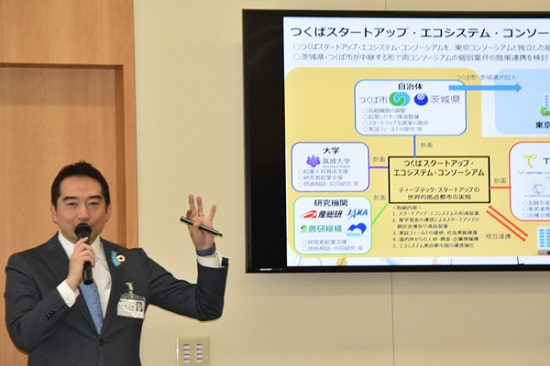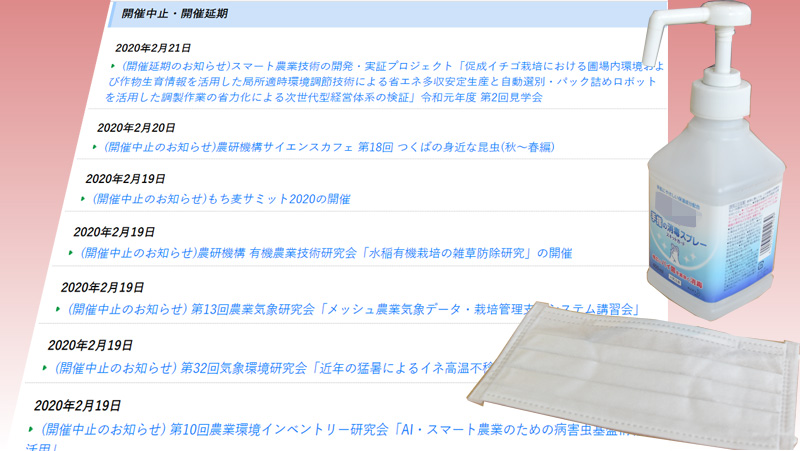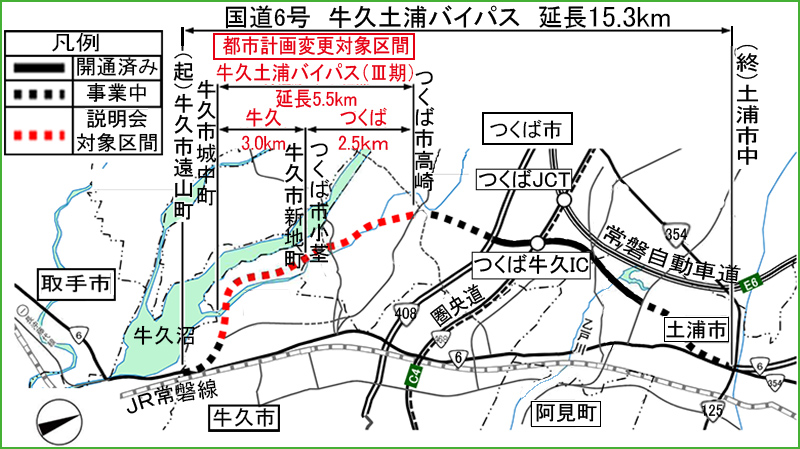【川端舞】障害者入所施設「津久井やまゆり園」(神奈川県相模原市)で殺傷事件を起こした植松聖被告と面会を重ねているノンフィクション作家の渡辺一史さんが15日、つくば市吾妻、吾妻交流センターで講演した。残忍な事件を起こした被告の異常性が話されるとともに、異常性が作られた背景にある障害者施設の実態も言及された。
渡辺さんは、筋ジストロフィーという難病当事者の地域生活を描き、昨年映画化もされたノンフィクション小説「こんな夜更けにバナナかよ」の著者。これまで13回、植松被告と面会してきた。その中で見えてきた植松被告の人間像を語ってもらおうと、当事者による障害者支援団体「つくば自立生活センター ほにゃら(川島映利奈代表)」が講演会を企画し、約40人が参加した。
事件後、それぞれの思い語り合う
同センターは、どんなに重い障害があっても入所施設ではなく地域で暮らしていける社会を目指して、地域で暮らしている障害者を支援したり、一般の人たちに障害者への理解を広めるために様々なイベントを開催している。やまゆり園事件の直後には、障害者や支援者を集めて犠牲者を追悼し、それぞれの思いを語り合う集会を開いた。センターの事務局長で自身も重度身体障害をもつ斉藤新吾さんは当時「『意思疎通のとれない障害者は安楽死させるべきだ』という植松被告の考えは極端だが、障害者は必要のない存在であるという考えは、無意識のうちに誰もが持ちうるものだと思う」と語った。
それから約3年後の2019年、同センターは、「こんな夜更けにバナナかよ」が映画化されたのをきっかけに、渡辺さんに「なぜ人と人は支え合うのか―『障害』から考える」をテーマに講演を依頼した。その中で渡辺さんはやまゆり園事件にも触れ「『障害者は生きている価値があるのか』という質問は、一見するとデリカシーのないものだが、インターネットの掲示板には多くの人が同じようなことを書いている」と指摘した。
渡辺さんが植松被告と面会を重ねていることを知った同センターは、植松被告の公判が開かれている今、被告がどのような人間なのかを知り、今後同様の事件を起こさせない、障害があってもなくても一緒に生きていける社会をつくるヒントを考えたいと、渡辺さんの講演会を企画した。
なぜ事件を起こしたのか
この殺傷事件が世の中に衝撃を与えた理由の一つに、被告がその施設に3年以上勤務していた元職員だったことがある。これまでの渡辺さんの取材によると、やまゆり園に就職した頃の被告は入所者のことを「かわいい」と言っており、将来は特別支援学校の教員になりたいという希望を持っていた。そのためのステップアップとして障害者施設の職員になったという経緯もあったという。
そのような志を持った青年が、なぜ障害者殺傷事件を起こしたのか。脱法ハーブや大麻を常用したことによる精神障害があったと弁護人は主張している。また、障害者への差別意識は多くの人が持っていても、それを「人を殺傷する」という具体的な行動に移すのには大きな隔たりがある。「被告がそこを越えてしまった原因がまだ理解できない」と渡辺さんは語った。
園内の環境も影響
一方、被告の中に「安楽死思想」が形成された背景には、彼が働いていた津久井やまゆり園内の環境も影響を与えたのではないかと渡辺さんは指摘する。去年6月にNHKで放送されたやまゆり園の元利用者についての報道を機に、やまゆり園の実情が問題視されるようになったといわれる。その利用者は、やまゆり園時代は「突発的な行動もあり、見守りが難しい」という理由で、車いすに長時間拘束されていたが、事件後、別の施設に移り、拘束を解かれた生活をするうちに、リハビリにより歩けるようになったほか、地域の資源回収の仕事までできるようになったそうだ。
また、渡辺さんが元利用者家族から聞き取った話では「居室が集まっているユニットはおしっこ臭かった」「毎日風呂に入れてもらっているはずなのに、フケも臭いもすごい」「部屋が施錠されていたのではないか」など園の実情に数々の疑問が聞かれた。そのような園の状況が、被告の「安楽死思想」に影響を与えたのではないかと渡辺さんは考える。その上で、渡辺さんはこれまでの取材の中で他の施設についての惨状を聞いてきた経験から、「津久井やまゆり園が特別なのではなく、同じようなことは他の入所施設でも起こりうる」と、入所施設の限界を指摘した。
講演会の参加者の一人は「私自身、知的障害の子どもを育てている母親として、この事件にはあまり関わりたくなかったが、事件の本質には被告自身の問題だけでなく、社会全体の問題があり、このまま終わりにしてはいけないと感じた」と話した。
5月の全国集会でもテーマに
今年5月30、31日に、つくば国際会議場でDPI(障害者インターナショナル)日本会議の全国集会が開催される。DPI日本会議とは、現在130カ国以上が加盟し、障害のある人の権利の保護と社会参加の機会平等を目的に活動をしている国際 NGOの日本国内組織である。2日間で全国から多くの障害者が集まる。2日目にはやまゆり園事件の裁判についても取り上げる予定である。この集会の実行委員会をつくば自立生活センターも担っている。
同センターは「3月16日にこの裁判の判決が予定されているが、3カ月程度のスピード判決はこの事件の何を浮き彫りにするのか。検証すべき重要な問題を闇に葬り去ってしまうことにならないか。障害者への差別や偏見を助長したりしないのか。様々な立場から問う機会にしたい」としている。
大規模の入所施設では限界
【記者のつぶやき】入所施設の場合、どうしても一人の職員が担当する入所者の数が多くなってしまい、入所者一人一人に丁寧な個別対応は難しい。被告が「意思疎通のとれない障害者」と称した被害者の方々も、一人一人、時間をかけて向き合えば、身振りや表情など、言葉以外の方法でコミュニケーションをとろうとしていたはずである。彼らが伝えようとしている想いを、周囲が丁寧に受け取れるようになるためには、大規模の入所施設では限界がある。入所施設の限界が浮き彫りになった今こそ、入所施設ではなく、在宅で障害者一人一人と関係性を作りながら支援することに重点を移すべきであろう。
➡障害者自立センターほにゃらの過去記事はこちら