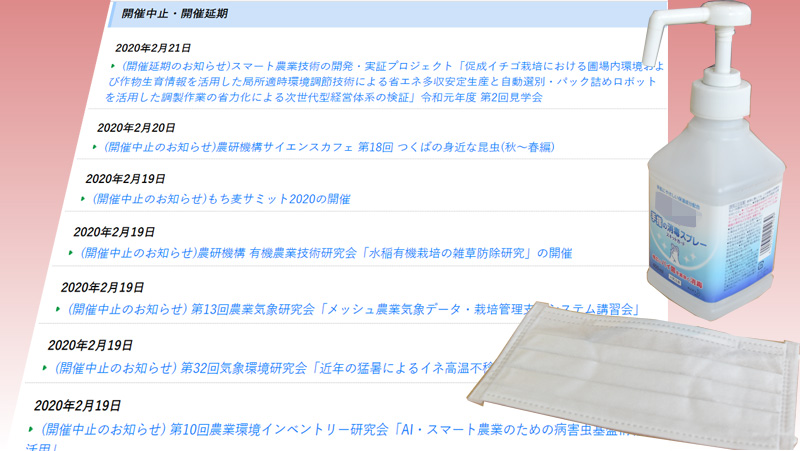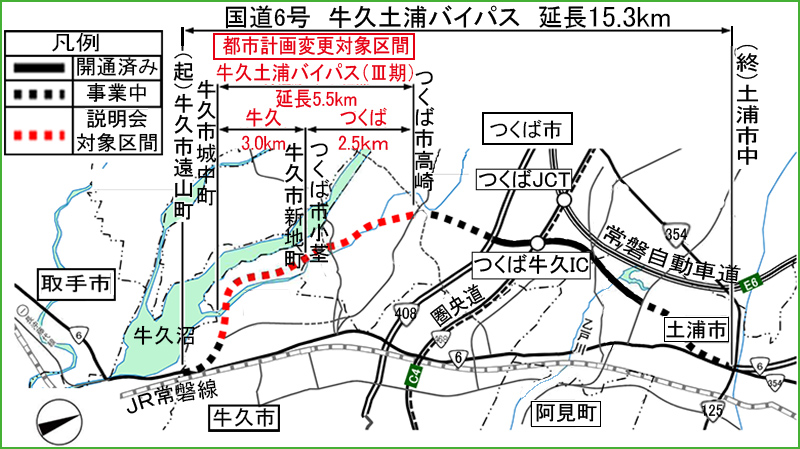【池田充雄】バレーボールVリーグ2部(V2)男子のつくばユナイテッドサンガイア(SunGAIA、本拠地つくば市)は22、23日、今季最後のホームゲーム2連戦をつくばカピオ(つくば市竹園)で開催。22日はきんでんトリニティーブリッツ(大阪市)にフルセットの末敗れたが、23日は埼玉アザレア(川越市)にセットカウント3-1で快勝。通算成績を10勝11敗とし、12チーム中7位に浮上した。

埼玉戦の第1セット、つくばは順調な立ち上がりで最大4点をリード。だが中盤、コンビネーションミスを2本続けて同点にされると、サーブレシーブの乱れなどで自分たちの形を作ることができず、相手にリードを許す。終盤の追い上げも届かず、このセットを失う。
第2セットは序盤のイーブンな展開から、瀧澤陽紀のサービスエースをきっかけに5点を連取。波に乗ったつくばはそのまま同セットを獲得。第3・第4セットも序盤からリードを保ち、追い上げられても流れを切って相手に渡さず。安定した戦いで、前回対戦ではストレート負けの相手に雪辱を果たした。
「瀧澤の渾身(こんしん)のサービスエースで流れを引き戻し、自分たちの力を発揮するとともに、ホームの大声援を力に変えて勝利することができた」と、都澤みどり監督。「今季はミスから崩れることも多かったが、今日は粘り強く戦えた。点差がついた後も気を緩めず、しっかり勝ちきれた」と浜崎勇矢主将。
あせりから攻撃が単調になる悪いクセが消え、多彩なアタックやサーブで相手を崩すことに成功。また今節では、セットの際に各選手がポジションを取り直さず、ローテーションの位置から直接攻撃に入ることが多かった。このため最短時間と最短距離で、相手ブロックの薄い部分を狙い打つことができる。
「全体でブロックを引き付け、各選手の状態を見ながらトスを上げている」と、セッターでもある浜崎主将。特に小針幸や奥村航は左右からのスパイクはもちろん、バックアタックでも効果的に得点を重ねていた。

来週は、他チームよりひと足早く今季最終戦を迎える。29日(土)午後1時から北海道帯広市総合体育館でトヨタ自動車サンホークスと対戦。勝って星勘定を五分に戻し、シーズンを締めくくりたい。
つくば 3-1 埼玉アザレア
23-25
25-20
25-19
25-14
➡つくばユナイテッドサンガイアの過去記事はこちら