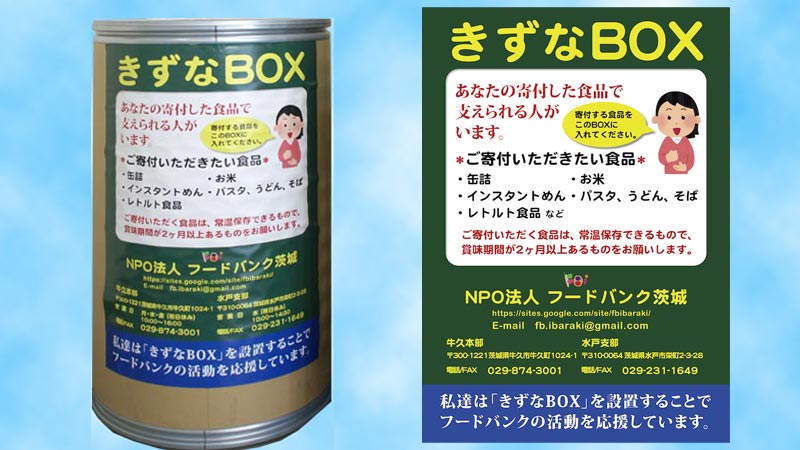【伊藤悦子】新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、土浦市立図書館(同市大和町)が9日から3月末まで分館を含めたすべての図書館を休館にした。県図書館協会によると、臨時休館となった図書館は増え、県内66館のうち30館が臨時休館になっている(10日時点)。イベントの自粛にとどまらず、休館に踏み切る公共施設が増えている。
土浦市立図書館の入沢弘子館長は「公共施設の中でも市立図書館は駅に近く、駅前のにぎわいをつくる機能もあるため、多世代にわたる来館者が非常に多い。また滞在型図書館であることから感染リスクも高まる」と休館の理由を説明し、理解を求める。
同館は単館として県内一の来館者があり1日約1800人が訪れる。土浦市は水戸市に次いで高校の数が多いため高校生の利用が多いことも特徴だ。さらに来館者がゆっくり過ごせる「滞在型」であるため多くの来館者が長時間滞在する。
新型コロナウイルスの全国的な感染拡大に対し、土浦市は県内他市町村に先駆けて2月21日、市主催イベントの開催基準を定め、公表した。市立図書館では当初、不特定多数が閉鎖された空間に集まる館内イベントのお話し会を中止した。その後3月2日から高校が、4日から小中学校が臨時休校になったことを受けて、図書館は4日から高校生が集まる4階の学習スペースと飲食コーナーだけを閉鎖した。
するとこれまで4階を利用していた高校生らが3階、2階に降りてきて勉強をするようになった。4階閉鎖後も来館者数は変わらず、かえって人が密集する状態になったため休館の検討を始めた。
当初は分館を開館することを検討したが、本館を休館すると来館者が分館に流れてしまうことを懸念し、分館も閉館にも踏み切ったという。
入沢館長は「図書館本来の使命を果たさないのか、という意見もあるかと思う」と話し「駅前のにぎわいをつくる機能もある滞在型図書館で、たくさんの人が長時間滞在する。感染リスクを考えるとお叱り覚悟で臨時休館を決めた」と語った。
休館について利用者からメールで問い合わせは入るが、事情を話すと理解してくれるという。臨時休館が始まった10日の朝は、開館前から入り口で待つ来館者はなかった。休館を知らせるポスターを見て引き返す人がいたものの、混乱は起きていないという。
閉館前日の8日、同館を訪れた同市小岩田に住む女子高校生(17)は「図書館は集中しやすい。勉強する空間がなくなるので困るが、家でなんとか頑張りたい」と話していた。
「再び開館するときはピカピカに」
休館中も職員は平常通り業務にあたる。傷んだ図書の修理など、普段なかなかできなかった作業を行うという。「再び開館するときはピカピカの状態になっていると思う。状況が変わり次第、ホームぺージなどにお知らせを出し、入り口にポスターを貼るので確認していただきたい」と入沢館長は話す。
貸出予約を受けた資料は、連絡済みの予約資料のみ15日までなら受け取ることができる。16日以降は貸出しないが、開館後、再度連絡する。貸出中の資料は図書館開館後、1週間をめどに返却してもらう。休館中は、各図書館や各地区公民館に設置している返却ポストを利用できる。他館の資料、相互貸借資料については相手館への返却のため、返却期限内の返却が必要だ。アルカスや各分館の窓口で対応してくれる。詳しくは同図書館の土浦市立図書館のホームぺージ。
◆土浦市内のほかの公共施設休館は次の通り(14日現在)。状況によって変更になることがある。休館中の使用料は返金する。詳しくは土浦市ホームぺージ。
▽りんりんポート土浦のシャワー室=2日から当面の間休止
▽勤労者総合福祉センターのトレーニング室=2日から当面の間休止
▽温浴施設「霞浦の湯」=2日から大ホール貸出を除き当面の間休止
▽老人福祉センター・湖畔荘のお風呂=2日から当面の間休止
▽老人福祉センター・つわぶきのお風呂=2日から当面の間休止
▽ふれあいセンター・ながみねのお風呂・プール=2日から当面の間休止。11日から開館時間を午後6時までに短縮
▽新治総合福祉センターのお風呂=2日から当面の間休止
▽小中学校体育館開放事業=2日~4月5日まで休止
▽ワークヒル土浦のトレーニング室、多目的ホール・工芸室の個人利用(卓球・ダンス等)=3日から休止
▽ネイチャーセンター=16日から当面の間休館
▽霞ケ浦文化体育会館(水郷体育館)=17日から当面の間休館。会議室を除く。トレーニング室は2日から利用休止
▽新治トレーニングセンター=17日から当面の間休館
▽市立武道館=17日から当面の間休館。弓道場を除く。
◆つくば市公共施設の休館状況は次の通り(14日時点)。状況によって変更になることがある。感染拡大防止のため交流センターなどの使用をキャンセルした場合、使用料を返金する。詳しくはつくば市ホームぺージ。
▽桜総合体育館の柔剣道場=4日から18日まで利用休止
▽谷田部総合体育館の柔剣道場=4日から18日まで利用休止
▽筑波総合体育館の柔剣道場=4日から18日まで利用休止
▽豊里柔剣道場=4日から18日まで利用休止
▽つくばウェルネスパークのトレーニングルーム=3日から当面の間、利用休止
▽桜総合体育館のトレーニングルーム=3日から当面の間、利用休止
▽谷田部総合体育館のトレーニングルーム=3日から当面の間、利用休止
➡新型コロナウイルスの関連記事はこちら