「発明の日」の18日に始まった科学技術週間は24日まで。つくば市内の教育・研究機関でも、各種イベントが展開中だ。新型コロナ感染対策から、施設公開やトークイベントなどをオンラインで行う一方、研究開発に取り組む現場の映像を配信するなど、工夫を凝らしたインターネット上での紹介が大半を占めている。(橋立多美)
宇宙と物質の謎配信 高エネルギー加速器研究機構(KEK) KEKチャンネル )1日目=https://youtu.be/3muAqQSO04E 2日目=https://youtu.be/POV1rikg284
ショートムービー&トークライブ配信 産業総合技術研究所(AIST) ホームページ から。参加無料。
研究現場を伝える産総研のショートムービーのワンシーン。「0.03ミリまで岩石をけずる」 (産総研提供) 食と農の科学館オンラインツアー 農業・食品産業技術総合研究機構(NARO) こちら 。
非常識な『ミカタ』~材料の科学者はこう考えた~ 物質・材料研究機構(NIMS) こちら から。
特設サイトで発信 国際農林水産業研修センター(JIRCAS) 一般公開特設サイト で。
オンラインでつながろう! 国際協力機構(JICA)筑波国際センター こちら
視覚障害に配慮した学び体験 筑波技術大学春日キャンパス
このほかの主な公開は次のとおり。
▽筑波大学 スーパーコンピューターと学際計算科学の最前線など研究室紹介の動画配信。宇宙史研究センターによる「宇宙の誕生から銀河の形成」は力作。宇宙の始まりから銀河の形成、さらにその先まで、宇宙の歴史の5日の場面でとらえ、その最新研究の様子を届ける。視聴はこちら のメニューから。
▽JAXA筑波宇宙センター 科学技術週間期間中、館内休憩室でJAXAの取り組みや最新の情報をショートムービーで紹介する。現在、一般見学は事前予約制、見学の案内サイト(https://visit-tsukuba.jaxa.jp)
▽産総研・地質標本館 2021年に発信した特筆すべき研究成果14件をまとめてウェブ会場 から紹介。地質標本館は3月16日深夜の地震により一部不具合が生じ、点検と必要な修繕のため臨時休館中。6月末までの新たな来館予約を停止している。
▽国立公文書館つくば分館 春の企画展「ゆっくら温泉ー江戸時代の湯めぐり」は終了した。新旧憲法、終戦の詔書(しょうしょ)などのレプリカ展示は常設で行われている。午前9時15分~午後5時、土日祝日休館。
▽国土技術政策総合研究所 津波越流に対する海岸堤防に関する実験や、災害時の道路交通維持に貢献する道路基盤実験施設など、Webでの公開のみ。視聴はhttp://www.nilim.go.jp/
▽土木研究所 研究所の紹介、免震橋や津波でも流出しにくい橋などの実験を配信。Web での公開のみ。
▽NTTアクセスサービスシステム研究所 細いガラス製の「光ファイバ」でさまざまな情報を伝える仕組みや、通信基盤を支える技術を紹介する。
▽国土地理院「地図と測量の科学館」 企画展「緯度経度 世界共通の正確な『ものさし』へ」を開催。測量用航空機くにかぜの内部公開は21日午前10時~午後3時、雨天中止。
▽つくばエキスポセンター =企画展「錯視の世界~あなたは今度もかならずだまされる」、科学のポスター展、科学技術映像祭など科学の不思議を体験できる。科学技術週間中は入館料が割引(大人200円、子ども100円)。
▽筑波実験植物園 =24日まで「さくらそう品種展」。100種類を超えるサクラソウの園芸品種を、江戸時代から続く伝統的な方法で展示する。一般320円(税込み)、高校生以下・65歳以上は無料。入園は午前9時~午後4時半。https://tbg.kahaku.go.jp/


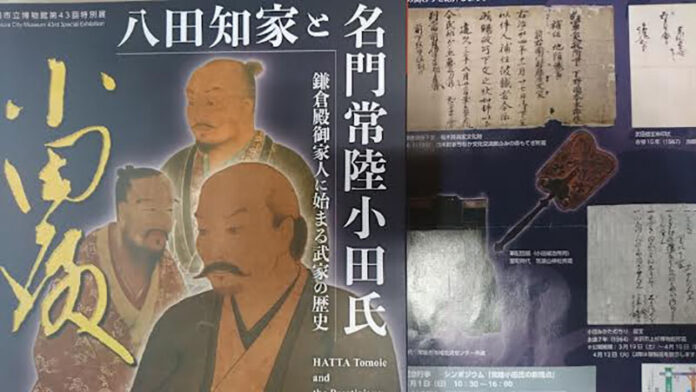

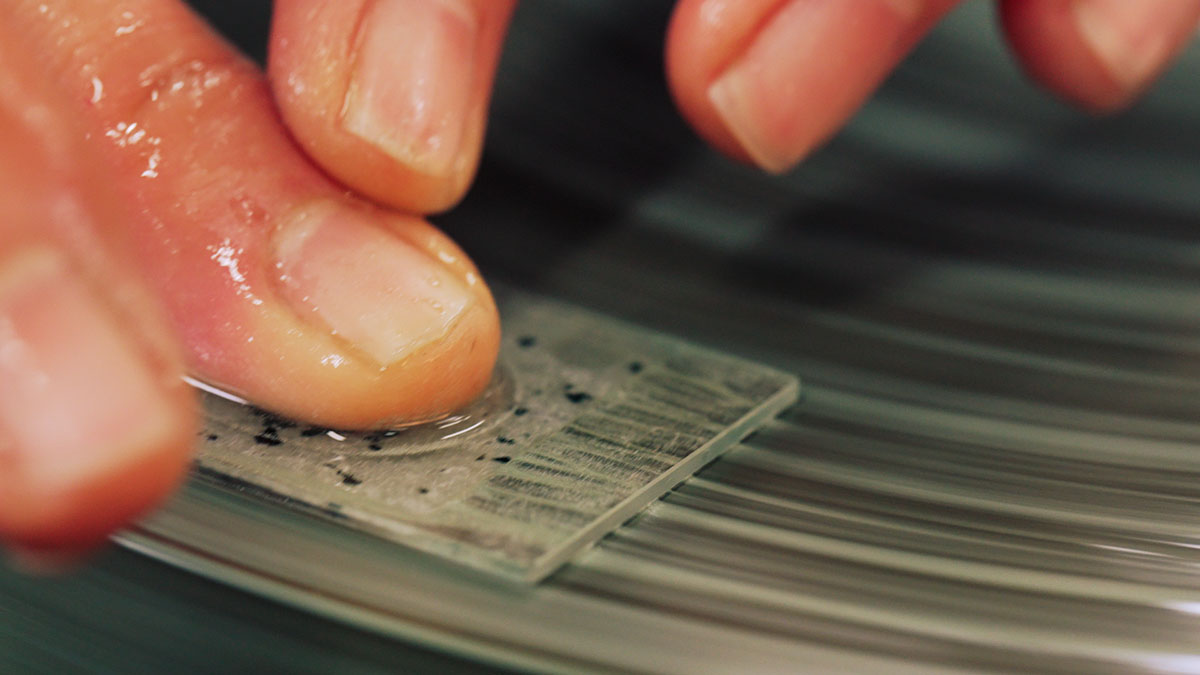

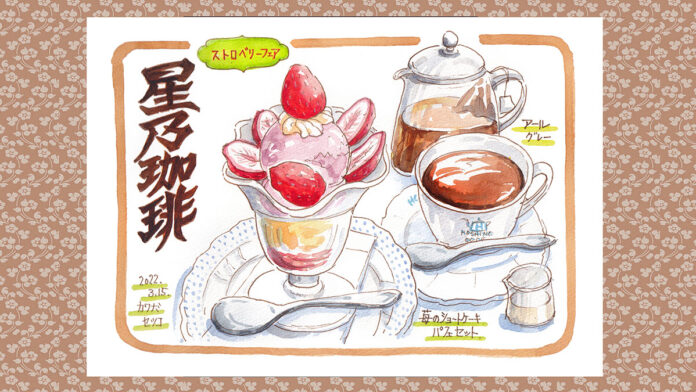












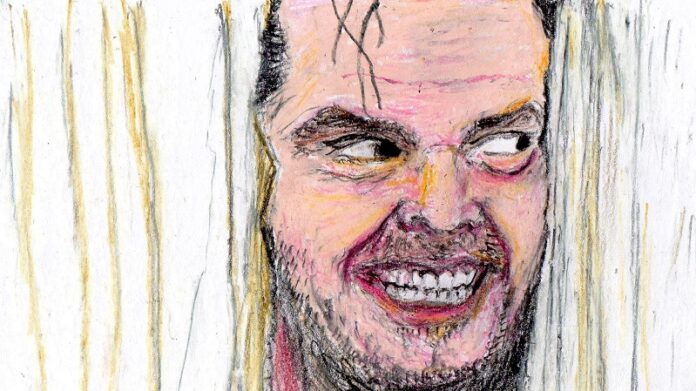




![川端舞 29[10847]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/04/23407016b8ea9c38660f60b7d7badbba-696x392.jpg)







