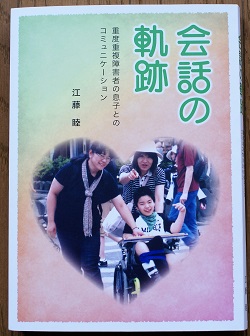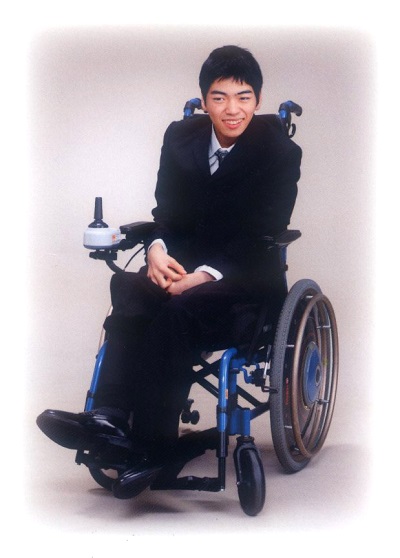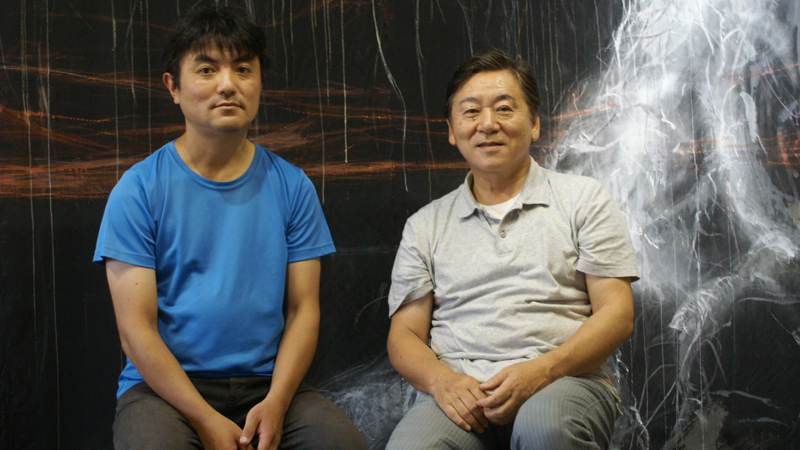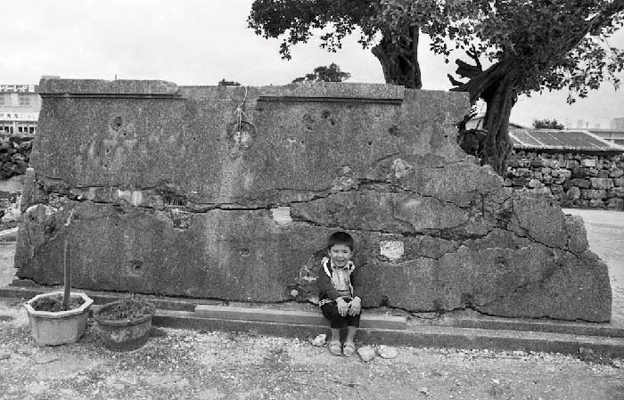【鈴木宏子】施設一体型小中一貫校を新設してきたつくば市の教育方針が大きく転換する。門脇厚司教育長は「5校目の義務教育学校はつくらない」と表明し、人口が急増するつくばエクスプレス(TX)沿線に今後新たにつくる小中学校は、施設一体型の一貫校とはしない方針を示した。つくば市の教育はどこに向かうのか、門脇教育長にインタビューした。
大規模校になってしまう
―人口が急増するつくばエクスプレス(TX)沿線にさらに2校を新設する計画が発表された19日の市議会全員協議会で、門脇教育長は「5校目の義務教育学校はつくらない」と明言されました。つくば市の小中一貫校を検証した市教育評価委員会の調査報告書「つくば市の小中一貫教育の成果と課題」(2018年7月)でも「小中一貫教育の効果は小中分離校でも発揮されている。施設一体校では中一ギャップは解消しているが、新たに小6問題が顕在化している」などの課題が出されています。義務教育学校、つまり施設一体型の小中一貫校はつくば市ではもう止めるということでしょうか。
門脇 小中一貫の義務教育学校がつくば市にはすでに4校あり5000人が在籍している。小中学生約2万人のうち4分の1になる。小中一貫教育の義務教育学校を止めるとは言えないが、5校目以降はつくらない。すでにある4校の義務教育学校については、これからはできるだけ小学部と中学部の分離を意識した学校運営をやりたい。
例えば、今は小学6年生を終えても卒業式もないし、中学生になる際に入学式もない。これからは小学部1年生から6年生、中学部1年生から3年生の区切りとし、小学部の卒業式も中学部の入学式もきちんとやるようにしたい。
―義務教育学校をこれ以上つくらない理由は何ですか。
門脇 これからTX沿線につくる新設校を義務教育学校にすると、大規模校になってしまう。それから2018年7月の「小中一貫教育の検証と課題」で指摘されたように、同じ小中一貫教育でも、小学校と中学校が分離していた方が教育効果が高いということなら、高い効果が現れる方を選んだ方がいい。
つくば市で子供の数が増えるのはこれから10年間か15年間。15年後には減ってしまう。これからつくる学校は、将来、何に転用するか考えてつくらないととんでもないことになる。将来どういう施設として活用するかを今から考えながら設計をしていく。
子育て世代 想定以上に増えた
―5月30日につくば市が発表した「今後の人口増加地域の児童生徒数の推計値」によると、新たに学校をつくったとしてもTX沿線では引き続き過大規模校のままとなってしまう学校が複数あります。なぜこんなことになってしまったのでしょうか。
門脇 想定より多い子育て世代がどんどん入ってきている。前任者もこうなると思ってなかったのではないか。前任者が「教育日本一」を大々的に掲げたこともある。保護者は、教育日本一とは学力日本一だと考えて、つくば市の学校に入れればわが子の学力が上がると考え、想定以上に増えたのではないか。できたばかりの新しい学校は立派できれいなので、うちの子もこんなすばらしい学校で勉強させたいと、わざわざ引っ越してきた親御さんもいる。
「世界のあした」のトップランナーに
―つくば市の教育はこれからどういう方向を目指すのかを示す教育大綱を今、策定中です。つくば市の教育はこれからどう変わっていくのですか。
門脇 子供たち一人ひとりを徹底的に大事にする教育を目指す。どの子にも、自分はこういうふうに生きていきたいと願う気持ちがあるわけで、それを実現させる教育にしたい。
つくば市は五十嵐市長が「世界のあしたがみえるまち」を掲げている。ならば、つくば市は「世界のあしたの教育」のトップランナーになると言ってきた。これまでどこでもやってない教育をやりたい。
そもそも現在の公教育制度は、150年前に、産業社会を発展させるために必要な人間を育てることを目的に作った制度で、極めて不自然なことを無理を重ねてやってきた。
一例をあげれば、その国に生まれた子供は誰もが一定の年齢になったら必ず学校に行くことを強制されるし、同じ年齢の子でクラスを作り、全員が同じ教科書で同じことを一斉に教わる。学期が終わると必ず競争試験があって、できる子と出来ない子を分けて、できる子にはもっと勉強させて新しいモノを創り出すことができる能力を高め、できない子には先生や経営者の言うことを守ればいいと教える。こんなやり方はいやだ、自分のペースで学びたいと言っても許されないというふうに、今の公教育は経済成長を最優先させるため不自然な教育を無理を承知でやっているというのが実態。
だから、新しい教育大綱をつくって、つくば市がこれから目指す教育をはっきり示さなくてはならない。学力競争の教育から抜け出して社会力を育てることを基本にすえる。社会力とは人と人がつながって社会をつくる力、さまざまな人と人がよい関係をつくり、協力しながらよりよい街をつくる力のこと。子供も大人も社会力を育てるのがつくば市の教育の将来になる。
新設校は固定観念を一新する
―これからできる新しい学校は、つくば市が目指す新しい公教育の在り方を先取りしたものになるのでしょうか。
 香取台小学校(仮称)建設予定地
香取台小学校(仮称)建設予定地
門脇 例えばいま設計に取りかかっている香取台小学校(仮称、2023年4月に万博記念公園駅近くに開校予定)は、学校に対する固定観念をぶち破る学校にしたい。
職員室はつくらないで、1年生の教室が並んでいる真ん中あたりに1年生の担任の先生たちの授業準備室をつくる。先生が授業の準備をしたり、お茶を飲んで雑談したり休憩したりする。全教職員が一カ所の部屋に集まる今の職員室は同調圧力のもとで、互いに監視し合ったりする。仕事が終わったので早く帰りたいと思っても隣の先生はまだ帰らないので残っているということになる。
カフェテリアをつくり、勉強に使っている机で給食を食べるのではなく、カフェテリアで食べることで食事そのものを楽しんでほしい。
プールはつくらず、プールの敷地に保育所や児童クラブや、大人が集う市交流センターなどをつくって、学校を小中学生だけの施設でなく市民が集える複合施設にするとか、演劇や音楽や美術の発表を楽しむホールや大勢で遊べる遊び場は作っても、「全体回れ右!」といった軍隊式の集団行動を訓練する体育館は作らないというふうに、学校とはこういうものだというこれまでの固定観念を一新するような学校を作ってみせたい。