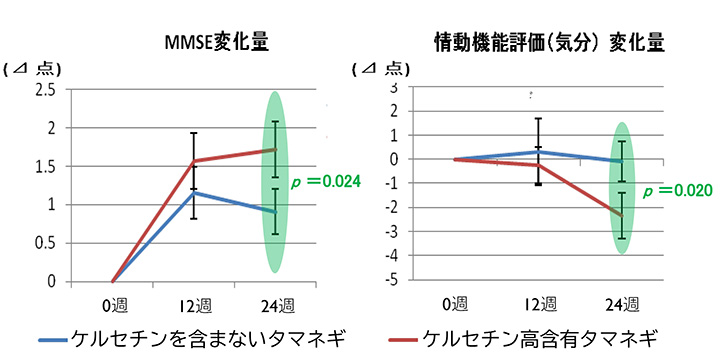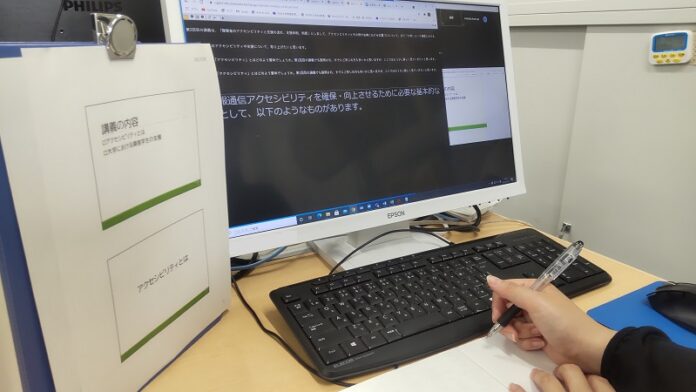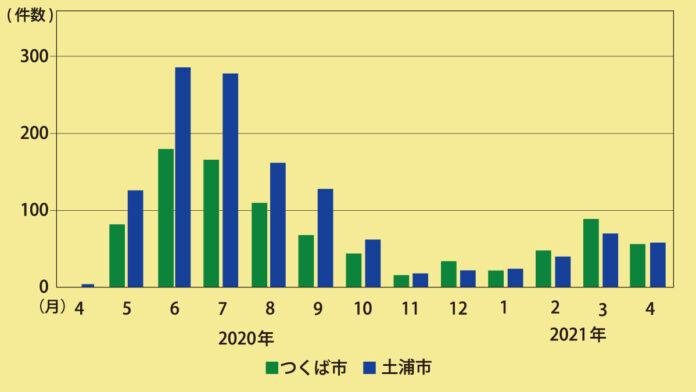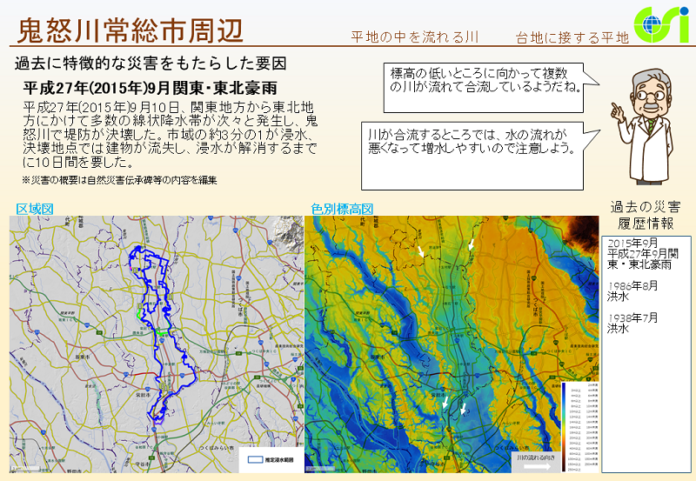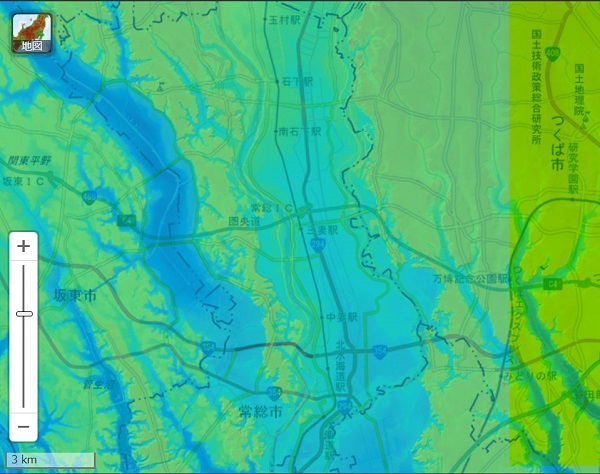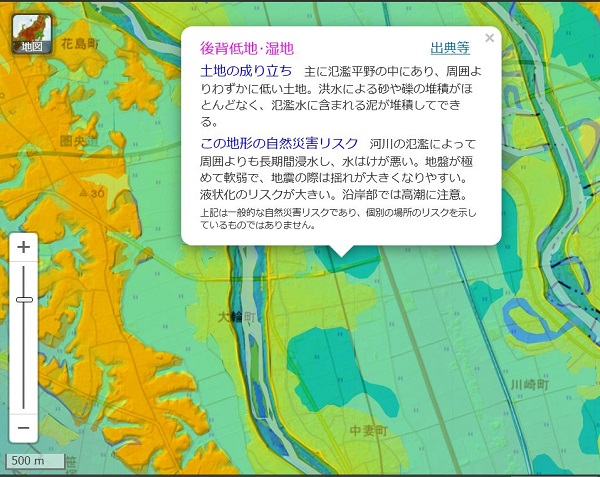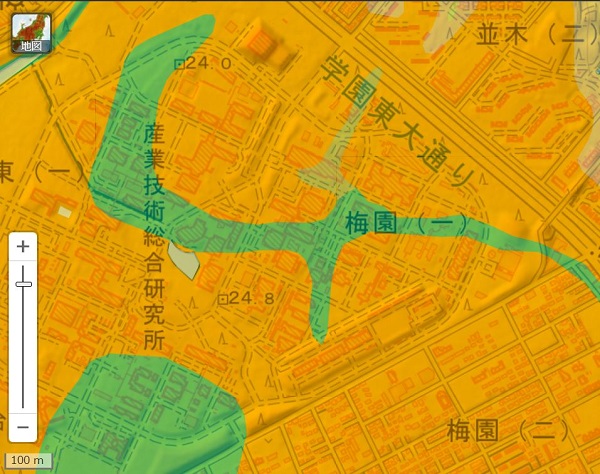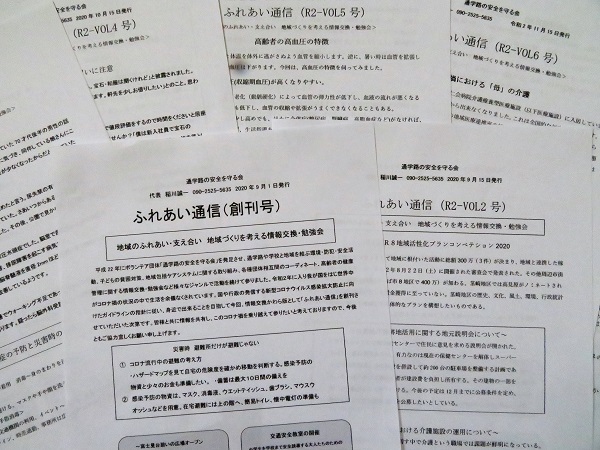新型コロナウイルスの感染拡大を受け、東京オリンピック・パラリンピックに出場する海外選手団の事前合宿を取り止める自治体が全国で出ている中、筑波大学で予定されているスイス選手団の事前合宿について、つくば市は2日の定例会見で、陸上と柔道の選手団計約70人が7月中旬から8月上旬にかけて、同大学で事前合宿を実施することを明らかにした。
新型コロナ対策として、スイス選手団は事前合宿中、毎日、PCR検査を実施するほか、選手団と直接接触する筑波大やつくば市担当者なども毎日、PCR検査を実施する。
選手団の練習中は、大学の施設を貸し切りにして、一般の筑波大生らと接触しないようにするほか、宿泊施設は市内のホテルのワンフロアを貸し切り、一般の宿泊者と接触しないようにする。選手団は練習会場とホテルを往復するだけにする。
選手団の食事は、スイスから随行する専用の料理人がホテルの調理室の一部を借りて調理する。食事は、専用の部屋でとるという。
市オリンピック・パラリンピック推進室によると、スイス選手の第1陣が7月13日夕方来日し、同日夜からつくば市内に滞在する予定だという。
競技種目ごとに順次、来日するため、市内に滞在する人数は最大で30人程度という。
当初予定では、陸上、柔道のほか、フェンシング、体操、トライアスロンの計5競技の選手団が、競技の2~3週間前に来日し、大学の陸上競技場や武道館、体育館などでトレーニングする計画だった。
5競技のうち、フェンシングと体操の事前合宿は取り止めになり、トライアスロンは未定される。
市民との交流イベントは中止
市によると、フェンシング選手団が取り止めとなった理由は、競技日程の都合だとし、来日後は直接、選手村に入る。未定のトライアスロン選手団が筑波大で事前合宿をする場合は10人程度になる見込み。
市民との交流は当初、ウエルカムイベントや小中学生との文化交流、事前合宿の見学会などが予定されていたが、選手と直接接触するイベントはすべて中止となる。一方6月中に市は、市内の市立幼稚園と小中学校などの給食にスイスの家庭料理メニューを出すことを計画している。
筑波大と県、つくば市は2018年4月、スイスオリンピック協会と基本合意書を締結し、事前合宿の受け入れを決めた。19年2月に同市はスイスのホストタウンとなった。
19年5月、スイスの女子リレーチームが、7~8月にはトライアスロン選手団がそれぞれ筑波大で事前合宿を実施し、小中学生が選手の食事を配膳したり、中学生が練習の様子を取材して記事を書くなどの交流イベントを実施してきた。