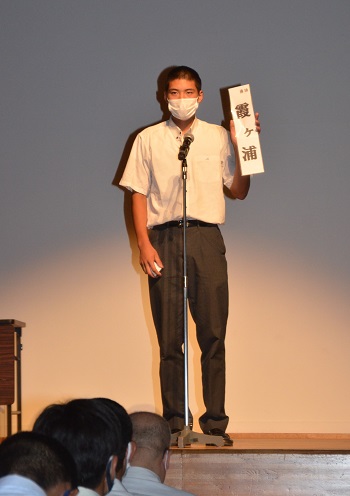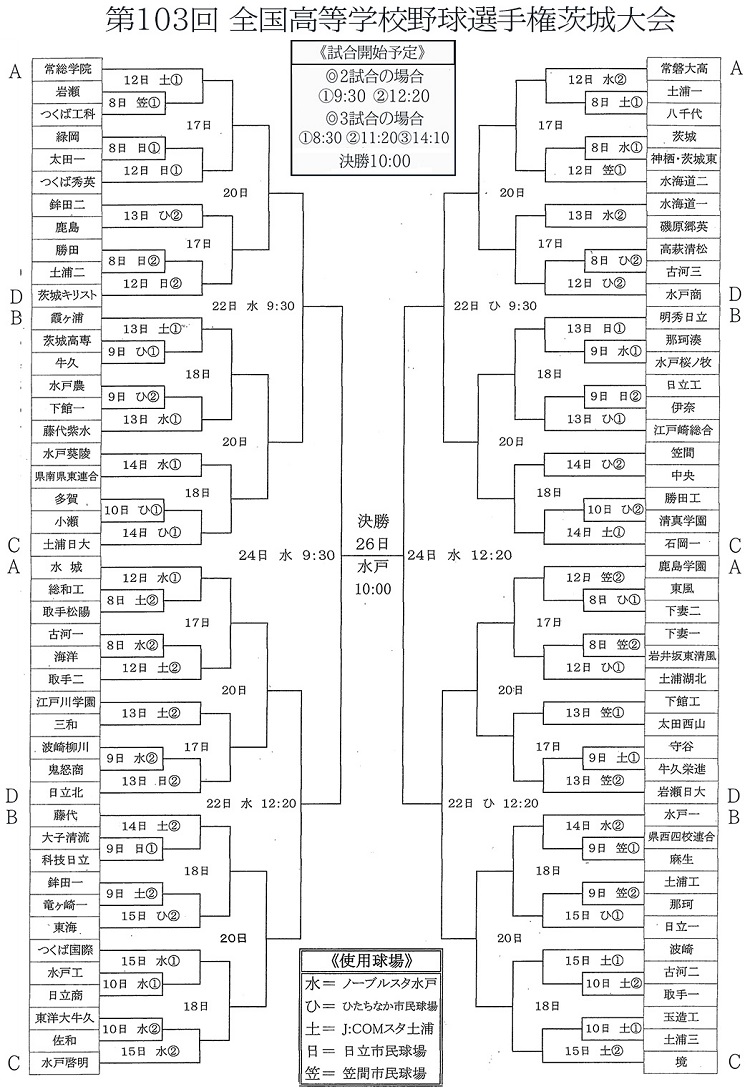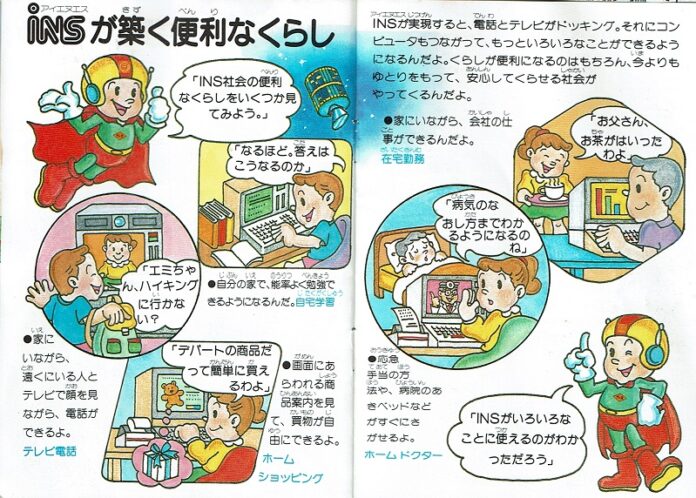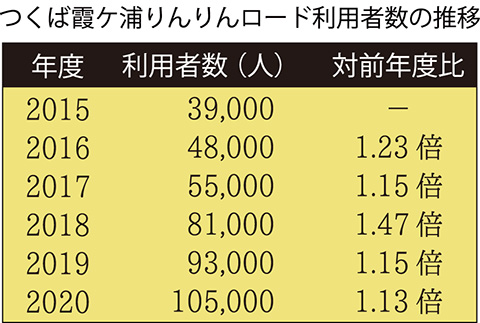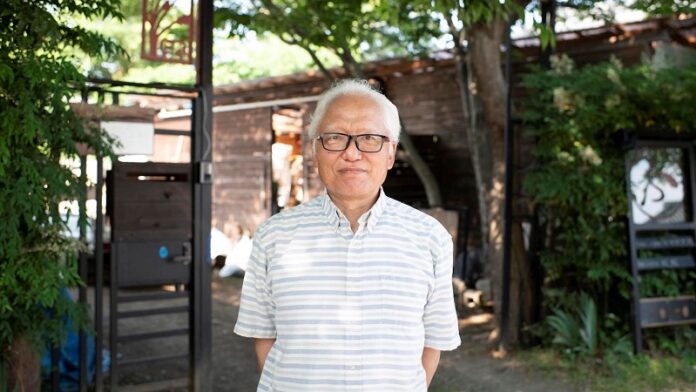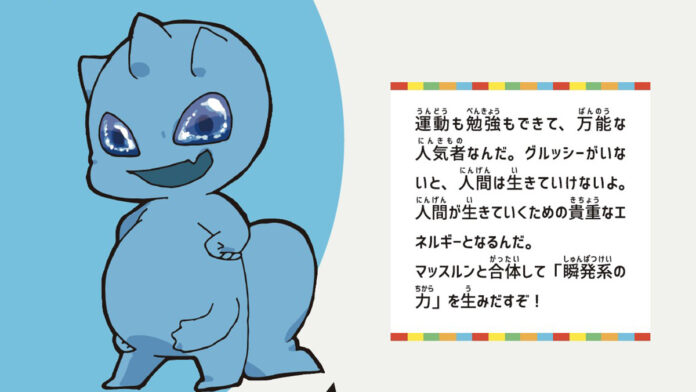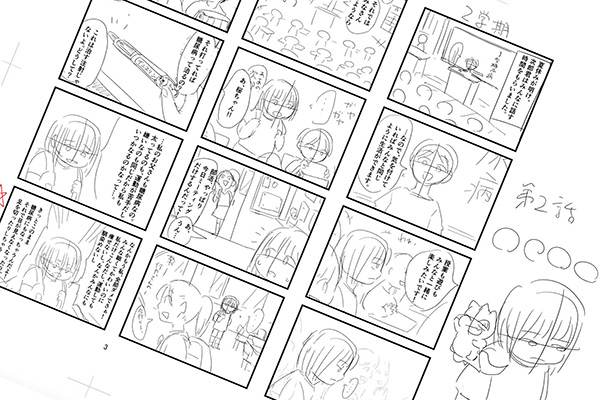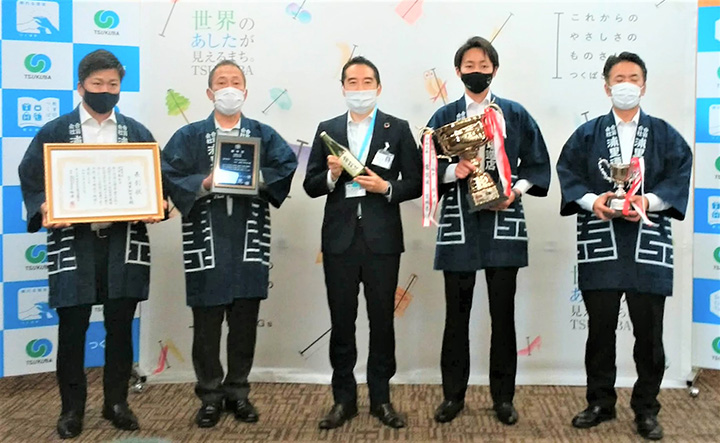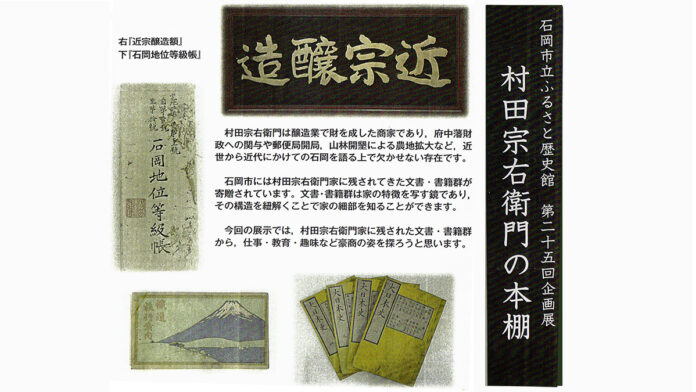【コラム・玉置晋】どうも最近、日に当たると手の甲が腫れるのです。インターネットで検索してみると、日光アレルギーというものがあるそうです。じゃあ日焼け止めを塗ってみなさいよと言われ、奥様の日焼け止めを借りてみたものの、腫れは治まらず。
さらに調べてみると、日光アレルギーの原因となる光の波長は可視光が多いとのこと。日焼け止めは紫外線を防ぐもので、可視光には防御力が限定的であるとのこと。宇宙天気防災研究を志しているのに、太陽からの攻撃に脆弱(ぜいじゃく)とは困ったなあ。とりあえず長袖を着ることにして、ひどいようなら病院に行こうと思います。
地球の大気は、厳しい日光から僕たちを優しく守ってくれています。人体に有害な波長の日光は、地球の大気がその大部分を吸収してくれています。大気に吸収されずに地表に到達しやすい波長領域が可視光や近赤外線で、「大気の窓」と呼ばれています。僕たち地上の生命は、この窓を通して降り注ぐ日光に適応した進化をしてきたわけです。
一方、地球は表面から、大気の窓を通して宇宙空間に赤外線の形でエネルギーを放射しています。二酸化炭素といった温暖化物質が増えてくると、大気の窓を塞ぐ効果があります。これが温暖化問題です。
地球はいかに幸せな場所か
大気の中でも特に僕たちを守ってくれているのは、高度10~50キロの成層圏にあるオゾン層です。紫外線は、エネルギーが高い順にUV-C、UV-B、UV-Aと分類されます。オゾン層は、エネルギーの高い320nm(ナノメートル)以下の波長であるUV-C、UV-Bを吸収してくれます。
だから、オゾン層は「厚さ3ミリメートルの宇宙服」とも呼ばれています。オゾン層の上の宇宙空間では、UV-CやUV-Bを直接浴びることになります。これらの紫外線は目の障害や皮膚がんを誘発させる恐れがあります。宇宙の中で地球がいかに幸せな場所なのか、ヒトは宇宙を知って初めて気が付くのかもしれませんね。
それにしても日光アレルギーの件はマズイなあ。このままだと、大好きなハワイに行っても外に出られないぞ。実にマズイ。(宇宙天気防災研究者)





![宍塚-2 [復元]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/06/9da1754895972ca256b67c07c0d7bf11-696x392.jpg)

![高校野球県大会組み合わせ抽選会・1[2305843009233841465]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/06/ae59b872d8bedeb35ff5b2d2f2db475d-696x392.jpg)