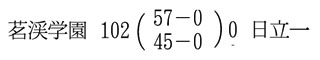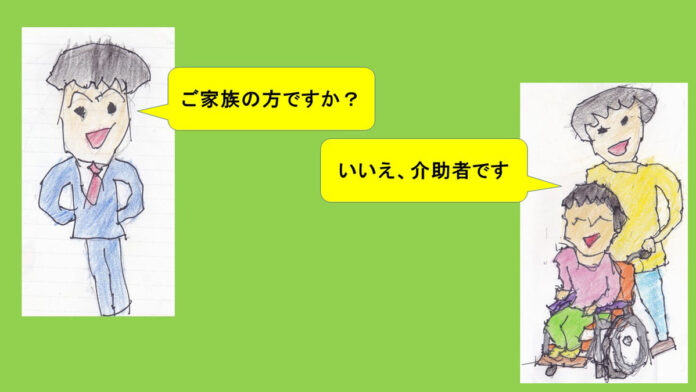つくば市谷田部の廃棄物運搬業者、江原工業所が、事業系ごみの一部を家庭ごみに不正に積み替えて、市のごみ焼却施設に搬出していた問題で(2020年9月1日付、18日付)、つくば市は、同社などを相手取って、本来得られたはずの事業系ごみの処理手数料など約1億円を損害賠償請求する方針だ。30日開会の12月議会に提案し、裁判所に訴えを起こす。
16年4月から20年1月まで3年10カ月間に本来得られたはずの損害金約1億85万円と、弁護士費用約1008万円、遅延賠償金などの支払いを求める。不正の期間や積み替えた量、算定方法などの根拠について市環境衛生課は、これから裁判になることなので「差し控えたい」としている。
市によると、訴えに先立って、9月22日に損害金の支払いを求める通知を出したが、支払い期限の10月22日までに支払いに応じなかった。
不正積み替え問題は2020年3月、元従業員が市に内部告発し発覚した。同年8月には「NHKから国民を守る党」(当時)が、不正積み替えを内部告発動画で配信し、市に抗議などが寄せられた。
江原工業所は当時、飲食店や事務所などから出る事業系ごみを収集・運搬する許可を市から受けていたほか、市の委託を受け、谷田部地区の一部で家庭ごみを収集していた。
事業系ごみは、廃棄物運搬業者が、ごみを出した事業所から収集運搬料を受け取り、市に10キロ190円(19年9月までは185円)の処理手数費を払って、市のごみ焼却施設に搬出する。一方、家庭ごみは無料で市のごみ焼却施設に搬出できる。
江原工業所は、収集した事業系ごみの一部を、処理手数量が無料の家庭ごみ収集車に移し替え、市に処理手数料を支払わす、ごみ焼却施設に搬出していたとされる。
市は2020年9月、不正な積み替えがあったとして、つくば警察署に被害届を出したほか、江原工業所に委託していた家庭ごみ収集委託契約を解除し、違約金約850万円を請求した。違約金は期限までに支払われた。一方、被害届は不起訴になったという。(鈴木宏子)



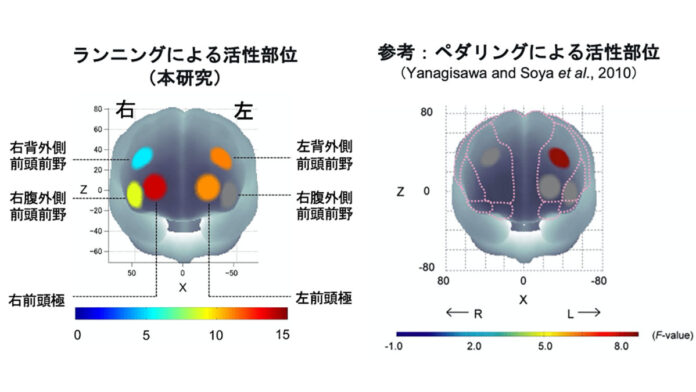
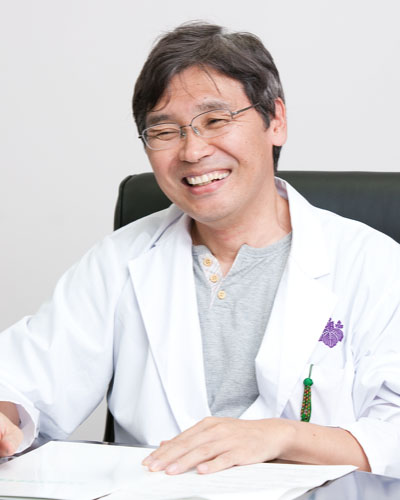

![宍塚大池_竹[2305843009271925446]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/11/30bac56663bb45270b8f14c3e4edea6c-696x392.jpg)


![古家晴美 31[2305843009267045513]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/11/7c29cbcf57d24ff569c01752baeaf1cb-696x392.jpg)

![斉藤裕之 98[7684]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/11/28c16a38154bc7c7eb74896ebcd1ac16-696x392.jpg)
![TX研究学園駅[7690]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/11/14c0dc2c8edec32844b929213a584a03-696x392.jpg)