【コラム・高橋恵一】少子高齢化を語るとき、1人の高齢者を働き盛りの年齢層が何人で支えるかを解りやすく表現するのに、イラストなどを用い、騎馬戦型(3人で1人)や肩車型(1人で1人)と呼んだりする。昔は4人で1人だったのに、今は2人弱で1人、将来は1人で1人を担ぐ肩車型になってしまい、世代間の不公平が進むなど、社会保障費の抑制を求める理由とされたりしている。特に、テレビや新聞などのメディアが安易にこの理論に乗ってしまっている。
元々、「年齢3区分別人口割合」は、国連が各国の人口構成をまとめたもので、開発途上国の現状や世界規模での高齢化を予測した統計である。生産年齢人口を15~64歳としたのも、途上国の現状を踏まえたものだ。65歳以上人口の割合が7%以上を高齢化社会、14%以上を高齢社会、21%以上を超高齢社会という。
しかし、この人口区分が現実と符合しないことは、お分かりだろう。日本の15~18歳は、大枠で就労人口に組入れられるだろうか。女性の就労率や、再雇用賃金の面から64歳まで生産年齢人口に換算できるのか。65歳以降の就労など、年齢人口区分の生産年齢人口と、就労・所得の人口割合とは、性格が異なるのだ。
さらに、生産年齢人口に対して、年少人口と高齢人口を合わせたものを従属人口と言う。つまり、騎馬戦の3人は、高齢者1人と年少人口3人を乗せていたのだ。肩車型では、高齢者1人と年少人口1人しか乗せないのだ。世代間負担の理屈は、年少人口の激減を考えなければ、それこそ不公平なのだ。
必要配分と応能負担の原則
高齢人口割合の上昇は、平均寿命の延びと年少人口割合の減少によるもので、日本の場合は、急激な出生人口の減少である。平均寿命の延びは、食糧事情の改善や生活環境の改善、医療水準の飛躍的発展、社会福祉サービスの向上などがあり、世界的にいえば、戦争や治安の悪化により理不尽に命が奪われることのないことだろう。
少子化については、生活水準の向上により、個人の時間や経済と出産・育児のバランスから、少子化はやむを得ない現象であり、人類社会の発展過程で、女性あるいは夫婦が最善の選択をした結果である。
少子高齢化を「国難」と言った総理大臣がいたが、個人の最適な生き方選択の結果が少子化であれば国難ではあるまい。長生きを遠慮させる国策などありえないだろう。
少子化の進行が人口をゼロにしてしまうわけではない。高齢化も無限ではなく、団塊の世代の山が、2040年くらいには平準化し、日本の人口は将来的には7000万人くらいで落ち着くはずだ。現在のドイツやフランス、英国並みの水準になり、人口密度は少々高めだが、海に囲まれ森林が豊富なので、安定した生活を維持できるだろう。
高度な福祉国家を維持する財源はどうするのか。世代間の負担の不公平はどうするのか。答えは簡単だ。「必要配分と応能負担の原則」。少子高齢化の波を正面から受け止め、安心で平和な政策と、それを正しく助長するメディアを望む。(地図好きの土浦人)


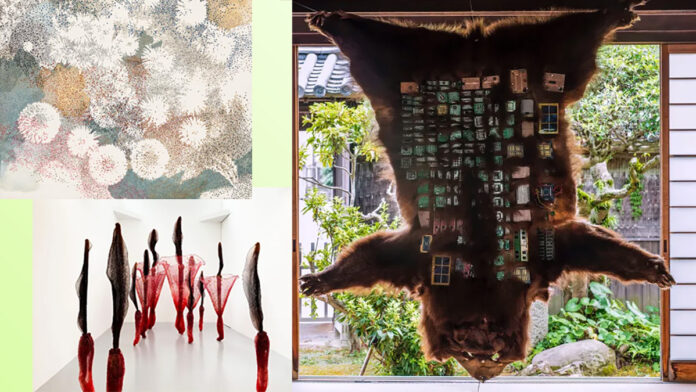

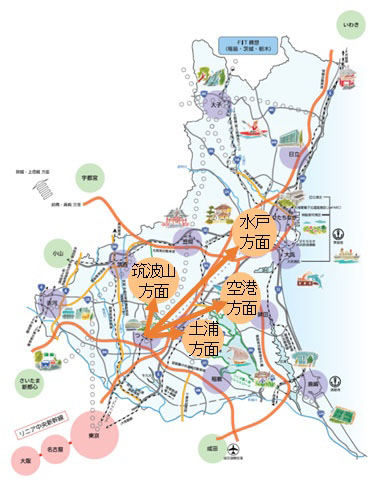






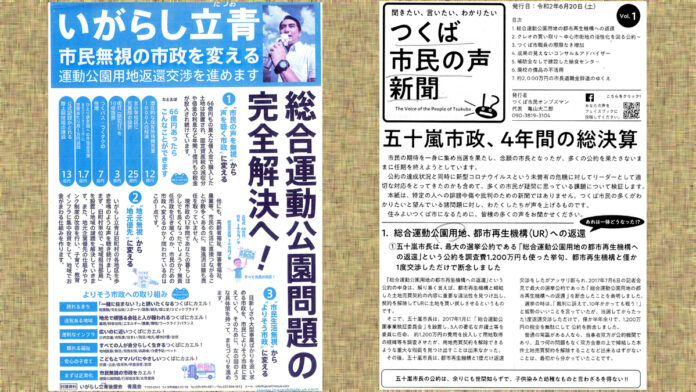

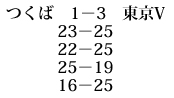






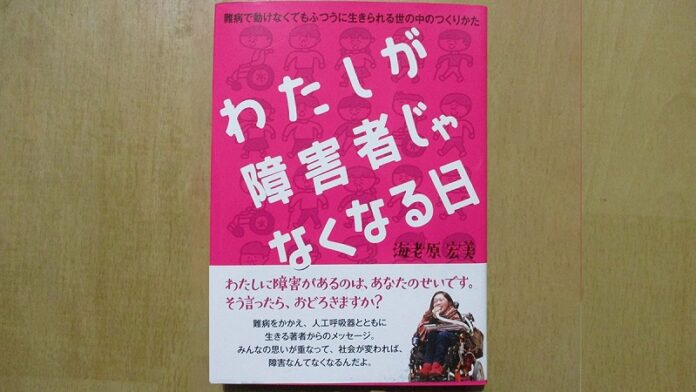

![くずかごの唄 102[2305843009278306955]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/02/858d2127203808a02d9a7dc4fc97a847-696x391.jpg)

![サイバーダインHAL[9185]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/02/7746e4eda262ee6750ab4e8d3f4e7c0f-696x391.jpg)
![川浪せつ子 44[2305843009277355696]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/02/a584640dc1385282af0ba35afc65e8a9-696x348.jpg)