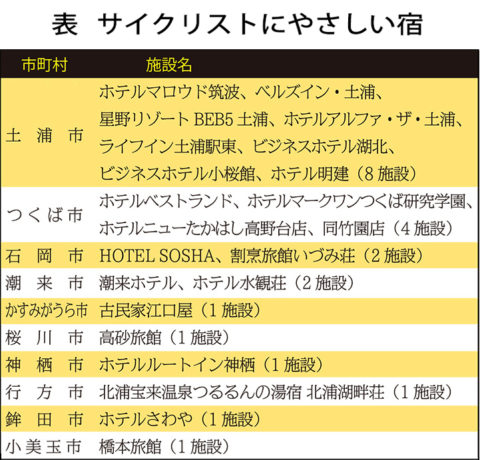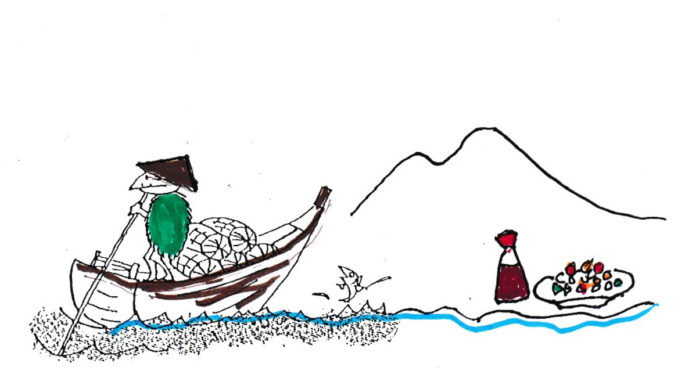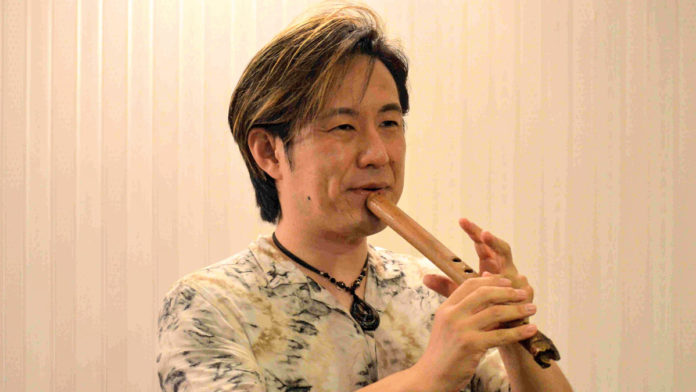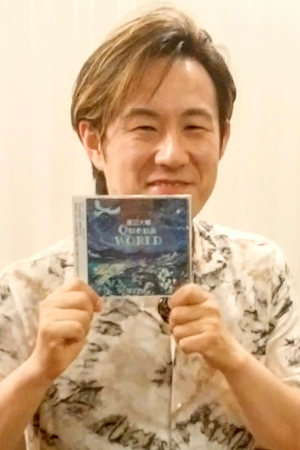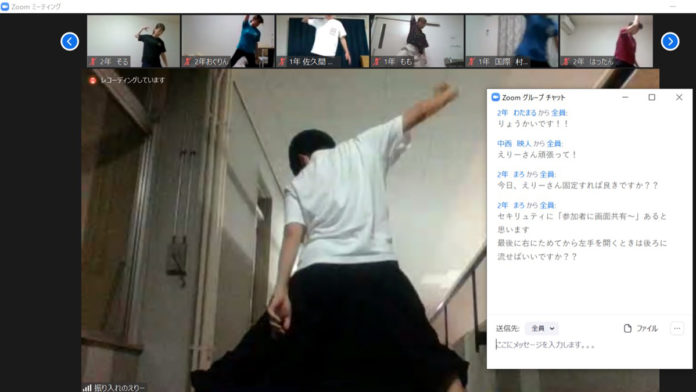【コラム・浅井和幸】30代男性のAさん。彼は借金をし、家賃を滞納していた。身よりもなく、人生の半分は家族とのつながりのない生活を送っている。こういった話を聞くと、怠け者で、誰ともコミュニケーションが取れないというイメージを持つかもしれないが、彼は嘘をつかず、人懐っこく、朗らかなしゃべり方をしていた。
複数のアルバイトをし、質素な生活をしている。しかし、職場の友人と遊ぶことにお金を使ってしまい、生活の基本に回せていない状況だった。お金を使ってでしか、人とつながれない寂しい状況だったのかもしれない。
アルバイトも長く続けていたけれど、新型コロナの影響が大きい分野で、出勤時間が減り、生活に支障をきたすようになった。それでも、一つのアルバイトは、正社員になれるかもしれないという期待もある。
私が「何か将来の夢か希望はありますか?」と聞いたら、「こんな自分がおこがましいのですけれど」と前置きし、「〇〇の店を自分で出せたら最高ですね」と答えてくれた。
なるほど、だから今のバイトなのかと納得した。そのバイトで足にけがをしたAさんだが、「これも仕事をしているのだからしょうがないです。それよりも、いろいろ技術や知識を得られるので楽しい」と、明るく答えてくれた。
おおよその収支を聞き取り、対策を考えてやり、彼は生活の立て直しを始めた。数年は苦しいだろうけど、頑張れば何とかなるだろう。「一緒に悩んでいきましょう」と言って別れたが、何かあるごとに相談の連絡があった。
「生活保護を受けた方がよいでしょうか?」
ある日、Aさんから「自分は生活保護を受けた方がよいでしょうか?」と、いつもと違う暗い声が電話から聞こえてきた。ある専門家から、そのようなアドバイスを受けたそうだ。
その人の考えは、働いても借金しなければいけない、家賃も払えない生活では、仕方がないだろうとのことだった。そんな状態で、辛い仕事をあえてする必要があるのかという理由も見え隠れしていた。
いくつかのアルバイトをしているAさんは、生活保護水準よりも少しだけ収入は高かった。私は、Aさんの希望や仕事に対する考え方も聞いていたので、疑問が沸き上がった。
仕事は辛いか? 働くのは嫌か? 働かない生活、医療費に困らない生活保護の方により魅力を感じるか? その他、いくつかの質問をしてみた。
仕事は辛いこともあるが、嫌ではない。むしろ、やりたい職種であるし、人に「ありがとう」と言ってもらえるし、やりがいがあるという答だった。
今、人生すべての決定をする必要はないが、その時点では、生活保護ではなく、働いて自分の希望に近づく道を選んだ。働くことは、お金を稼ぐことだけではなく、人とのつながり、人に感謝してもらう喜びを感じられる場でもあるのだから。(精神保健福祉士)