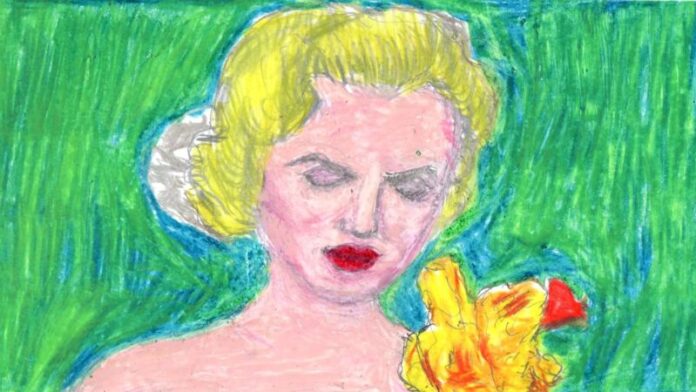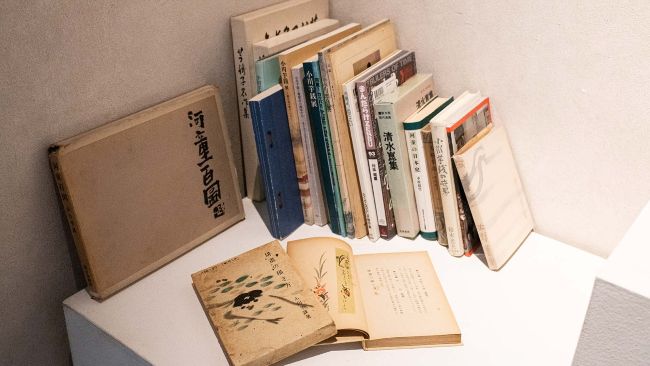【コラム・小泉裕司】第94回土浦全国花火大会(11月1日)は、競技開始を知らせる直径約24センチの 8号玉5段雷花火が筒から打ち上げ後すぐに爆発、いわゆる過早発(8月17日掲載コラム参照)で、会場の数万人の脳裏に「中止」の二文字がよぎったに違いない。
通常、イベント開催を知らせる雷花火は直径12センチの4号玉なので、2倍の大きさがある。使用の機会はまれだ。安全確認後、プログラムは再開したが、それまでの13分間は、ただただ無事を祈るばかり。再開後は、前線の影響か、例年の風向きとは異なる南風で、観覧席や付近の住宅にガラが舞う夜となったが、大会は無事終了した。
それでは、恒例の「振り返り」をしよう。まずは競技の全体印象だが、2025年の総決算の大会と言って間違いないだろう。その中でも茨城勢と秋田勢、そして山梨勢の強さが際立つ大会となった。特に、夏の大曲全国花火競技大会で内閣総理大臣賞を受賞した野村花火工業(水戸市)のグランドスラム達成は圧巻だった。
10号玉の部(直径30センチの尺玉1発)
 10号玉の部優勝の「昇り曲導付五重芯変化菊」(井上準二さん提供)
10号玉の部優勝の「昇り曲導付五重芯変化菊」(井上準二さん提供)
上位を占めたのは、やはり五重芯の作品。8作品のうち、優勝した野村花火工業、準優勝の山﨑煙火製造所(つくば市)の五重芯は、安定度抜群で甲乙付けがたい完成度。山﨑煙火のこれまでと異なる色の組み合わせが多少順位に影響したのかも知れないが、僅差(きんさ)であったことは間違いない。
2007年に四重芯花火を完成させた菊屋小幡花火店(群馬県)の五重芯も、昨年あたりから安定度が格段に増している。こうした多重芯が優位の中、入賞したマルゴー(山梨県)の「昇り曲付超(スーパー)変化菊」は、十八番の点滅系花火で、いわゆる自由玉の部類。
自由玉が進化すればするほど、こうした自由玉と多重芯花火を同じまな板の上で採点することについて、花火師や観客から違和感を指摘する声が聞かれる。この点、実行委員会ではすでに数年前から課題としているが、具体的解決策が見えておらず、早期の解決が待たれるところだ。
創造花火の部(直径15センチの5号玉7発)
18回目の優勝を飾ったのは、北日本花火興業(秋田県)の「赤いキツネと緑のタヌキ」。この日、会場で最も大きな歓声が湧いた作品だ。キツネは3匹中1匹、タヌキは4匹中3匹が審査委員側に顔を向けたが、この技術とアイデアこそ「型物花火の神様」と言われるゆえんだ。
社長の今野義和さん(61)は、昨年「現代の名工」に選ばれ、今月には「黄綬褒章」を受賞するなど、日本煙火史に残る卓越した成果を残し続けている。
準優勝は芳賀火工(宮城県)の「ラッパでドレミ」、特等は加藤煙火(愛知県)「今が旬!ドクドクきのこ」の2作品。これらを含めた上位3作品は、老若男女、誰にもわかりやすいデザイン。大きな拍手が審査員の採点を後押ししたに違いない。
打ち上げ順番が早い作品は高得点が出にくいと言われるが、それを実感したのが26番伊那火工掘内煙火店(長野県)の「幸せのクリスマスツリー」。7発一斉打ち上げはこれまで見たことがない。落ちるときに段階的に輝く彩色千輪の段咲きは、打ち上げや開発のタイミングを計算し尽くしたチャレンジングな作品で、まさに「創造花火」の秀作と言える。
審査員のみなさんには、前半とは言え「いいもの」には、勇気を持って高得点を付けていただきたい。
スターマインの部(直径12センチの4号玉以下400発以内)
 スターマインの部優勝の「颯爽と吹く風になって」(井上準二さん提供)
スターマインの部優勝の「颯爽と吹く風になって」(井上準二さん提供)
優勝した野村花火の「颯爽と吹く風になって」は、選曲センスが抜群。ピアニストよみぃさんの演奏によるTVアニメ「とある科学の超電磁砲」 のオープニング曲は、アップテンポで疾走感のあるメロディー。十八番の野村ブルーとグリーンを基調とした八方咲き、輪菊、蜂など手抜きのない名花ばかりが、まさに駆け抜けるように音楽とシンクロ。お見事の一言に尽きる。
準優勝の山﨑煙火の「感情反転~愛と憎悪~」は、奇しくも野村花火と同じピアの曲を採用。ピアニスト清塚真也さんの「恋」と「怒りのともしび」の2曲をシーンごとに使い分けて、紅色のハート花火、牡丹、千輪菊などの連打に加えて、ひときわ大きな音を出す万雷を効果的に散りばめながら、愛情から憎しみへの激しい心の変化を表現した。
名作ぞろいの大会だったが、順位を分けたのは保安点、つまり落下による減点ではないだろうか。例年以上に多かったように感じた。その点、上位3作品は、垂れ落ちる星を一定の高さで消失するよう、見事にコントロールされていた。
内閣総理大臣賞受賞コメント
 第94回全国花火競技大会表彰式(土浦市提供)
第94回全国花火競技大会表彰式(土浦市提供)
大会翌日2日の表彰式では、受賞者を代表して、内閣総理大臣賞を受賞した野村花火工業社長の野村陽一さんが謝辞を述べた。今回の受賞で土浦の花火13回、大曲の花火10回と、合わせて前人未踏の23回目の受賞を果たした。
「多くの花火業者が土浦に参加していただくことで多くの学びがある。花火の世界はWhyの連続。1歩進んで、2歩下がるどころか11歩下がってしまうこともある。そんな多くの課題を乗り越えて今があるが、数多の成績は、父との研究開発の成果だ。その私を、技術的にすでに超えた弟子の山口花火師とともに、100周年の土浦の花火がさらに発展するよう、さらには、みなさんに夢と感動を与えられるような花火づくりにこれからも取り組んでいきたい。」
それにしても、1年のうちに石破総理と高市総理2人の総理大臣から表彰された花火師は、史上初ではないだろうか。めでたし、めでたし。大会の無事開催を祝い「ドーン ドーン ドーン!」。(花火鑑賞士、元土浦市副市長)