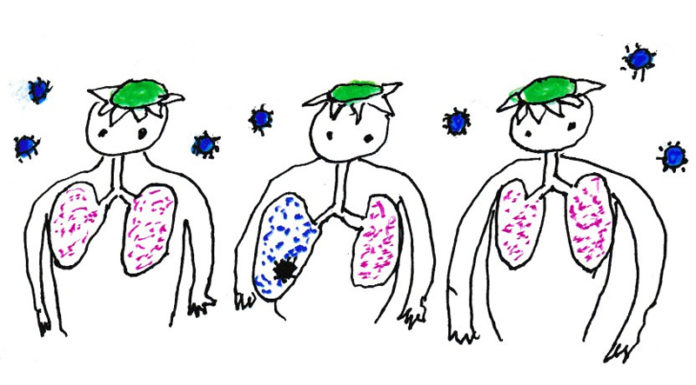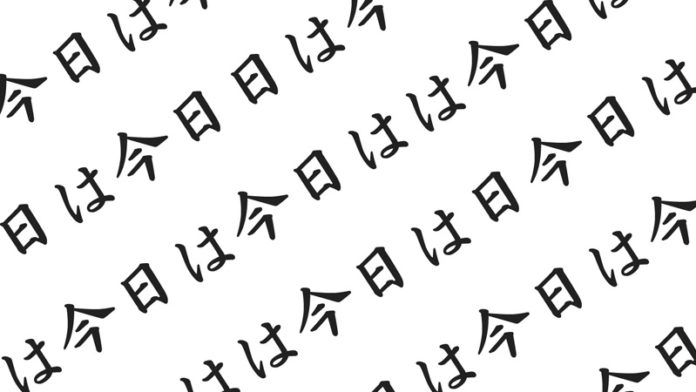病気療養休暇を申請した際、病院の領収書を偽造したとして、つくば市は7日、市水道工務課水道監視センターの男性係長(59)を同日付けで停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
市上下水道総務課によると、係長は、2019年2月5日から7日までの3日間、療養休暇の取得を申請した。申請の際は、受診した医療機関の領収書のコピーを添付するが、係長は、過去に病院からもらった領収書の日付部分を偽造して提出し、虚偽の申請と報告を行って不正に休暇と給与を得ようとしたとされる。
提出された領収書のコピーが不自然だったことから、市が原本の提出を求めたところ、係長は当初「シュレッダーにかけたので原本はない」「病院で再発行してもらえないと言われた」などと釈明していた。
しかしその後、偽造を認め「体調不良で休んだが、有給休暇(年20日間)を使い切ってしまったので領収書を偽造した。その日は病院には行かなかったが自宅で療養していた」などと話したという。
市は早々に偽造に気付き療養休暇ではなく欠勤扱いとしたため、休んだ3日分の給与は係長に支払われておらず実害は出ていないという。
一方、有印私文書偽造に当たることから、市は19年9月、警察に被害届を出し、同年12月、係長は起訴猶予処分となった。
刑法上の処分が決定したのを受けて、市は、再調査の上、市職員の懲戒処分基準に基づき処分を決定した。
五十嵐立青市長は「市の職員が市民の信頼を裏切り、多大なるご迷惑をお掛けしたことを心からお詫びします。行政に対する市民の不信を招く許されざる行為であり、今後、さらに綱紀の保持を徹底させます」とするコメントを発表した。