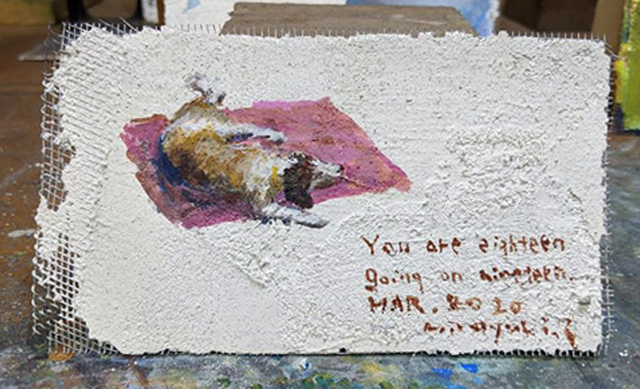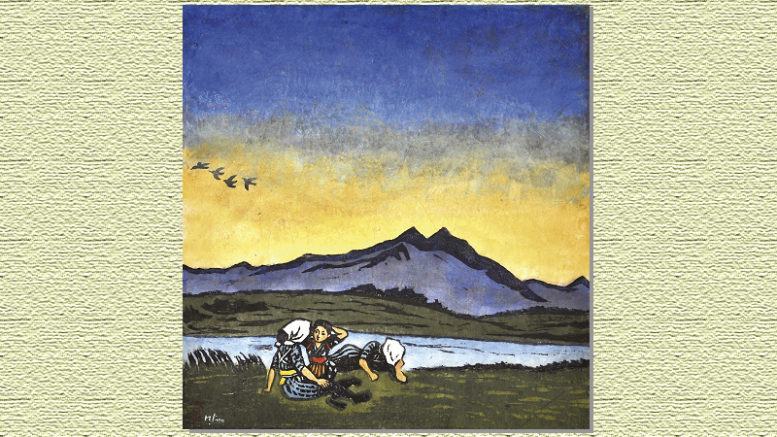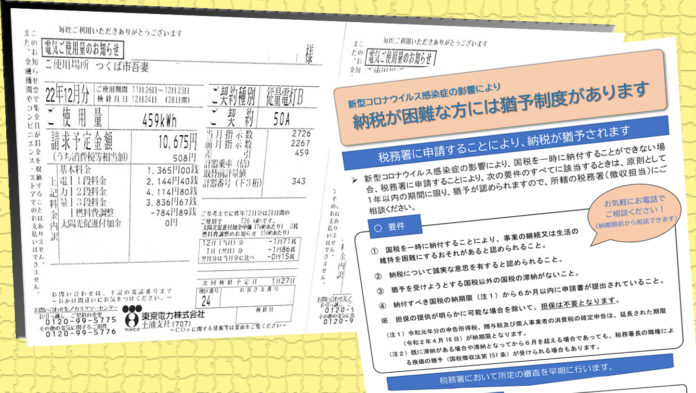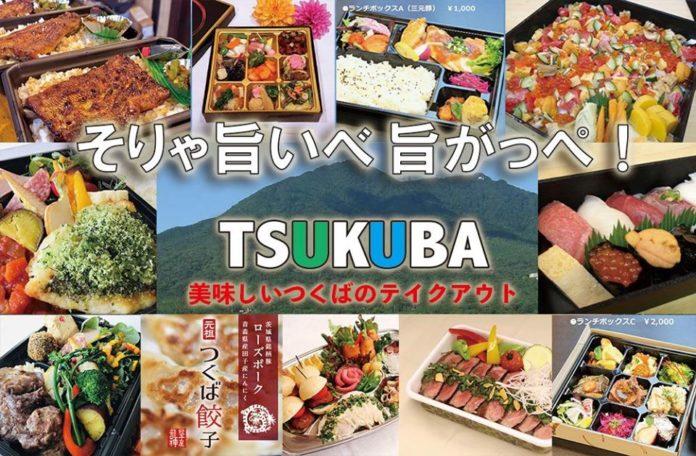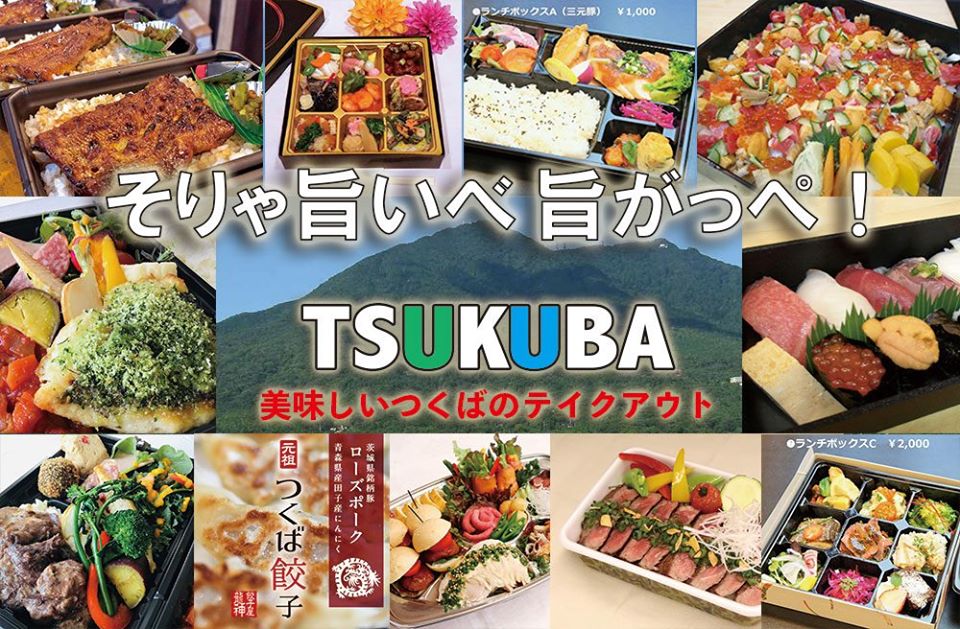【コラム・奧井登美子】「きょうはお祖父さまの命日。お花を忘れないであげて下さい」。2月10日、兄の奥井勝二から必ず電話がかかってくる。
兄は千葉大学医学部の外科教授であった。成田日赤病院の院長をしていたこともある。ものすごく忙しい人なのに、祖父の死は頭から離れないようだ。彼がまっすぐ医学の道に進んだのも、母親から何回も聞かされた、祖父のスペイン風邪による死がきっかけだったのかも知れない。
祖父の平沢有一郎は、茨城県初の薬剤師国家試験合格者。北里柴三郎は福沢諭吉の援助で、「土筆ヶ岡(つくしがおか)養生園」という日本初の結核療養所を芝の白金三光町につくるが、祖父は北里柴三郎を尊敬し、明治28年(1895)までそこに勤務している。
奥井家に婿に来て、薬局をつくった。娘の教育も国際的で、外国人と交際し、英会話を習得させ、外国に留学させる夢を持っていたという。しかし、1918年、流行のウイルス性疾患のスペイン風邪により、53歳で亡くなってしまった。
母は留学をあきらめ、薬剤師免許を取得して薬局を継ぎ、幼い妹たちを育てた。有一郎の死は、奥井家にとっても存亡の危機であったらしい。
世界の死者は2000万~4000万
当時、ウイルス性疾患の怖さは、世間では不明。医者にも、一般の人にも、よく解らない。まさに、深刻な医療崩壊であったという。医療崩壊に翻弄(ほんろう)された日本人の残酷さを、私も、母から痛いほど聞かされた。
森岡恭彦(もりおか・やすひこ)先生からいただいた本「医学の近代史 苦闘の道のりをたどる」(NHKブックス)を読むと、1918年のスペイン風邪で、日本人の死者は推計48万2000人、世界の死者は2000万~4000万人とある。
今のように、疾患別死者の統計がキチンとされてなかった時代とはいえ、48万人という数字はあまりに大きい。
昔と違って、今は、世界の医療情報がすぐにネットやテレビで公開される。知恵を絞って、新型コロナウイルスを鎮静させることができるか。人類とウイルスの永遠の戦いは、当分終わりそうもない。(随筆家、薬剤師)