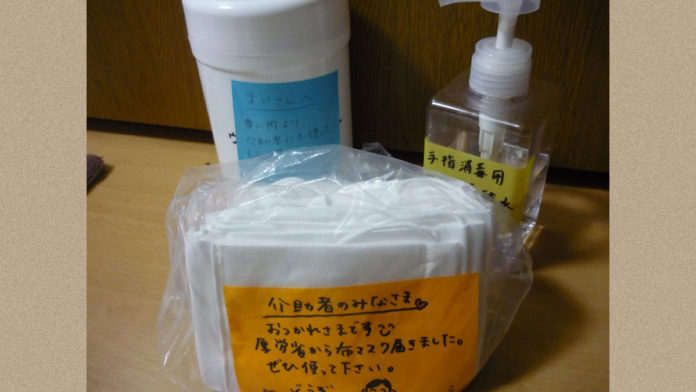【コラム・及川ひろみ】日本は、亜寒帯から亜熱帯にまたがる大小の島々からなり、屈曲に富んだ海岸線と起伏の多い山岳など、変化に富んだ地形や、各地の気候風土に育まれた多様な動植物相が見られます。
多様な生態系(高山帯・森林草原・里地里山・湖沼・砂浜・磯藻場干潟・サンゴ礁・島嶼)のそれぞれについて、環境省では全国1000カ所程度のモニタリングサイトを設け、基礎的な環境情報の収集を長期にわたって(100年)継続し、日本の自然環境の質的・量的な劣化を早期に把握することを目的に調査を行っています。
調査は記録を残すことだけが目的ではありません。結果を生かすことこそが大切なのではと、われわれは環境省のシンポジウムで質問しました。変化を捉えたなら、素早く保全に生かすことが調査の目的ではないかと主張しました。(環境省のHPには調査の目的に保全に生かすとは書かれていないことが残念です)
モニタリング調査を行う環境省の方針のもと、里地里山の調査内容について、日本自然保護協会が専門家、市民2団体と調査・検討を開始したのは2003年のことです。昆虫・植物・土壌・動物・水質などの調査項目が挙がる中、生態系を捉える上で、昆虫より上位に位置する動物の調査が必要だと提案した結果、アカガエルの卵塊調査、哺乳動物調査の項目が入り、試行錯誤をしながら、調査を開始しました。
より正確に里山の自然環境を把握
環境省は里地里山モニタリング調査を、当初、専門家に委託することを考えていました。しかし、身近な自然環境である里地里山調査は、年数回やって来る専門家による調査より、専門性を持った市民が足しげく通って調査する方が、より正確な里山の自然環境の把握ができるのではないか―と思い、(公財)日本自然保護協会と当会が2006年2月、モニタリングシンポジウムを土浦市民会館で開催しました。
そのとき、環境省「モニタリング1000」担当者を前に、これまで行ってきた市民調査を発表した結果、里地里山モニタリング調査は市民団体が行うことになり、その取りまとめを日本自然保護協会が行うという、現在の体制が確立しました。
市民調査と言っても、モニタリング調査に求められることは、正確さと全国一律の方法で実施することです。専門家が各サイトに出かけ、調査の正確さと手法(マニュアル)の指導を行うことで、この問題を解決しました。
われわれの会は、里地里山コアサイトとして、生物相調査(毎月)、アカガエルの卵塊(1~4月)、野鳥(繁殖期・越冬期)、中型哺乳類(5~10月)、カヤネズミ(6月・11月)、チョウルートセンサス(4~11月)、水質(年4回)―の調査を行っています。(宍塚の自然と歴史の会代表)