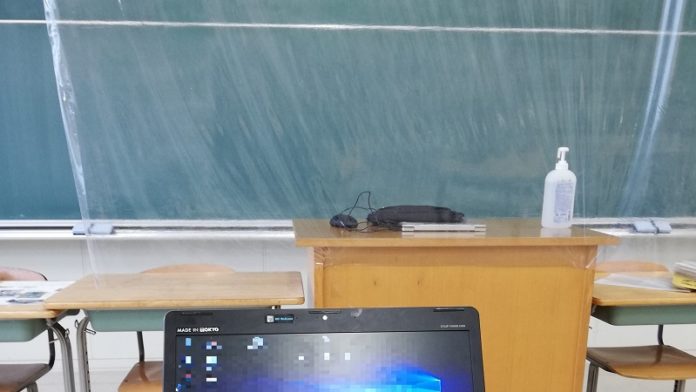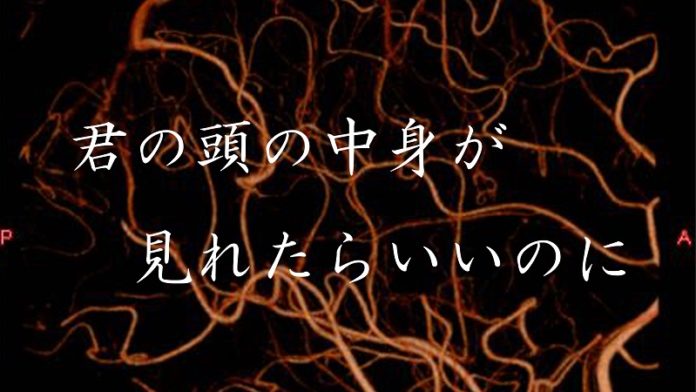【田中めぐみ】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休校により、勤務する中高一貫校で4月からオンラインでのリアルタイム授業が始まった。
学習用端末の普及で実現
土浦市の土浦日本大学中等教育学校で高校生に古文を教えている。文科省のGIGAスクール構想に先駆けて、本校では以前より生徒1人に1台ノートパソコンを支給し授業で活用していたことや、スマートフォンなどの普及で自宅でも情報端末に困らない環境にあることが後押しとなった。
通信ネットワークの問題はどうか。総務省の要請により、4月からドコモ、KDDI、ソフトバンクの携帯キャリアは容量超過後も50GBまで無料、テザリング=メモ=オプションも追加無料となった。自宅にインターネット回線がなくても容量超過を気にすることなく授業が受けられるようになり、こちらもクリアできた。
教材や課題はデジタルデータ化し、学校ホームページやクラウドにアップして共有する。生徒らは自宅のプリンターで印刷して準備し授業に臨む。中にはプリンターを持っていないという生徒もいるが、画面上で教材データを見てノートで解いている。
国語の教科ではどうしても大量の文字を読まなければならない。スマホから接続している生徒も多いため、最初は文字が小さくて見えないのではないかという懸念があり、「見えますか?」という問いかけを頻繁にしていたが、ピンチアウト(画面を拡大する操作)を使い慣れている生徒たちに特に心配はいらなかった。
教材をデジタル化
黒板やホワイトボードに書いたものを映すのでは見えにくいため、今まで板書して説明していたものをデジタル化する必要がある。教材の文章をOCR(印刷された文字をスキャナーやデジタルカメラによって読みとりデジタルデータ化する技術)でデータ化し、文を引用しながら要点を解説するスライドを作った。
だが、スライドではアドリブがきかない。生徒の様子を見ながら説明する順序を変えたり補足したりするのに、板書の方が良い部分もある。
スライドやPDFファイルにそのまま書き込む方法を考え、10年ほど前に買ったペンタブレットを出してきた。書き込みながら説明ができるように設定し、なんとなくの授業スタイルができあがった。
準備に長時間
教科指導におけるICT(情報通信技術)の活用ということが現実味を帯びて議論され始めたのは10年ほど前からではないだろうか。15年前はスマートフォンも普及しておらず、スキャナーやOCRなど電子テキストデータ化の技術も実用に足るレベルではなかった。当時はうまく認識しないソフトや周辺機器と格闘し、一晩費やしたことも一度や二度ではない。
それが今や一瞬だ。スマートフォンの進化にも比例する技術発達の恩恵をひしひしと感じる。新型コロナウイルスの感染拡大がもし15年前に起きていたとしたら、休校になっても泣き寝入りするしかなかったに違いない。
しかし、技術の進歩はあっても授業の準備にはかなり時間がかかる。プリントを印刷する時間が一切無くなったのは良い点だが、体感的に教室で行う授業準備の3~5倍の時間を費やしている。それでいてたくさんの情報を伝えようとすると難しい。通常の授業と同様の内容で一度はスライドを作ったものの、情報量が多くなりすぎていると感じてスライドの枚数を間引くこともあった。
生徒、教師、双方とも慣れていないせいもあるが、現段階ではリアルの教室よりも伝えられることが少なくなっているように感じる。
(続く)
※メモ
【テザリング】モバイルデータ通信ができる端末を利用してPC、タブレットなどをインターネットに接続すること。