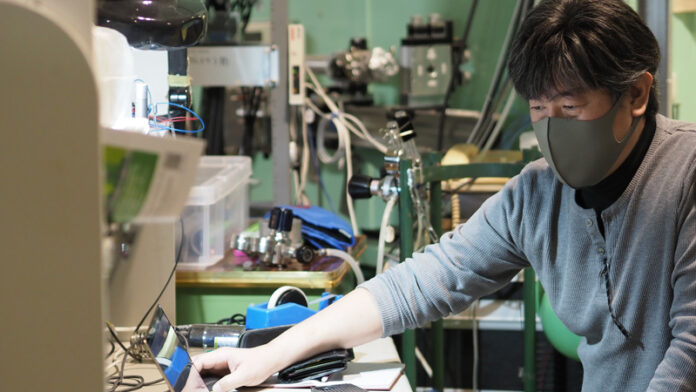【コラム・浅井和幸】かなり前から、何度も何度も繰り返し言っているのに、何も改善されない。そのように感じる人は多いのではないでしょうか。それは、社会に対してかも知れないし、知り合いに対してかも知れないし、家族に対してかも知れません。ときには、自分に対して感じることもあるかもしれませんね。
「人は変えられない、自分は変えられる」ということを鵜呑(うの)みにする必要はありません。私たちはコミュニケーションをとって相手に影響を与え、相手が変わることも経験しているはずです。批判をすることも悪いことではなく、批判をすることで改善されることだってあるでしょう。
しかし、何度も繰り返し伝えているのに変わらないと感じたときに、どのような手段を今後とっていくか、とらえ直すことは大切なことです。もちろん、同じ手段を重ねることも、黙って相手が変わるのを待つことも一つの手段として有効なことはあります。ですが、多くの場面では、同じ要素が集まれば、同じ結果が表れるのは当然で、結果、同じことが繰り返されます。
例えば、「宿題やれ」とか「もっとまじめに考えろ」とか「お菓子を食べるな」とか「不正をなくせ」とかの言葉を、同じ状況で、同じように繰り返し伝えたところで、そこに集まる要素は変わらないので、材料が同じであれば同じ現象が起こり、改善されません。批判を伝える相手が敵対しているならば、同じ現象が起こるどころか、批判とは反対の方向に進み、事態は悪化します。
足りない何かを足すことが必要
もし、同じ言動を繰り返しても変わらないのであれば、そして変えたいと思うのであれば、足りない何かを足す必要があります。それが、その相手と味方の関係になることなのか、むしろその相手は無視して自分が行動してしまうのか、別の批判の仕方をするのか、足りない何かを探し試します。足りない何かは、自分がすべて背負う必要はなく、他の誰か志を共有できる誰かに動いてもらってもよいかもしれません。
また、言動を変えるということで言えば、批判をやめるということでプラスに転じることがあります。学校に行けと言わなくなることで登校できるようになったり、お互いの短所を言い合うことをやめることで、連携して物事を解決できるようになったりする例はたくさんあります。「廊下は危ないから走るな」よりも「廊下は静かに歩いた方が安全だよ」と伝えたほうがよいことがあります。
私が相談を受けてアドバイスをするときに、「来年も落第したら、もう大学をやめてもらうからな」というよりも、「あと3年は大学の費用を出す協力はできるからな」と伝えるようにとアドバイスをする場面が多くあります。「ある何かができないと、悪い未来が待っているからな」と伝え、その後に続く「だから、そうならないように頑張れよ」という言葉を端折(はしょ)ってしまうと、不安をさらに上乗せしてしまいますので、お気を付けください。(精神保健福祉士)



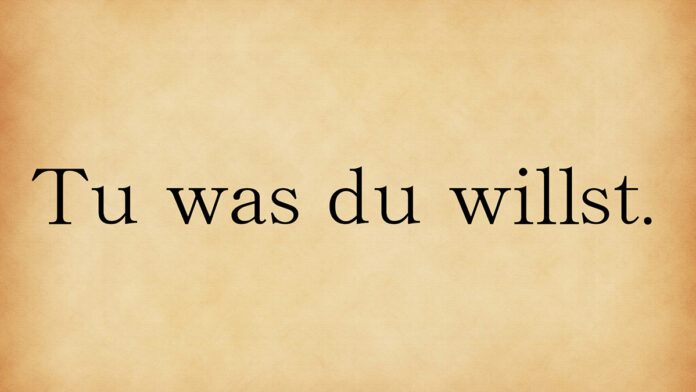

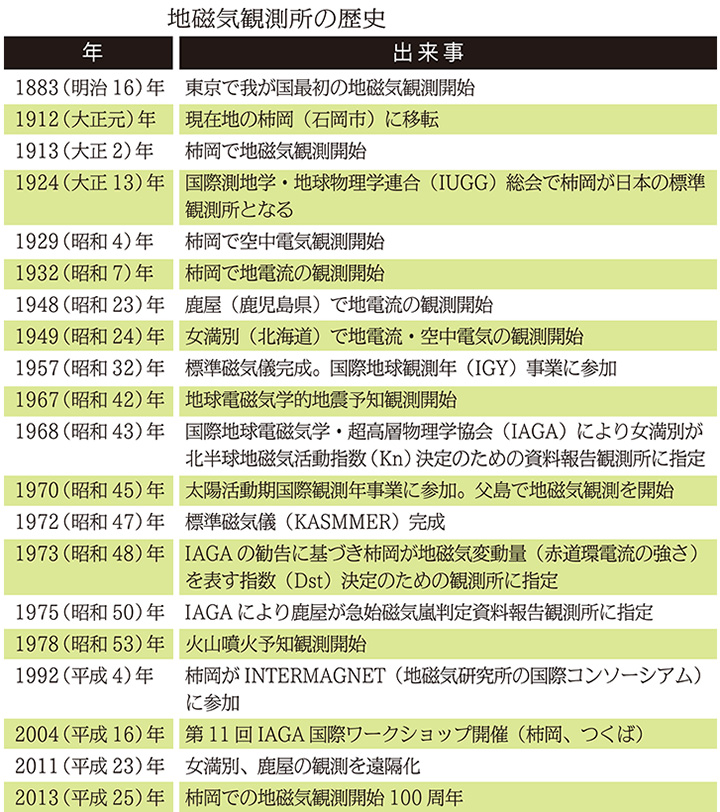





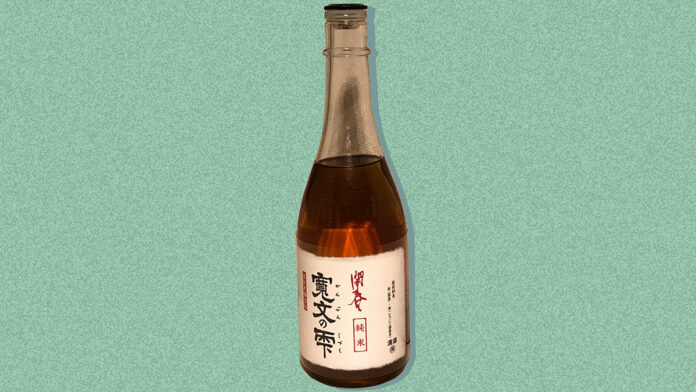


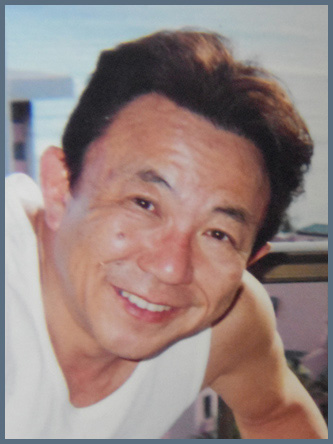



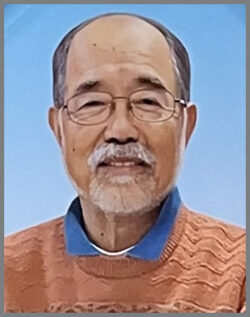

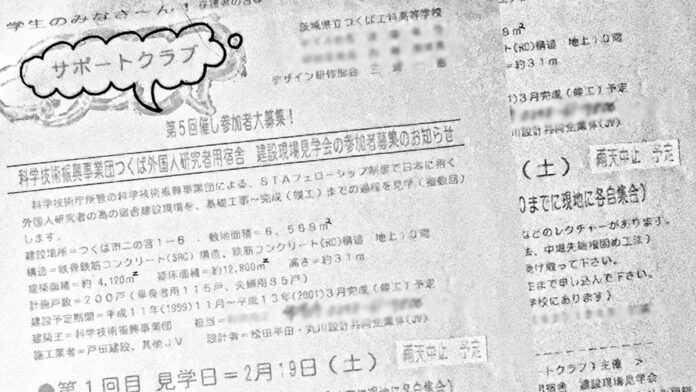








![邑から日本を見る 90[4263]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/06/2a12fbc27eeffa348ffecce1922d219e-696x392.jpg)