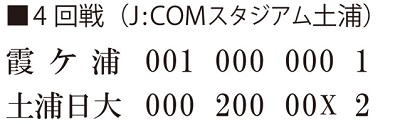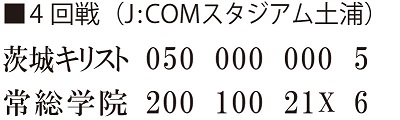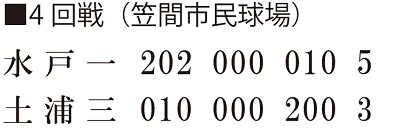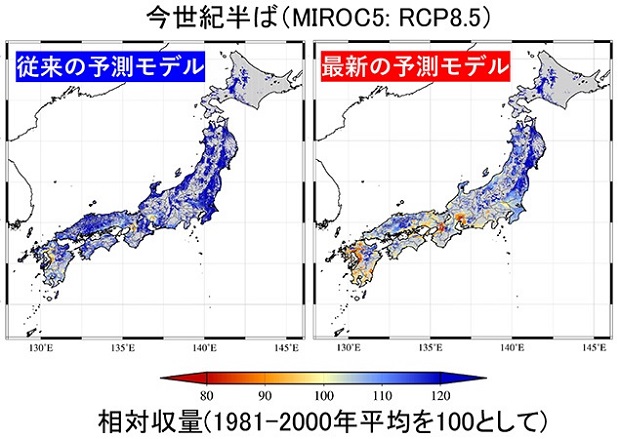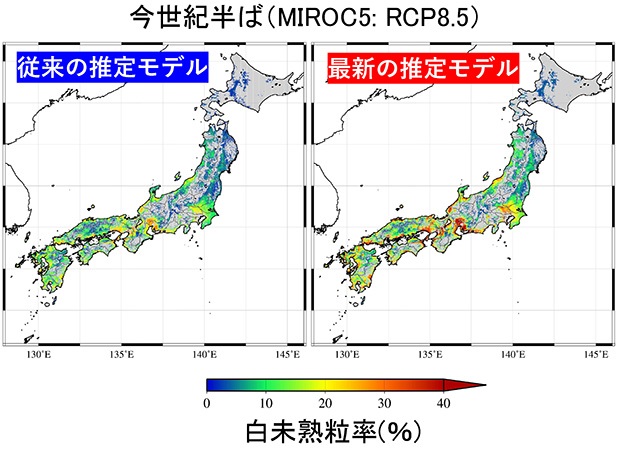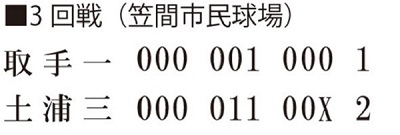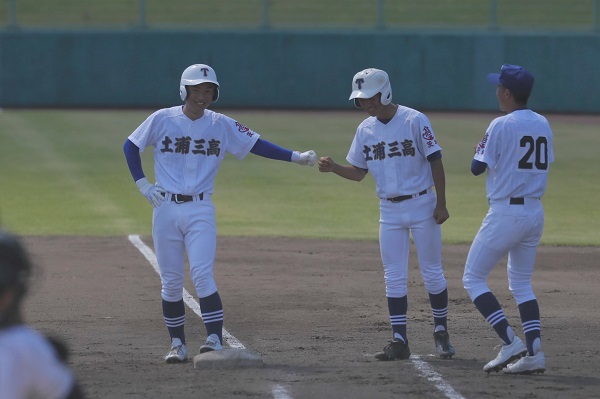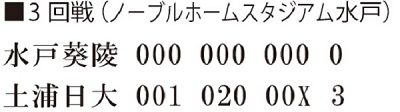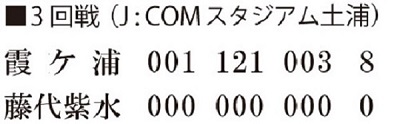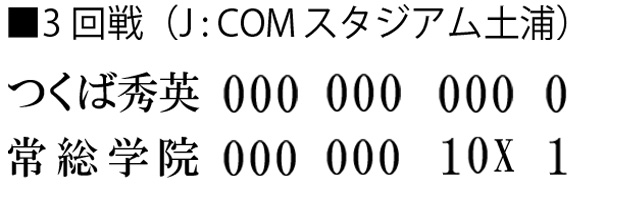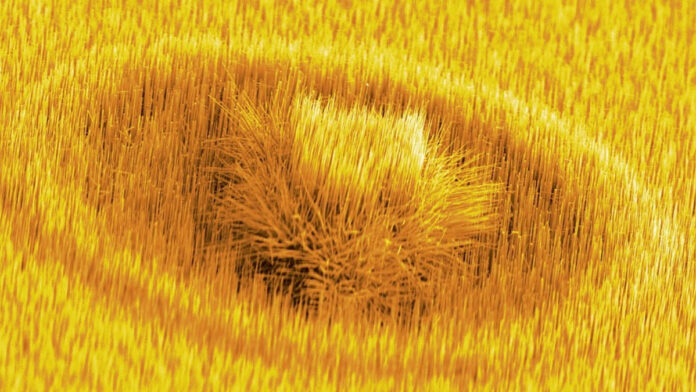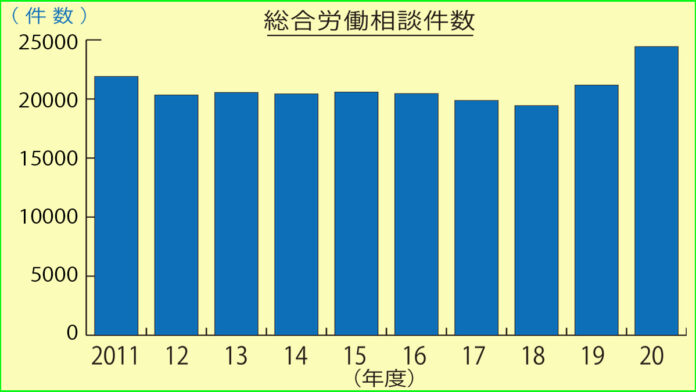【コラム・斉藤裕之】生後10日を過ぎてやっと名前が決まった孫。乳もよく飲むし夜泣きもほとんどしない。我が子の場合と違って、目鼻や耳、頭の形や髪の毛など、双方の祖父母の顔まで思い浮かべて、何がどう遺伝しているのか、誰に似ているのか、大げさに言えば、大昔からつながる、そしてこの先つながっていく命の不思議をも感じてしまう始末で、まあいずれにしても、なかなかいい面構えをしていると、ひとりニヤける。
それから、今どきはよくできたもので、旦那さんも長い育休をとって、おむつを替えたり寝かしつけたりで、ここ1カ月はにぎやかに暮らしているのだが、カミさんと2人暮らしのときと比べて、飯の支度やら洗濯やらが意外に大変で、寝床につくときには冷蔵庫の中を思い出しながら明日の献立を考えたりする自分がいたり、梅雨時は洗濯物も乾かないので近所のコインランドリーに朝6時に出かけたら、何台もの乾燥機が回っていることに驚くやら。
そうこうしているうちにも、コロナの勢いは衰えるどころか、東京は緊急事態宣言下でどうやらオリンピックは開かれることとなり、何とも複雑な夏を迎えることとなった。
粭島での作品展は延期
それとは関係ない?関係なくもない?が、何かと家にいる時間が長くなった私を見て、「どこかで働いてきなさい」という指令がカミさんから下された。どこかでと言われても、いまさら雇ってくれるところもないのだが、カミさんの目論見としては、かねてからお誘いのあった草刈りのバイトに行けということらしい。
草を刈る場所は、高低差10メートル、幅数10メートルほどのノリ面。上り下りするだけでも大変だが、刈り取ったカヤやササの葉は滑りやすく、斜面で足を踏ん張りながらの作業。炎天下、汗の量も半端ではない。幸い雇い主が親しい友人ということに甘えて、「半日しかできないよ」と宣言して始めたが、朝8時から始めてお昼には限界が来る。おまけに刈り終えた斜面からまた順番に草が生えてきて、「終わらない夏」の予感。
肉体労働は汗をかいた分のお給金をもらえるので嫌いではない。「アリとキリギリス」という寓話を思い出す。お金が無くなると肉体労働をするしかなかった。そこはアリ的に生きてきたのだが、人から見れば、やはり絵描きはキリギリスなのかもしれない。つまり私は「アリギリス」? しかし、キリギリスとはギリシャっぽい和名で何とも面白い。
残念だが、この夏に予定していた故郷の粭島(すくもじま)での作品展は延期することにした。もう少しすっきりしないと、小さな島とはいえ、いや小さな島だからこそ人を呼び入れることははばかられる。日々変わる孫の顔が見られないのはちと寂しいが、またカミさんとの2人の暮らしに戻る。刈るのをためらったアザミが夏空に赤い花を咲かせている。(画家)

![斉藤裕之 90[2305843009235941421]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/26f90825b8f411f03977ae34863806a8-696x447.jpg)

![2021-07-21 NIMS[4840]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-21-NIMS4840-696x392.jpg)