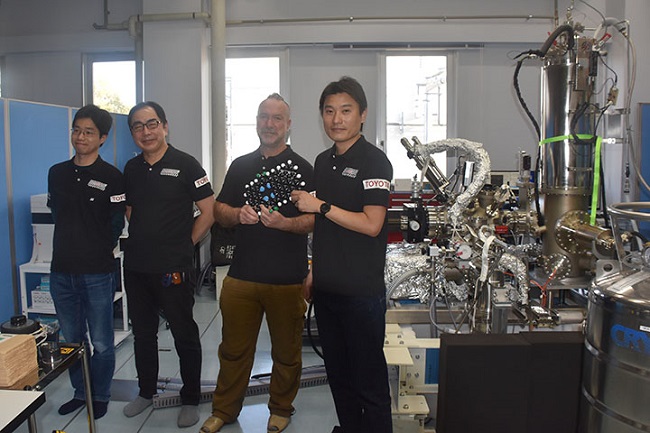つくば市は18日、4月1日付け組織改編と人事異動を内示した。政策強化を図る組織改編として、国内の国際交流のみならず海外の諸都市との連携を図るため、市民部市民活動課の課内室だった「国際交流室」を「国際都市推進課」に格上げし、市長公室に移設する。
内閣府国家戦略特区諮問会議からスーパーシティ特区の指定を受けたことなど、スマートシティの実現に向けた取り組みを具体化するため、政策イノベーション部の「スマートシティ戦略室」を「スマートシティ戦略課」に格上げする。
複数の部署に分かれていた子供に対する支援を一体化するため「福祉部社会福祉課こども未来室」と「こども部こども政策課子育て相談室」を統合し、こども部に「こども未来課」を新設する。
地方公営企業の上下水道事業は、組織の合理化を図るため「上下水道局」を新設する。
異動の規模は20.4%の267人(消防本部等を除く)で、前年度同様、業務の継続性を重視し、専門性、効率性を高めるため必要最低限の異動とするとしている。
4月1日付の全職員数は前年度より35人増えて2004人になる。定年退職者は51人、普通退職者は37人、新規採用職員は76人、再任用職員は134人。
女性管理職の割合は、消防本部を除き、2021年度の25%から22年度は25.3%になる。
国や県との人事交流は、引き続き文科省出身職員を政策イノベーション部長に配置する。国、県などに実務研修生6人を配置する。
任期付き職員として、学校などの特別支援教育に豊富な知識と経験がある人材を特別支援教育推進室長に配置するほか、学校にICT(情報通信技術)指導員を3人配置する。幼稚園長に、幼稚園や小中学校の現場で管理職として働いた経験のある人材5人を配置する。
国際都市推進課長に岸田和克子市長公室統括政策監
4月1日付人事異動は以下の通り。カッコ内は現職。敬称略。
【部長級】
▽政策イノベーション部長兼市長公室政策調整監(政策イノベーション部長)森祐介
▽市民部長(市民部次長)大久保克己
▽福祉部長(保健部次長)安曽貞夫
▽こども部長(市長公室次長兼秘書課長兼広報監)塚本浩行
▽都市計画部長(都市計画部次長兼都市計画課長)大里和也
▽上下水道局長(生活環境部次長)坂入善晴
▽消防長(消防本部消防次長)木村勝平
【次長級】
▽総務部次長(政策イノベーション部次長)杉山晃
▽政策イノベーション部次長(企画経営課長)大越勝之
▽市民部次長(生活環境部環境政策課長)池畑浩
▽市民部地区担当監兼地区相談課長(市民部市民活動課長)大木茂樹
▽市民部地区担当監・大穂相談センター所長、再任用(消防長)植木利男
▽市民部地区担当監・豊里相談センター所長(生活環境部次長)野原浩司
▽市民部地区担当監・谷田部相談センター所長、再任用(総務部総務政策監、再任用)藤後誠
▽市民部地区担当監・桜相談センター所長(生活環境部次長)嶋崎道徳
▽市民部地区担当監・筑波相談センター所長(福祉部次長)吉原衛
▽市民部地区担当監・茎崎相談センター駐在、再任用(財務部財務政策監、再任用)髙野正美
▽福祉部次長(障害福祉課長)根本祥代
▽保健部次長(福祉部高齢福祉課長)中根英明
▽こども部次長(幼児保育課長)吉沼浩美
▽経済部次長(都市計画部次長)岡田克己
▽都市計画部次長兼都市計画政策監、再任用(都市計画部長、再任用)中根祐一
▽都市計画部市街地振興監(教育局次長)貝塚厚
▽生活環境部次長(市民部スポーツ振興課長)伊藤智治
▽上下水道局次長(総務部次長)中泉繁美
▽会計管理者(財務部次長)飯島正志
▽教育局次長(教育局次長兼教育施設課長)飯泉法男
▽教育局次長(経済部産業振興課長)久保田靖彦
▽消防本部消防次長・消防本部担当(同・消防署担当)五月女謙次
▽消防本部消防次長(消防救助課長)青木孝徳
▽消防本部主任参事兼中央消防署長(消防総務課長)小島幸司
▽消防本部主任参事兼消防指令課長(消防指令課長)山田和美
【課長級】
▽市長公室秘書課長(秘書課長補佐)伊藤尚美
▽市長公室国際都市推進課長(統括政策監兼企画監)岸田和克子
▽政策イノベーション部企画経営課長(生活環境部環境政策課長補佐)横田裕治
▽政策イノベーション部科学技術振興課長(科学技術振興課スタートアップ推進室長兼産業振興センター所長)前島吉亮
▽政策イノベーション部スマートシティ戦略課長(科学技術振興課スマートシティ戦略室長)中山秀之
▽財務部管財課公共施設マネジメント推進室長(都市計画部建築指導課長)吉田和行
▽財務部納税課長兼徴税管理監(納税課長補佐兼徴税監)柳田賢一
▽市民部市民活動課長(地区相談課長)荒澤浩俊
▽市民部市民活動センター所長、再任用(こども部長)中山由美
▽市民部大穂窓口センター所長(文化芸術課長)日下由美子
▽市民部豊里窓口センター所長(豊里窓口センター所長、課長補佐級)伊藤紀子
▽市民部谷田部窓口センター所長(経済部農業政策課長)垣内伸之
▽市民部桜窓口センター所長(大穂窓口センター所長)中川和子
▽市民部筑波窓口センター所長(教育局生涯学習推進課長)大久保文子
▽市民部茎崎窓口センター所長(谷田部窓口センター所長)宮本孝雄
▽市民部副地区担当監、大穂相談センター駐在(オンブズマン事務局長)栗山正行
▽市民部副地区担当監、大穂相談センター駐在(保健部国民健康保険課長)木澤伸治
▽市民部副地区担当監、谷田部相談センター駐在(建設部道路管理課長)色川英雄
▽市民部副地区担当監、桜相談センター駐在(大穂相談センター駐在)渡辺寛明
▽市民部副地区担当監、筑波相談センター駐在(桜相談センター駐在)御田寺義郎
▽市民部副地区担当監、筑波相談センター駐在(福祉部社会福祉課長)安田正幸
▽市民部スポーツ振興課長(政策イノベーション部科学技術振興課長) 岡野渡
▽市民部スポーツ振興課参事、つくば市スポーツ協会派遣、再任用(市民部長)横田修一
▽市民部文化芸術課長(文化芸術課長補佐兼係長)矢口治重
▽福祉部社会福祉課長兼非課税世帯等給付金室長(社会福祉課長補佐兼係長兼非課税世帯等給付金室長)相澤幸男
▽福祉部障害福祉課長(障害福祉課長補佐)岡田治美
▽福祉部高齢福祉課長(医療年金課長)日下永一
▽保健部国民健康保険課長(社会福祉課長補佐兼企画監)飯村修
▽保健部医療年金課長(医療年金課長補佐)城取美知枝
▽保健部健康増進課感染症対策室長(こども部こども政策課長)美野本玲子
▽保健部健康増進課新型コロナウイルスワクチン接種対策室長(中央図書館副館長兼視聴覚センター所長)松浦智恵子
▽保健部健康増進施設いきいきプラザ館長、再任用(福祉部長)津野義章
▽こども部こども政策課長(保健部健康増進課長補佐)鈴木加代子
▽こども部こども未来課長(福祉部社会福祉課こども未来室長)中澤真寿美
▽こども部幼児保育課長(幼児保育課長補佐)岩田光弘
▽経済部産業振興課長(財務部管財課公共施設マネジメント推進室長)柳町哲雄
▽経済部農業政策課長(農業政策課長補佐)根本隆
▽経済部観光推進課長(観光推進課ジオパーク室長)伊藤祐二
▽都市計画部都市計画課長(周辺市街地振興課長補佐)大久保正巳
▽都市計画部周辺市街地振興課長(周辺市街地振興課長補佐)吉岡誠生
▽都市計画部建築指導課長(建築指導課長補佐)中泉弘行
▽建設部道路管理課長(建設部道路管理課長補佐)石塚一弘
▽生活環境部環境政策課長(経済部産業振興課経済支援室長)渡邊俊吾
▽上下水道局水道総務課長(生活環境部上下水道総務課長)小吹正通
▽上下水道局下水道総務課長(財務部管財課長補佐)桜井克仁
▽上下水道局上下水道業務課長(生活環境部水道業務課長)本山雅之
▽上下水道局水道工務課長(生活環境部水道工務課長)植木亨
▽上下水道局水道監視センター所長(経済部観光推進課長)兼平勝司
▽上下水道局下水道工務課長(生活環境部下水道課長)渡辺高則
▽教育局教育施設課長(建設部公共施設整備課長補佐兼係長)鈴木聡
▽教育局生涯学習推進課長(教育総務課長補佐兼企画監)澤頭由紀子
▽中央図書館副館長(政策イノベーション部企画経営課長補佐兼オリンピック・パラリンピック推進室長)沼尻祐一
▽選挙管理委員会事務局副局長(政策イノベーション部企画経営課持続可能都市戦略室長)吉岡直人
▽オンブズマン事務局長、再任用(市民部地区担当監、筑波相談センター所長)木村徳一
▽消防本部消防救助課長(予防広報課長)鈴木浩
▽消防本部消防総務課長(消防救助課長補佐)廣瀬好
▽消防本部予防広報課長(予防広報課長補佐兼危険物係長)高野順一
▽北消防署長(中央消防署並木分署長)太田義春
▽中央消防署参事兼中央消防署副署長(中央消防署副署長)細田義美
▽北消防署参事兼筑波分署長(中央消防署豊里分署長)青木節
【退職】3月31日付
▽市民部長 横田修一
▽市民部主幹、つくば市国際交流協会派遣 飯村通治
▽福祉部長 津野義章
▽こども部長 中山由美
▽消防長 植木利男
▽市民部地区担当監・筑波相談センター所長 木村徳一
▽経済部次長 中澤正登
▽会計管理者 酒井作徳
▽消防本部兼中央消防署消防監 東郷道明
▽消防本部主任参事兼北消防署長 山田勝
▽財務部納税課長兼徴税管理監 上方和男
▽市民部副地区担当監・大穂相談センター所長 矢島正弘
▽市民部副地区担当監・谷田部相談センター所長 秋葉芳行
▽市民部副地区担当監・桜相談センター所長 関口正昭
▽市民部副地区担当監・筑波相談センター駐在 星野和也




![西口正隆学芸員[10190]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/03/d2b19b7c07d4a8454fb6dd8a2c57b54b-696x392.jpg)
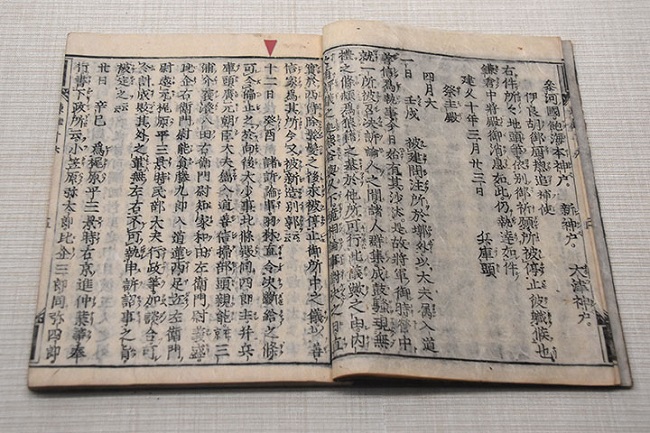
![川端舞 28[10155]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/03/3f633051ef23b984373a45baa11e61bb-696x392.jpg)


![奥井登美子 104[10153]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/03/14e9f1c8999b55d745d523fc38095ac8-696x392.jpg)
![岩崎教授[10160]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/03/6aa495a8f788d339534889e6850920f8-696x392.jpg)


![川浪せつ子 45[2305843009281695504]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/03/19c54caf937c17ffdcd0a284c40f8e3b-696x348.jpg)
![ドライバーを務める川井さん[2305843009281706804]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/03/39307e9bc501be5d141bffd30fe8a9c9-696x392.jpg)