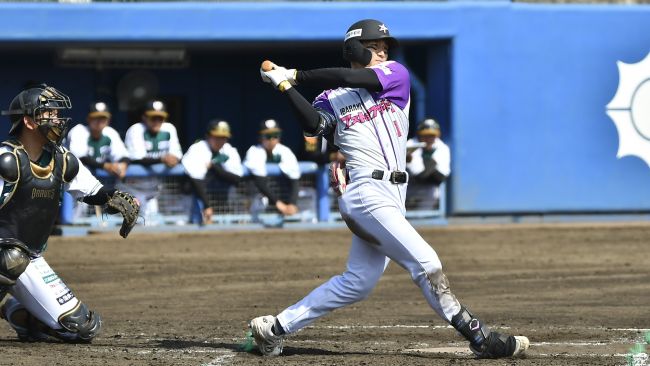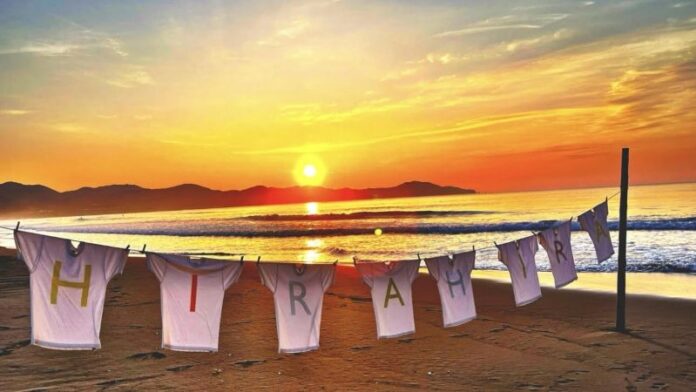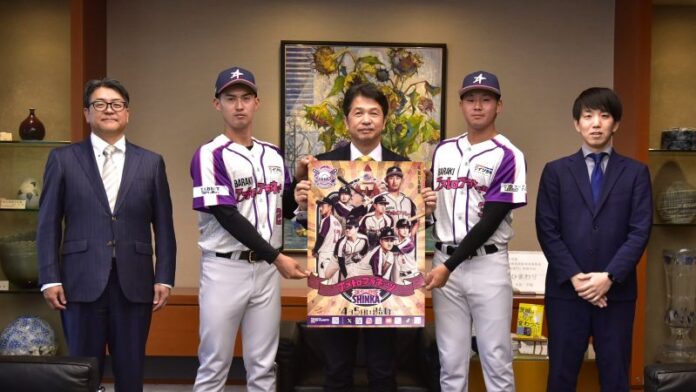【コラム・坂本栄】新年度に入りました。4月からコラム欄の構成を少し変えます。これとの関連で、5月から新しい執筆者に参加してもらいます。コラムは原則として1日1本ですが、行政記事や催事記事とは色合いの違うコラムを引き続きお楽しみください。
執筆回数は月1回に統一
これまでの執筆者は、月2回の方、月1回の方、隔月の方に分かれていました(ほかに随時出稿の方も)。4月からは月2回を止め、月1回に統一します(隔月執筆はそのまま)。仕事で多忙の方もおり、月2回はきついとの声が寄せられたからです。月2回の田口哲郎さんは研究活動の都合もあり、109回(3月29日掲載)が最後になりました。
研究学園駅周辺の地域活動を紹介してもらった「けんがくひろば」は、15回(2月25日掲載)が最終回になりました。題材が尽きてきたとのことで、4月から「随時」に移ってもらいます。12回(24年11月7日掲載)の後、忙しくて休載が続いた医療通訳の松永悠さんも「随時」に移行します。
親友の瀧田君が昨秋逝去
告知はしませんでしたが、国際政治について独自の分析を執筆してくれた瀧田薫さん(茨城キリスト教大学名誉教授)は2024年秋、逝去されました。バイデンとトランプが争う米大統領選挙の構造を取り上げた62回(24年8月4日掲載)が最後です。
瀧田さんは、幼稚園-小学校-中学校-高校の同級生でした。土浦聖母幼稚園(土浦市大町)の第1回卒園で、いろいろな場でいろいろ議論してきました。彼の茨キリ大での専門分野は国際政治、私の通信社での専門分野は国際経済でしたから、「解」を見つけるための情報をお互いに補完できました。田中角栄は米情報機関によって抹殺されたとの陰謀論については盛り上がりました。
茨キリ大で、彼は常務理事として大学運営にも携わっていました。経営学部を立ち上げた後、「新しい学部で兼任講師として国際経済を教えてくれないか」と誘われました。もちろん私は快諾し、毎週1回、大学がある日立市まで常磐高速道を飛ばしました。若い同僚講師との懇親会、好奇心あふれる学生との交流は実に愉快でした。
水戸の元広報課長も参加
逝去、多忙などで生じた「穴」は埋めていきます。2月から古本屋店主の岡田富朗さん(初回は2月1日掲載)に加わってもらいましたが、5月からは写真家の海老原信一さん、元水戸市課長の沼田誠さんにも参加してもらいます。海老原さんは鳥類の撮影が得意で、毎回2枚アップしてもらいます。今休載中のオダギ秀一さん(直近は1月16日掲載)に続き、写真家は2人目です。
沼田さんは、水戸市の「みとの魅力発信課長」を務めていました。変わった組織名ですが、他の役所で言えば広報課長に当たります。数年前に市役所を辞め、今はつくば市に住み、環境問題や街づくりの分野で活躍しています。好奇心が強い方で、水戸地域の話だけでなく、「水戸っぽ」の視点から学園都市のことも書いてもらいます。
ほかの執筆者についても、現在リクルート活動を続けています。独自の視点や面白い話題を提供してもらい、ネット媒体ならではのコラムにしたいと思います。ご期待ください。(NEWSつくば理事長)