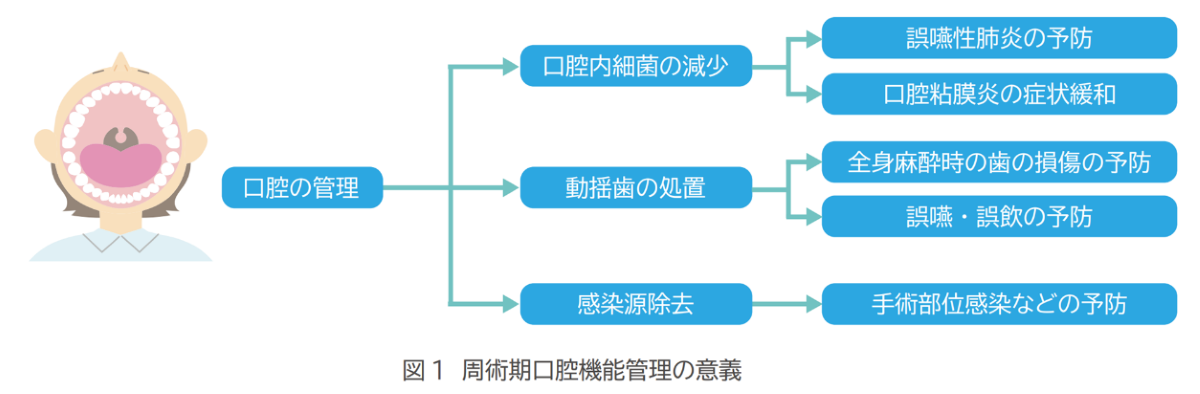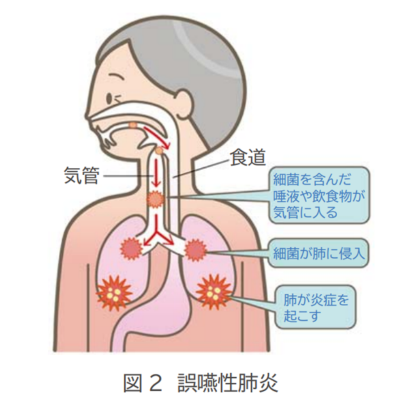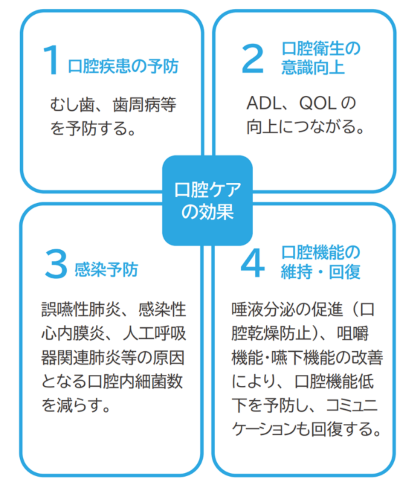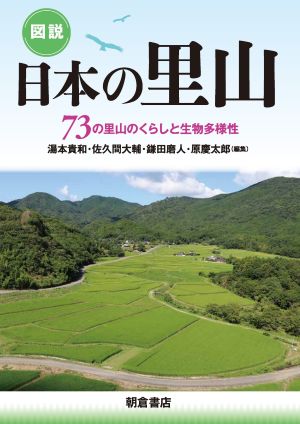人獣共通の寄生虫を媒介
茨城県内で飼われていた猫が今年5月、マダニにかまれ、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)に感染して死んだ。6月には県内の40代男性が、渡航先の欧州でマダニにかまれライム病を発症した。いずれもマダニが媒介する人獣共通のウイルスが原因だ。自身がマダニにかまれないようにするにはどうすればいいのか、ペットの犬や猫をどう守るのか。寄生虫学が専門で、マダニが媒介する寄生虫など人獣共通寄生虫病の予防に取り組む麻布大学(神奈川県相模原市)獣医学部寄生虫学研究室の平健介教授に聞いた。
関東で初
 平健介教授
平健介教授
―5月にマダニにかまれて死んだ猫は、マダニが媒介するウイルスによりSFTSに感染しました。SFTSは主に関西での感染例が多かったのですが、ペットの猫が感染し死んだのは関東で初めてです。STFSとはどういった感染症ですか。
平 SFTSウイルスによって引き起こされるウイルス感染症であり、このウイルスを持つマダニの吸血時に人や動物が感染します。
―マダニにかまれると人も動物も感染するのですか。
平 マダニに吸血された人が誰でも発症するわけではなく、発症や重症化リスクは年齢によって異なります。特に高齢者や持病がある人は注意が必要です。
―感染した場合、人、動物それぞれ、どのような症状が出ますか。致死率は。
平 人が感染した場合の症状は、マダニにかまれてから1〜2週間後に、主に発熱,倦怠感,頭痛がみられます。その後,嘔吐,下痢,食欲不振などの消化器症状が現れます。人の致死率は10〜30%程度とされます。70歳以上の高齢者では死亡リスクが高く,若年層では軽症または無症状であることが多いです。
一方、野生動物は発症することが少ないですが、猫や犬は発症しやすい。猫の致死率は60〜70%以上,犬では10〜30%程度と報告されています。
全国的に分布広がる
―今回、関東で初めて飼いネコが発症したことについてどう思われますか?
平 関東以北でもSFTSウイルスを持つマダニが増えつつあり,人や動物への感染において警戒が一層重要になります。
北海道でも感染マダニが確認されており,全国的に分布が広がっています。まずは(人もペットも)マダニにかまれないように対策を徹底することが,効果的な予防になります。
―人とペットそれぞれの具体的な予防方法や対策は?
平 マダニは草むらや雑木林などの野外環境に広く生息し、野生動物の通り道に多くみられます。そのため人は、草むらや林に入る際は,長袖・長ズボン,足首を覆う靴下や帽子を着用し、虫よけスプレーを使用することを勧めます。帰宅後に衣類や体にマダニが付着していないか確認することを習慣づけることも重要です。
ペットにはマダニ予防薬を定期的に投与し、散歩後はブラッシングや体表のチェックを習慣的に行うことがマダニ対策として有効です。
野外で具合の悪そうな野良ネコや野生動物を見掛けても、絶対に素手で触らないことも重要。市町村の環境課や保健所など公的機関に連絡してください。
 口を皮膚の中に深く差し込んでイノシシを吸血するフタトゲチマダニ。吸血すると体長は10ミリ程度になる=平健介教授提供
口を皮膚の中に深く差し込んでイノシシを吸血するフタトゲチマダニ。吸血すると体長は10ミリ程度になる=平健介教授提供
―万が一、マダニにかまれたらどうすればいいですか?
平 もしかまれたら、人もペットも医療機関や動物病院を受診したほうがいいです。人もペットも、マダニは皮膚に口を深く差し込んで固着しており,自分で無理に引き抜くと口が皮膚に残ることが多々あります。
やむを得ず自分で除去する場合は,マダニ専用ピンセット等を用いて,マダニの体部に圧をかけないようにして,口の根元をつまんで慎重に引き抜きぬく。マダニの口の部分が皮膚に残らないように気を付ける必要があります。除去したマダニは密閉して保管し診察時に持参すると診断の参考になります。
事前に動物病院に連絡を
―もしペットにSFTSの疑いがあって動物病院に行く場合の注意点はありますか。
平 SFTSを疑って動物病院に行く場合は、感染動物から飼い主や他の動物,獣医師への感染リスクがあるため、受診前に必ず動物病院に連絡し,感染対策の準備を依頼してください。
SFTSウイルスは,感染した動物の血液やだ液,体液を介して人にも感染することもあるため、飼い主も手袋・長袖・マスクなどで防護し,ペットとの接触は最小限にとどめるべきです。ペットの運搬には密閉できるケージを使用したほうが良いです。
 筆者の飼い猫。マダニにかまれないよう守りたい
筆者の飼い猫。マダニにかまれないよう守りたい
県、市町村が注意呼び掛け
県生活衛生課によると、5月に死んだのは1歳のメスネコ。室内飼育だったが、4月下旬屋外に出てしまった時に、マダニに刺されたとみられるという。動物病院でダニを除去したが、5月9日に高熱、嘔吐、食欲低下が見られたため再度動物病院を受診。治療したものの12日に死んだ。動物病院がSTFS を疑い12日に県に連絡、検体の血液を検査したところ、15日にSTFSウイルス陽性とわかった。
県では、関西だけでなく北陸地方や東海地方でも近年、SFTSが発生していることから関東にもいると想定。ウイルスがどの程度広がっているかを動物から把握するため、今年3月から県獣医師会に所属している動物病院を対象に、疑わしい症例があった場合は検査を依頼していた矢先だった。
一方、6月にライム病を発症した男性は、5月下旬に滞在していた欧州でマダニにかまれたと推定されている。6月9日に倦怠感、10日に紅斑が出て医療機関を受診した。現在は快方に向かっているという。県内でライム病が発生したのは2017年9月以来、8年ぶり。
県生活衛生課は、県内44市町村に対して5月に猫が死んだ事案を知らせ、注意喚起を促している。ダニが媒介する人獣共通の寄生虫はSFTSやライム病のほか、日本紅斑(こうはん)熱などもあるため、人もペットも注意してほしいとSNSなどで警戒を呼び掛ける。つくば市や土浦市でも市の公式サイトなどで注意を呼び掛けている。(伊藤悦子)