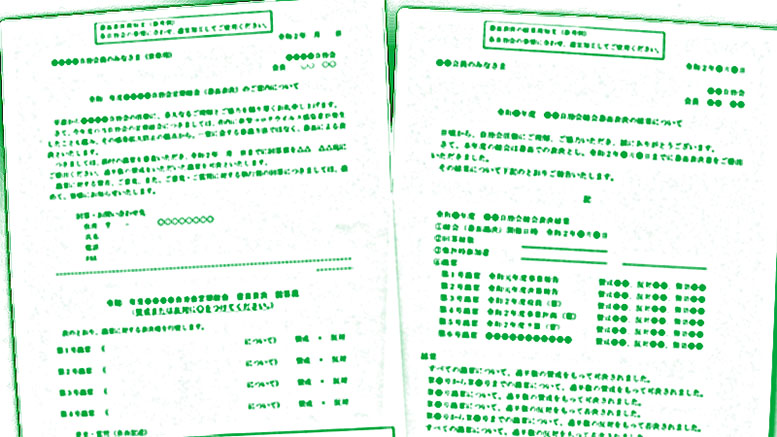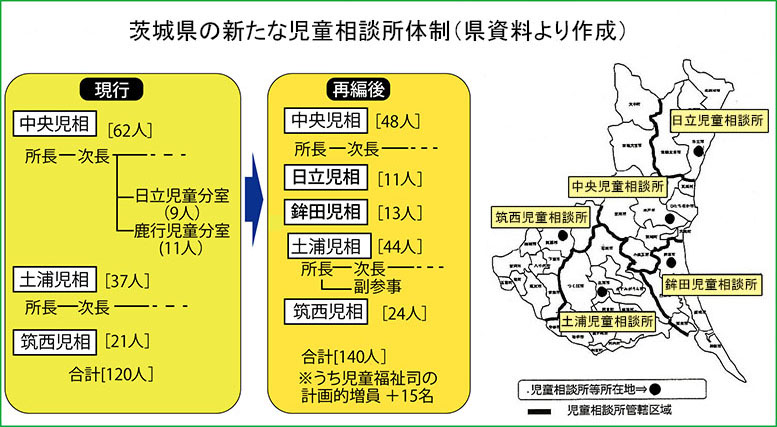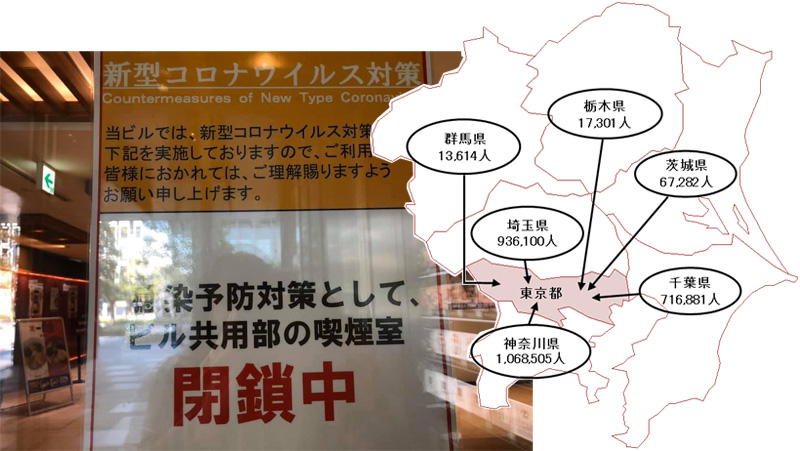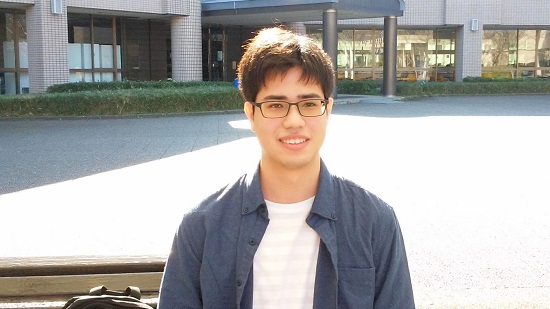【伊藤悦子】土浦市制施行80周年を記念、市内3つの文化施設が「土浦城」をテーマに陣容を整えたのに、講演会など記念行事はすべて中止となった。土浦市立博物館(土浦市中央)の第41回特別展「土浦城―時代を越えた継承の軌跡」、市民ギャラリー(同市大和町)の「戦国群像 諏訪原寛幸イラストレーション展」、上高津貝塚ふるさと歴史博物館(同市上高津)の「地下にのこる土浦城-市内近世遺跡の調査成果」。新型コロナの感染拡大に対応して、ともに5月6日まで展示のみの開催となるなか、充実の見どころを関係者に聞いた。
市立博物館 土浦城の資料を一堂に展示 博物館の学芸員西口正隆さんによると、開催のきっかけは2017年、公益財団法人日本城郭協会の「続日本100名城」に土浦城が選定されたことから。市制施行80周年記念の特別展を企画した。
「続100名城に選定されたことで訪れる人が多くなったため、今一度土浦城に注目しようという思いもあった。今回は土浦城をかなり調査し、絵図や古文書を総合的に展示したのでまとめともなる」と西口さん。
展示資料は絵図や古文書、出土品など全部で167点。土浦城の形跡がわかる航空写真の展示などもある。また今回の展示は、明治、大正、昭和と近代までの長いスパンをとっているのも特徴だ。近代までの城の展示は全国でも珍しいという。
西口さんは「時代ごとに描かれた絵図をじっくり見てもらうとおもしろい。土浦城が低地を利用して作られたことや、時代ごとに変化していく城の姿や徐々に建物が増えていく様子がわかる。城の見取り図である縄張(なわばり)の比較もおすすめ」と話す。
城の歴史を書き継いだ「土浦城記」の展示を通して、土浦城は人々が受け継いできた城だということにも注目してほしいという。
博物館を訪れた土浦市在住の小池健二郎さん(72)は、「ふだんは小田城でボランティアをしている。迫力のある展示で1日では見きれない。明日もあさっても来る」と笑顔で話していた。
◆土浦城―時代を越えた継承の軌跡 入館料は一般105円、小中高生50円(税込み)。問い合わせ電話029-824-2928
イラストに見入る来館者=土浦市民ギャラリー
市民ギャラリー 諏訪原寛幸「戦国群像」イラスト展 土浦市民ギャラリーでは市立博物館との連携企画として「戦国群像 諏訪原寛幸イラストレーション展」が開催されている。
展示について、土浦市教育委員会文化生涯学習課文化振興室長の石川功さんは「博物館の土浦城特別展に合わせて、市民ギャラリーも何か一緒にやろうということになった」と話す。
土浦城をめぐって、小田氏と佐竹氏が攻防を繰り広げた元亀元年(1570)から450年目の節目でもあり、戦国時代の人物のイラストで有名な阿見町出身の諏訪原寛幸さんに依頼したところ、イラストの展示を快諾してくれたという。
足利義政や上杉謙信、織田信長など戦国武将のイラストやグッズ数は全部で約120点と、ボリュームのある展示が見どころだ。100点を超える展示数は全国初で、諏訪原さん自身も初めてだという。
石川さんは「茨城にゆかりのある戦国武将や、メジャーな人物からマイナーな人物までと内容も盛りだくさん。1枚1枚のイラストにドラマがある」と話す。
なかでも小田氏治(うじはる)のイラストは、市立博物館所蔵の肖像画と比べて欲しいという。肖像画には猫が1匹描かれているが、イラストには2匹描かれており、実は諏訪原さんが以前飼っていた猫と今飼っている猫だという。
土浦市在住の男性(66)は、「戦国時代に興味があって来た。迫力があって一度に観るとお腹いっぱいになるので、日にちを分けて来館したい」と感想を話していた。
◆戦国群像 諏訪原寛幸イラストレーション展 入館は無料。問い合わせ電話029-846-2950
上高津貝塚ふるさと歴史博物館では、土浦の遺跡25「地下にのこる土浦城-市内近世遺跡の調査成果」を開催。過去に行った土浦城跡の発掘調査と、市内で発見された江戸時代の遺跡調査成果を紹介するテーマ展となる。◆地下にのこる土浦城-市内近世遺跡の調査成果 入館料は一般105円、小中高生50円(税込み)。問い合わせ電話029-826-7111