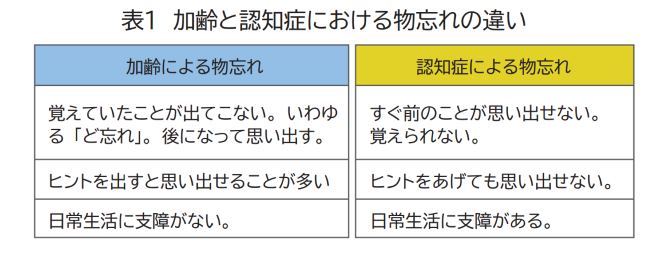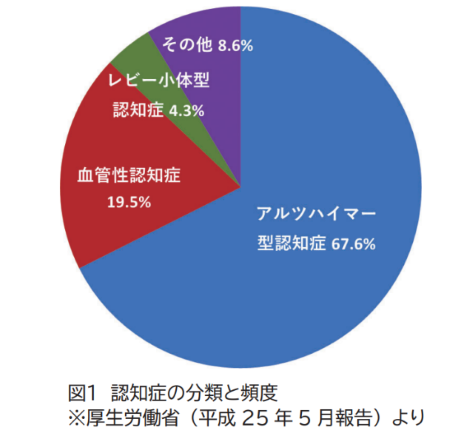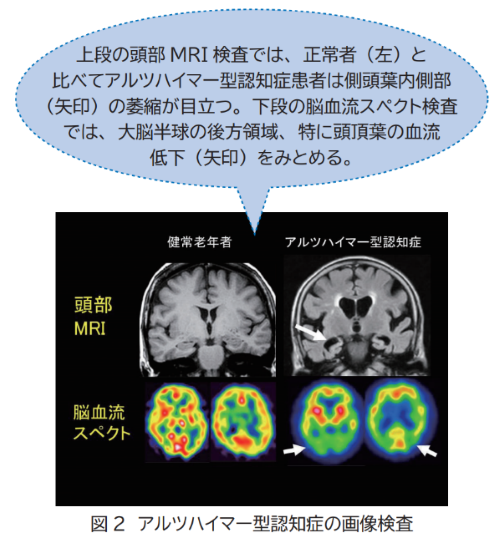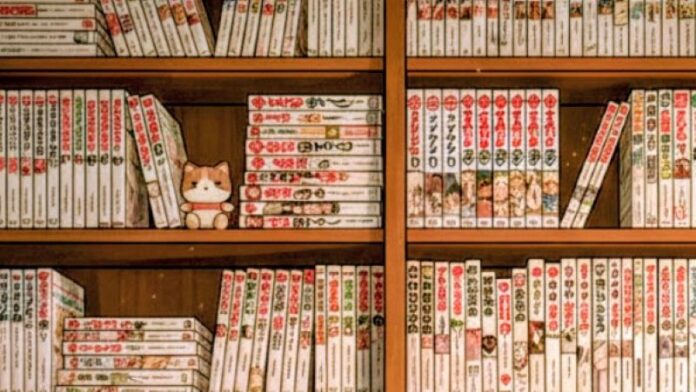2026年は午(うま)年。日本中央競馬会(JRA)美浦トレーニング・センター(トレセン)がある美浦村に、引退した競走馬のセカンドキャリアを模索し、馬耕によるワイン作りやホースセラピー、子供たちとの触れ合いなど、さまざまな取り組みに挑戦している拠点がある。
引退競走馬の可能性を広げたいと、JRAの調教師でもある大竹正博さん(56)が2023年10月に開設した。施設の設計には筑波技術大学(つくば市天久保)の梅本舞子准教授と建築系の学生らが関わり、大竹さんの夢を形にした。施設を中心に様々な活動が評価されて25年グッドデザイン賞を受賞した。

地域の人が集う
拠点は約1ヘクタールの広さで、美浦トレセンの西側にある。敷地北側に、木造平屋建ての建物が弧を描くように3棟並び、隣りに広さ約800平方メートルの砂地の馬場が設けられている。南側には約5000平方メートルのブドウ畑が広がる。拠点の名前は「ブリコラージュ」。手元にあるものを寄せ集めて新しいものを作り出すという意味のフランス語だ。
3棟の建物はそれぞれ、8畳間4部屋分(約56平方メートル)の広さで、正方形の形をしている。3棟のうち2棟は厩舎(きゅうしゃ)で、現在、競馬を引退したサラブレット4頭とポニー1頭の計5頭が暮らす。1棟は引退馬に関わる地域の人々が集うクラブハウスだ。

ブリコラージュには、元のオーナーから引退競走馬を引き取った今の所有者らが通い、馬の体をブラッシングしたり、馬場で運動させたり、乗馬を楽しんだりしている。発達障害児などを支援する放課後等デイサービス「きゃっちぼーる」を利用する子供たちが毎週1~2回来て、えさを用意したり、乗馬に挑戦したりする。地域クラブ「美浦ホースクラブ」は、土日に厩舎を掃除したり、えさを用意したり、乗馬を体験するなどしている。調教師の大竹さんのほか、近くに住む美浦トレセンの元厩務員が馬の手入れなどを手伝う。

南側のブドウ畑では10品種が栽培されている。つくば市のワイナリー「つくばヴィンヤード」の高橋学さんからブドウ栽培の指導を受けた牛久市の畠山佳誉さん(53)が、2022年から苗を植え毎年増やしてきた。引退競走馬は畑で鋤(すき)を引っ張り、横に伸びるぶどうの根を切るなど「馬耕」をする。年3回ほどまく堆肥は、つくば市若栗にある「つくば牡丹(ぼたん)園」の関浩一園長が開発した馬ふん発酵堆肥だ。競走馬の育成牧場などから大量に出される馬ふんからつくられている。

畑を耕しているのは「サモン」という名の8歳の元オス馬。2017年に北海道日高町で生まれ、19年にデビューした。12回レースを戦ったが1勝ができないまま、20年に中央競馬の登録を抹消された。地方競馬への転籍を検討したが、骨折していることが分かり引退となった。サモンの管理調教師だった大竹さんと、デビュー時からサモンをずっとひいきにしてきた美浦村の関亮子さん(52)の2人が共同所有者となって、元のオーナーから引き取った。
関さんは「サモンは人懐っこくて、ずっと応援していた」と話す。大竹さんは、サモンに馬耕をさせる際、周囲から「競走馬に馬耕させるのは聞いたことがない」と驚かれたと振り返る。「馬耕をするようになって、サモンはむしろたくましくなった」と大竹さんは目を細める。

サモンが耕した畑のブドウで2025年春、初めて赤ワインを醸造し362本が出来上がった。「綴(つづり)」と名付け、美浦村のふるさと納税返礼品にもなった。ブドウ畑を担当する畠山さんは「馬が畑を耕す『馬耕』のほかに、これからは収穫したブドウや堆肥を馬に運んでもらう『馬搬』にも取り組み、引退競走馬のセカンドキャリアを応援したい」と話す。畑にブドウの苗をさらに植えて、ワインの種類も3種類くらいに増やす計画だ。

年5000頭近くが引退
中央競馬では毎年、5000頭近くの競走馬が引退するという。馬の寿命は長いと30年ほど。引退後は地方競馬に転籍したり、乗馬クラブが引き取ったり、競馬ファンが譲り受けるケースなどがある。しかし活躍の場が用意されない引退馬も少なくないと大竹さんはいう。
大竹さんは東京都出身。父親は騎手で、子供の頃から馬に親しんで育った。麻布大学獣医学部を卒業後、北海道で働いた後、JRAの調教師になり、2009年、美浦トレセンに厩舎を開いた。18年に有馬記念を制したなどの実績がある。
調教師の仕事の傍ら、大竹さんは個人で、引退競走馬支援団体を応援するなどの活動を続けてきた。「かつて、母屋と厩(うまや)が一体になった曲がり屋で人と馬が隣り合って暮らしてきたように、人と馬が一緒に過ごせる現代版のコンパクトな曲がり屋をつくりたい」と思うようになり、2020年ごろから、馬がストレスなく過ごせる、馬が主役で人が集まる場所づくりの構想を温めてきた。
実現に向け、筑波技術大の梅本准教授らと構想を練り上げた。美浦トレセンそばの畑を大竹さんが一部購入したり、借りるなどしてブドウ畑をつくり、厩舎とクラブハウス3棟を建て、ブリコラージュが完成した。3棟の建物の骨組みには、岩手県の森林で切り出された木材を馬が運んだ「馬搬出材」を用いている。弧を描くように配置された3棟は、人と馬が常に気配を感じられるように設計されている。施設には視覚を遮る垣根などは設けず、通り掛かった人だれもが、馬がいる風景を眺められるようにした。

引退馬を引き取ると通常、管理費用として1頭当たり月15万円、年間で200万円程度かかる。大竹さんは、引退馬を引き取った所有者や、引退馬に関わりたいと希望する地域住民が自ら、馬のえさやり、手入れ、運動などを手伝うことでコストダウンできる仕組みをつくり、だれもが支援の担い手となれるようにした。厩舎の清掃やえさやりをする地域クラブ「美浦ホースクラブ」代表の阿部彩希さん(37)は「一人一人、ブリコラージュに集う目的は違うが、馬を通じて、地域のたくさんの人が自分の目標に向かって活動し、協力し合う場所になっている」と話す。
人と馬が一緒に過ごす3棟の建物で構成される現代版の曲がり屋を、だれもが引退競走馬に関わることができる支援拠点として、地域にさらに増やしていくのが大竹さんの次の目標だ。大竹さんは「まずここに来て馬を知ってもらって、興味をもってくれたら」と話す。(鈴木宏子)