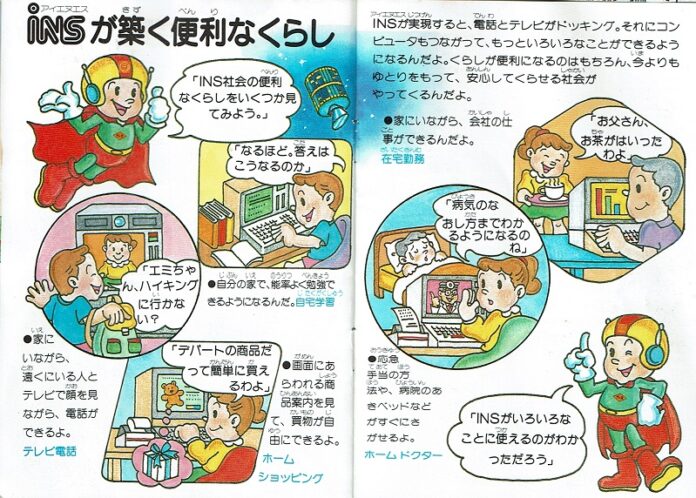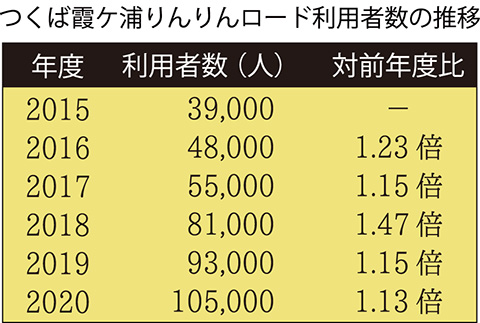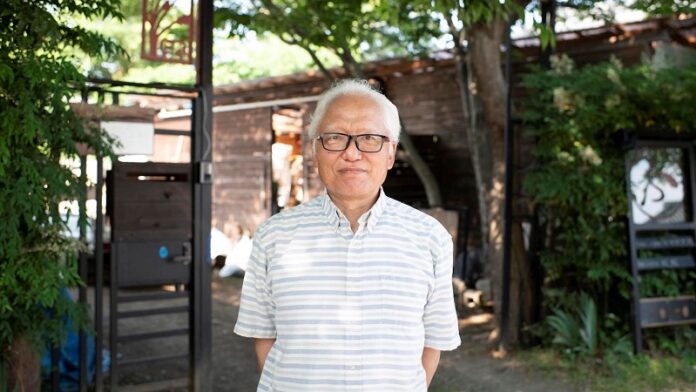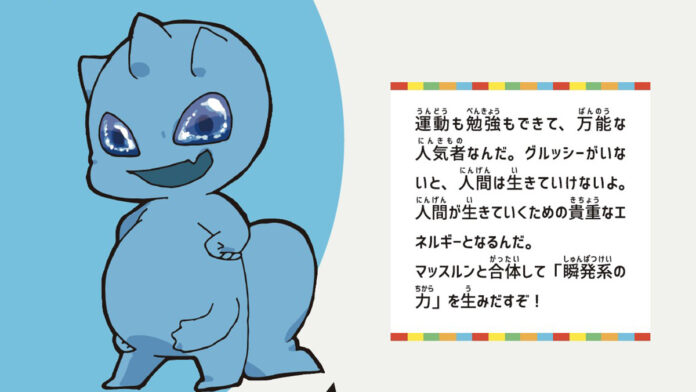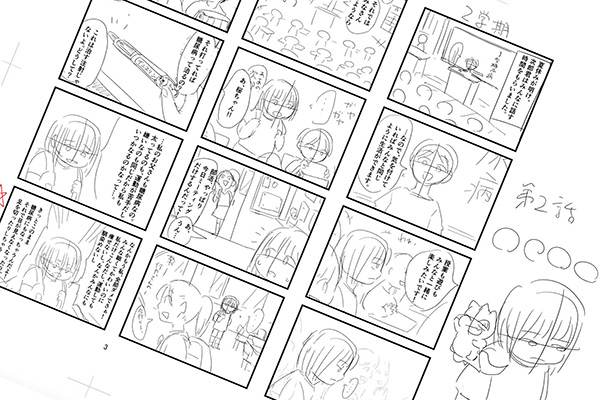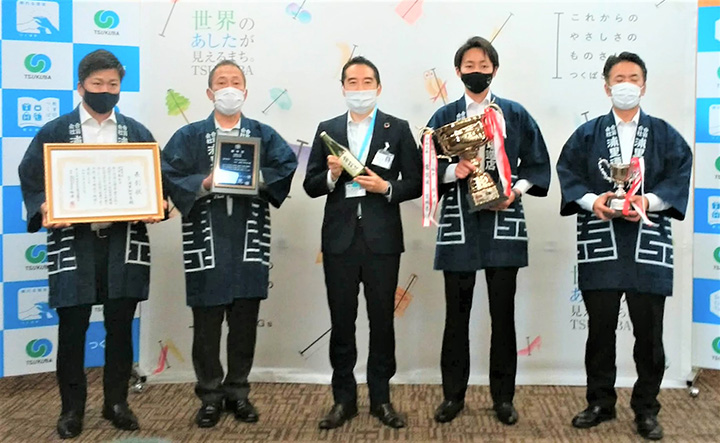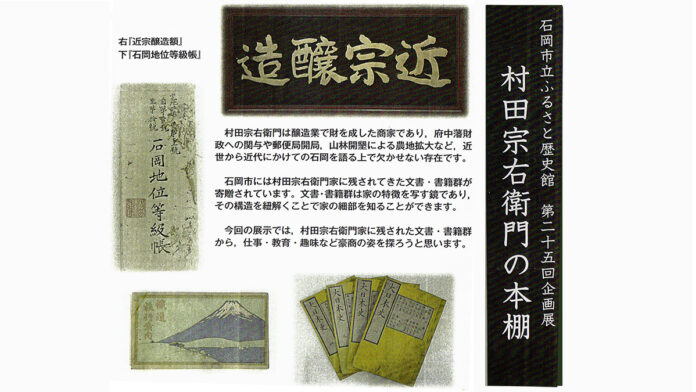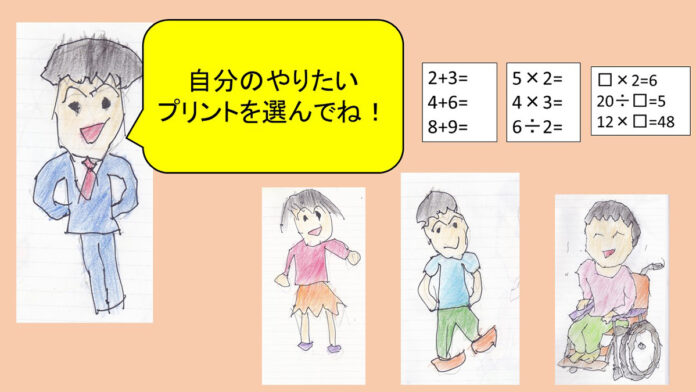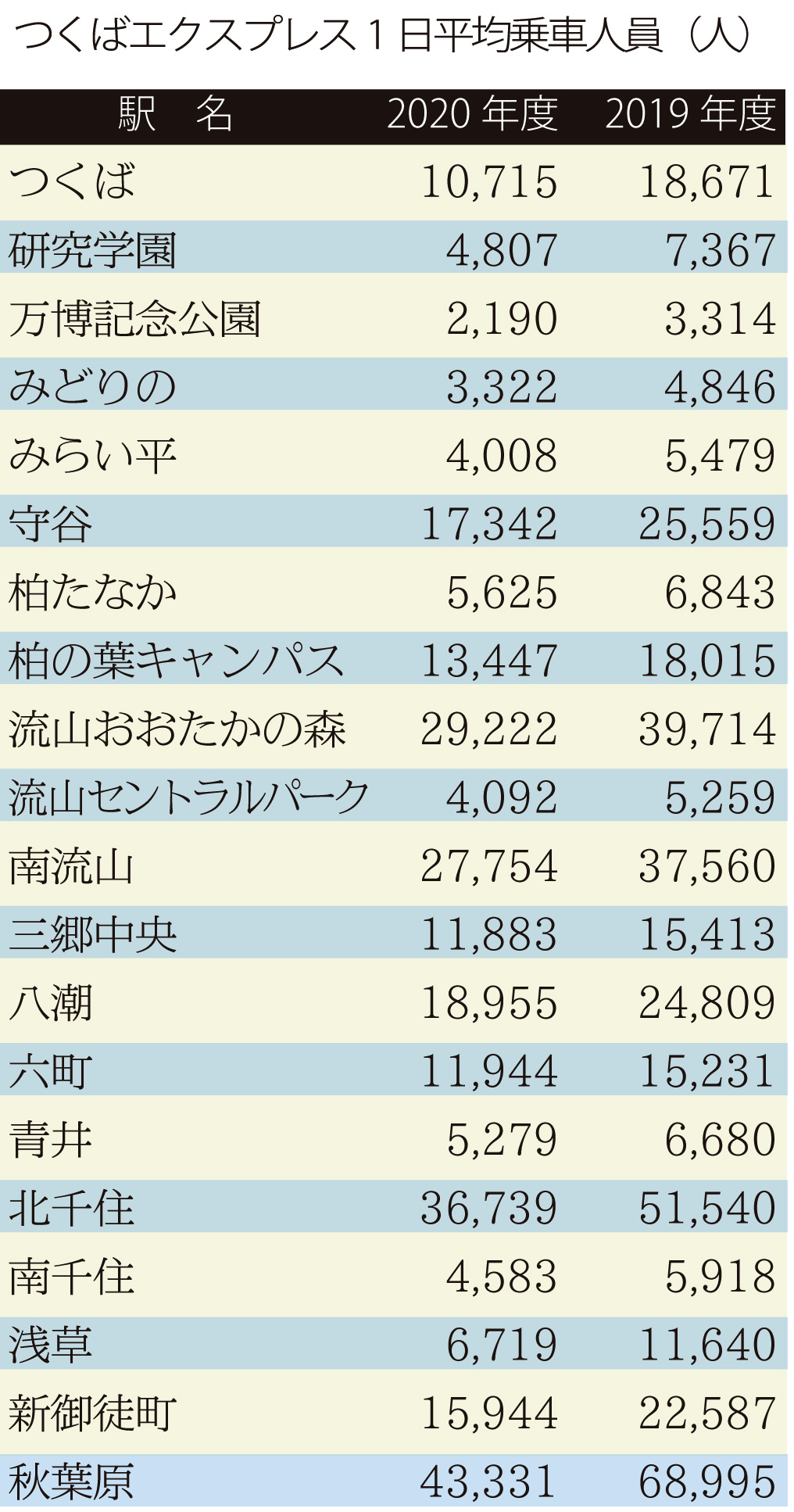コロナ禍で敬老福祉大会を中止する代わりに、つくば市が70歳以上の高齢者約3万7200人に贈る予定の記念品「箸とスプーンセット」をめぐって、16日、市議会から異論が相次いだ。
同市では財政負担の増加が見込まれるとして、今年3月、75歳以上に3000円を給付する一般敬老祝金を廃止したばかり。祝金がもらえなくなる高齢者が大半となる中、片や高齢者のほとんどの家庭にすでにある箸とスプーンを贈って喜ばれるのか、という意見だ。
さらに物品調達を、障害者就労施設1カ所に発注する予定であることが分かり、発注の仕方をめぐっても、障害者施設の受注機会を増やすことを目的とする障害者優先調達推進法の主旨に添わないという疑問も出された。
敬老福祉大会は昨年に続き2年連続、中止となる。昨年は中止に代わって、コロナ禍の市民生活応援商品券5000円分が70歳以上の高齢者や18歳以下の子供などに配られた。
一方、敬老祝金は2020年度まで、一般敬老祝金として75歳以上に3000円の商品券が給付され、特別敬老祝金として88歳に1万円の商品券、100歳に3万円の現金、101歳以上に2万円の商品券が給付されていた。給付額は20年度の場合、総額で約7500万円だった。21度からは3000円の一般祝金を廃止して支給対象者を限定する。77歳に3000円、88歳に1万円、100歳に3万円、101歳以上に2万円の現金が給付される。
「市民の反応が怖い」
今年9月の敬老福祉大会中止に代わって送る記念品については、今月3日開会の6月議会に提案された一般会計補正予算案の中で、敬老祝品贈呈委託料(記念品と包装代など)約6300万円と、郵送代約1300万円の計約7600万円が計上され、記念品の中味が、箸とスプーンセットであることが明らかにされた。
箸はポリエステル塗装を施した木製、スプーンはアクリル樹脂製の定価1000円のセットで、男性に黒、女性に赤を贈る。
物品調達は、入札を実施せず、障害者就労施設に委託する。結城市内に本部がある、つくば市内の施設1カ所に発注する予定だという。
これに対し16日開かれた市議会文教福祉委員会(木村清隆委員長)で異論が相次いだ。
「そもそもなぜ、箸とスプーンなのか。喜んでいただけるのか疑問をぬぐえない。去年はコロナ禍の生活応援として5000円の商品券を配布した。今年はお箸とスプーンがきた、となったら市民の反応が怖い」(小森谷さやか市議)。
「物品調達はかなり課題が大きい。せっかく大きな仕事ができた。(多くの施設が仕事を受託できるよう)物を市が買って、作業を委託していく方法もある」(山本美和市議)。
「なぜ箸とスプーンなのか。調達の仕方にも問題がある」(橋本佳子市議)などだ。
これに対し市高齢福祉課は、祝い品として何がふさわしいか、市内部で5種類くらい検討し、長く、毎日使えるものとして、はしとスプーンセットに決めたと説明する。「マスクや消毒液、(市認定物産品の)つくばコレクションの銘菓なども検討対象になったが、マスクは祝い品としてふさわしいか、菓子は保存期間や発送が難しいなどの意見が出た」という。
箸とスプーンの色については、高齢者と同居している市職員37人にアンケートをとり、7種類の中から黒と赤を選定した。
商品の調達と発送方法については、障害者就労施設が、市指定の箸とスプーン3万7200セットをあらかじめ自前の資金で購入し、のしを貼って封筒に入れるなどの作業をする。同課は「市内の3カ所ぐらいを当たったが、2カ所から、調達する資金がない、置く場所がないなどの理由で断られた」と説明する。
一方、16日の市議会文教福祉委で意見が出たことから「(包装などの)作業だけ委託先が分けられないか検討したい」とし、委託先を増やすことを検討するという。記念品を市が購入して、包装作業を数多くの施設に委託する方法については「市が物品を購入する場合、入札を実施しなければならず、9月の敬老の日前後に発送するには間に合わない」としている。
この問題は、22日の予算決算委員会で再度、審議される。(鈴木宏子)