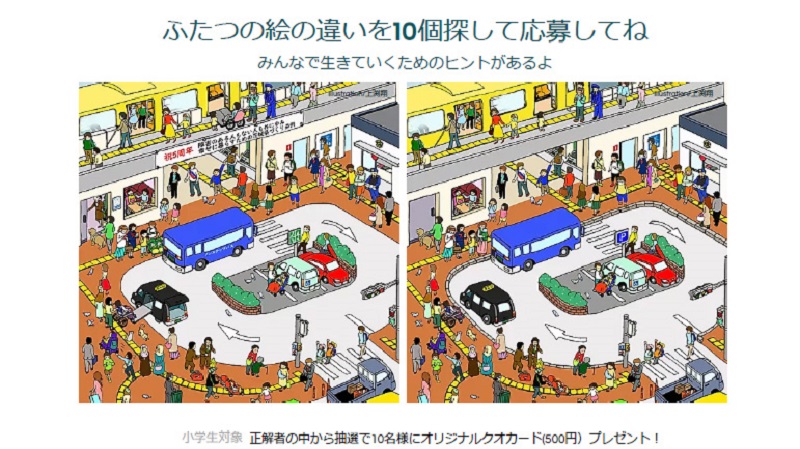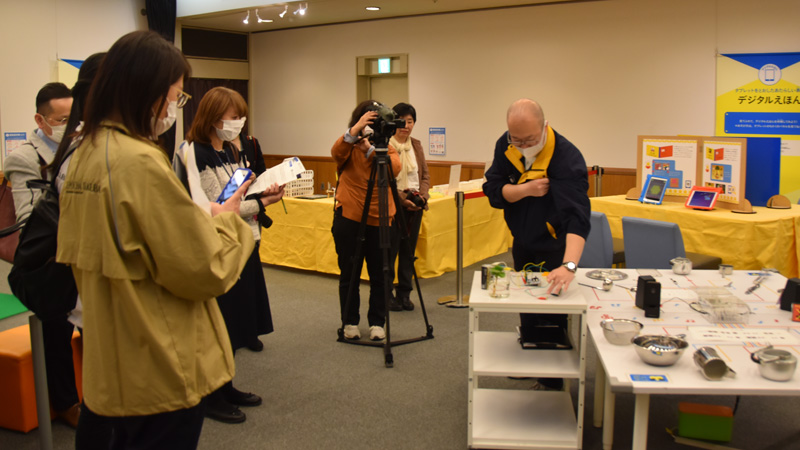つくば市は4月1日付け市職員の人事異動を内示した。異動総数は253人(全職員数の19.4%)で、業務の継続や専門性を重視し必要最低限の規模となる。
女性管理職の割合(幼稚園長、保育所長を除く)は16.4%で前年度より2.3%増える。国や県との人事交流は、引き続き文科省から政策イノベーション部長、国交省から都市計画部次長を配置し、国と県に7人の実務研修員を派遣する。
任期付職員は、昨年9月から企画経営課持続可能都市戦略室に配置している民間出身者を、ふるさと納税やガバメントクラウドファンディングなどの手法を活用して資金調達を行うため引き続き配置する。制度改正により、これまで嘱託として配置していた市立幼稚園の園長6人を任期付職員とする。
定年後の再任用は原則、退職時の2級下の職での任用とする。松本玲子市長公室長は部長級として同市で初めて2年連続の再任用となる。
定年退職者は41人、自己都合などの普通退職者は34人、新規採用者は64人で、4月1日付けの職員数は前年度より4人増えて1973人になる。再任用は同比5人減の123人。
スポーツ未来室など設置
組織改編は、科学技術の社会実装と起業家育成プログラムなど関連政策の連携を密にするため、経済部産業振興課のスタートアップ推進室と産業振興センターを政策イノベーション部科学技術振興課に移す。
まちづくりにおけるスポーツの価値を分野を超えて検討するため、プロジェクトチームとして、市民部にスポーツ未来室を設置する。障害児の相談に重点的に取り組むため障害福祉課に障害者地域支援室を設置し8人の職員を配置する。
農作物への鳥獣被害対策を強化するため農業政策課に鳥獣対策・森林保全室を設置し、3人を配置する。都市計画道路の早期完成を実現するため道路計画課に都市計画道路整備推進室を設置し、4人を配置する。
ほかに、教育局教育指導課を学び推進課に名称変更する。下水道事業の地方公営企業法全部適用に伴って水道と下水道の共通する総務部門を同一課などとする。消防本部は警防課を消防救急課に名称変更し、救急課を新設して5人を配置する。
4月1日付け人事異動は次の通り。カッコ内は現職。敬称略
【部長級】
▽市長公室長・再任用(同)松本玲子
▽総務部長(経済部長)篠塚英司
▽保健福祉部長(同部次長)小室伸一
▽経済部長(農業委員会事務局長)野澤政章
▽建設部長(同部次長)小又利幸
▽生活環境部長(同部次長)谷内俊昭
【次長級】
▽市長公室次長兼秘書課長兼広報監(総務部人事課長)塚本浩行
▽総務部次長(教育局次長)大久保克己
▽総務部次長兼総務課長(総務課長)中泉繁美
▽総務部総務政策監・再任用(総務部長)藤後誠
▽政策イノベーション部次長(市長公室次長兼秘書課長兼広報監)杉山晃
▽財務部次長・納税課、市民税課、資産税課担当(財務部次長)中島弘志
▽財務部次長兼財政課長(財政課長)斎藤健一
▽市民部次長(国体推進課長)横田修一
▽市民部地区担当監兼茎崎相談センター所長(生活環境部次長)西村誠
▽保健福祉部次長(同部次長兼健康増進課長)吉原衛
▽保健福祉部次長(こども部こども政策課長)安曽貞夫
▽こども部次長(同部次長兼幼児保育課長)松本茂
▽経済部次長(政策イノベーション部次長)片野博司
▽都市計画部次長・沿線開発整備室、市街地振興課、総合交通政策課担当(同部次長・総合交通政策課担当)中澤正登
▽都市計画部次長兼市街地振興監兼政策イノベーション部スマートシティ戦略室ディレクター(都市計画部次長兼同ディレクター)大塚賢太
▽建設部次長(道路計画課長)富田剛
▽建設部建設政策監・再任用(同政策監・再任用)栗原正治
▽生活環境部次長・上下水道総務課、水道業務課、水道工務課担当(同部次長・水道総務課、水道業務課、水道工務課担当)岡野康夫
▽生活環境部次長(下水道整備課長)野原浩司
▽生活環境部次長(環境政策課長)嶋崎道徳
▽教育局次長(教育総務課長)貝塚厚
▽議会事務局次長(都市計画部市街地振興課長)中島一美
▽選挙管理委員会事務局長(同副局長)窪庭隆
▽農業委員会事務局長(市民部次長)山田憲男
▽消防本部中央消防署長(北消防署長)沼尻博
▽消防本部北消防署長(消防総務課長)山田勝
【課長級】
▽総務部人事課長(法務課長補佐)沼尻浩幸
▽財務部管財課長(資産税課長補佐)海野原雅也
▽財務部市民税課長(同課長補佐)髙野克則
▽市民部地区相談課長(同副地区担当監・谷田部相談センター駐在)日下由美子
▽市民部地区相談課地区調整監・再任用(生活環境部長)風見昌幸
▽市民部副地区担当監・大穂相談センター駐在(市民部国体推進課国体推進監)矢島正弘
▽市民部副地区担当監兼豊里相談センター所長(市民部副地区担当監・桜相談センター駐在)小神野真
▽市民部副地区担当監・豊里相談センター駐在・再任用(建設部長)上野義光
▽市民部副地区担当監兼谷田部相談センター所長(消防本部地域消防課長)秋葉芳行
▽市民部副地区担当監・谷田部相談センター駐在・再任用(同谷田部相談センター所長・再任用)新井隆男
▽市民部副地区担当監兼桜相談センター所長(国体推進課国体推進監)関口正昭
▽市民部副地区担当監・桜相談センター駐在(生活環境部サステナスクエア管理課長)星野和也
▽市民部副地区担当監・筑波相談センター駐在・再任用(同・再任用)長島芳行
▽保健福祉部医療年金課長(社会福祉課長補佐)日下永一
▽保健福祉部健康増進課長(介護保険課長補佐)岡野智
▽こども部こども政策課長(教育局文化財課長兼桜歴史民俗資料館長)美野本玲子
▽こども部幼児保育課長(市民部文化芸術課長補佐)吉沼浩美
▽経済部観光推進課長(同課長補佐)兼平勝司
▽都市計画部市街地振興課長(同課長補佐)大久保正巳
▽都市計画部市街地振興課都市政策調整監・つくば都市交通センター派遣研修・再任用(同・再任用)長卓良
▽建設部道路計画課長(総務部契約検査課長補佐)山田正美
▽建設部防犯交通安全課長(経済部観光推進課長)一瀬剛
▽生活環境部環境政策課長(教育局健康教育課長)池畑浩
▽生活環境部サステナスクエア管理課長兼サステナスクエア南分所長(環境衛生課長補佐)窪庭茂
▽生活環境部上下水道総務課長(水道総務課長)小吹正通
▽生活環境部水道業務課長(財務部市民税課長)本山雅之
▽生活環境部水道工務課長(水道業務課長)坂入善晴
▽生活環境部下水道課長(下水道管理課長補佐)渡辺高則
▽教育局教育総務課長(同課長補佐兼教育局企画監)笹本昌伸
▽教育局健康教育課長(こども部こども政策課長補佐)柳町優子
▽教育局筑波学校給食センター所長(建設部防犯交通安全課長)杉山一彦
▽教育局つくばすこやか給食センター豊里所長(財務部管財課長)新関清美
▽教育局つくばほがらか給食センター谷田部所長(大穂学校給食センター所長)山口康弘
▽教育局文化財課長兼桜歴史民俗資料館長(文化財課長補佐)石橋充
▽議会事務局議会総務課長(同課長補佐)町井浩美
▽選挙管理委員会事務局副局長(議会事務部局議会総務課長)渡辺寛明
▽農業委員会事務局農業行政課長(建設部公共施設整備課長補佐)佐藤宏明
▽消防本部地域消防課長(地域消防課長補佐)木村宏
▽消防本部救急課長(警防課長)古山正則
▽消防本部消防指令課長(中央消防署豊里分署長)山田和美
▽消防本部消防救助課長(警防課長補佐兼警防係長)木村勝平
▽消防本部消防総務課長(消防指令課長補佐)小島幸司
▽中央消防署副署長(中央消防署桜分署長)野口勝
▽中央消防署桜分署長(消防総務課長補佐兼消防本部企画監)鈴木浩
退職者は以下の通り。3月31日付。
【部長級】
▽総務部長・藤後誠
▽建設部長・上野義光
▽生活環境部長・風見昌幸
【次長級】
▽市民部地区担当監・瀧田剛己
▽市民部地区担当監・松崎若美
▽市民部地区担当監兼豊里相談センター所長・大塚喜則
▽市民部地区担当監兼桜相談センター所長・松浦裕之
▽市民部地区担当監兼茎崎相談センター所長・秋葉義美
▽保健福祉部社会福祉推進監・稲葉光正
▽経済部次長・永田悦男
▽議会事務局次長・中泉治
▽選挙管理委員会事務局長・石田慎二
▽消防本部中央消防署長・高野和之
【課長級】
▽保健福祉部医療年金課長・岡田高明
▽経済部農業政策課参事つくば市農業再生協議会駐在・稲川正明
▽生活環境部水道工務課長・小神野哲夫
▽生活環境部下水道管理課長・滝本勝弘
▽教育局桜学校給食センター所長・村上克己
▽教育局筑波学校給食センター所長・安田勝則
▽教育局つくばすこやか給食センター豊里所長・鈴木洋一
▽農業委員会事務局農業行政課長・中川正
▽消防本部消防指令課長・竹内信之
▽中央消防署副署長・堀江道夫



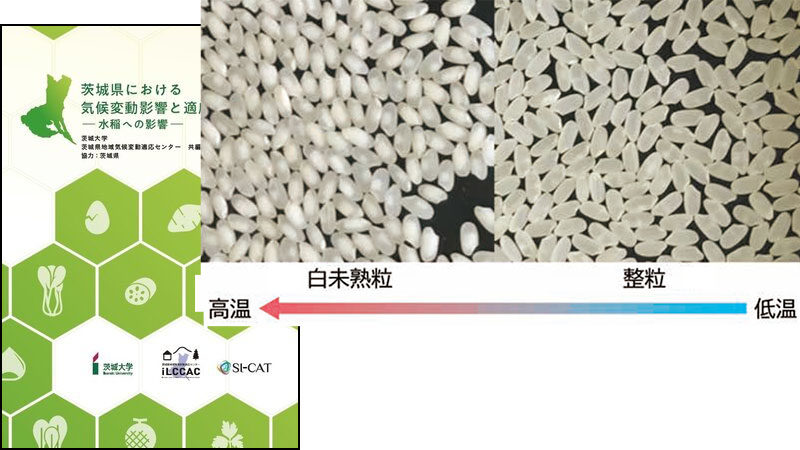








![9183882905242ef7bac5f723dc66cc23[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/02/9183882905242ef7bac5f723dc66cc231.jpg)