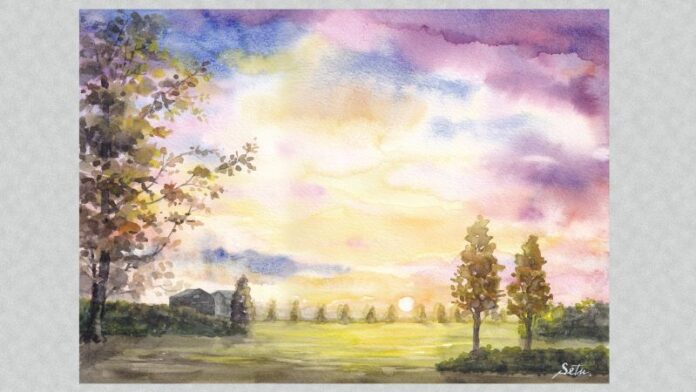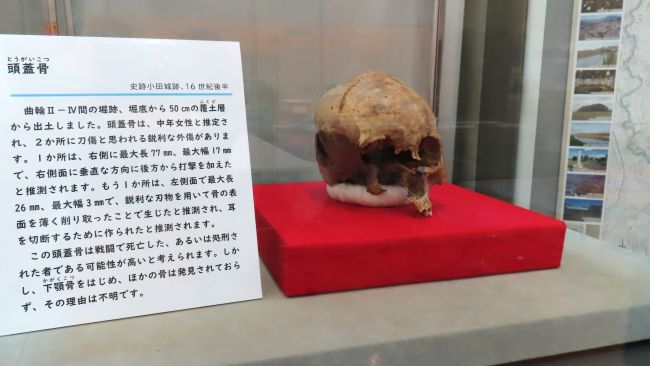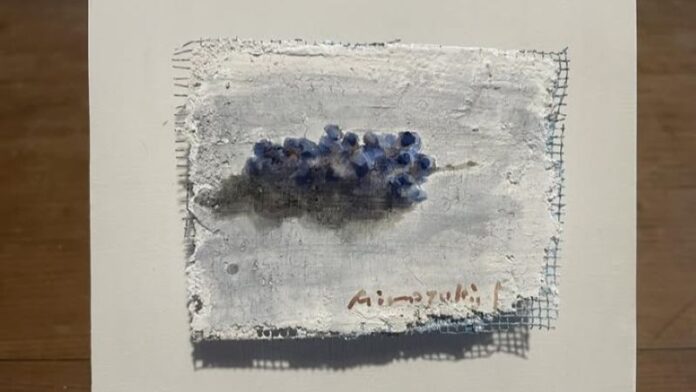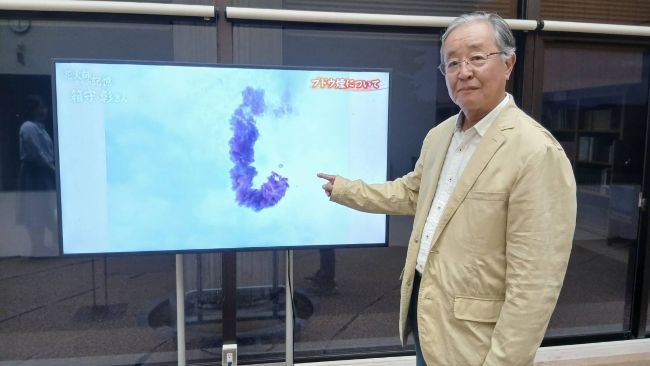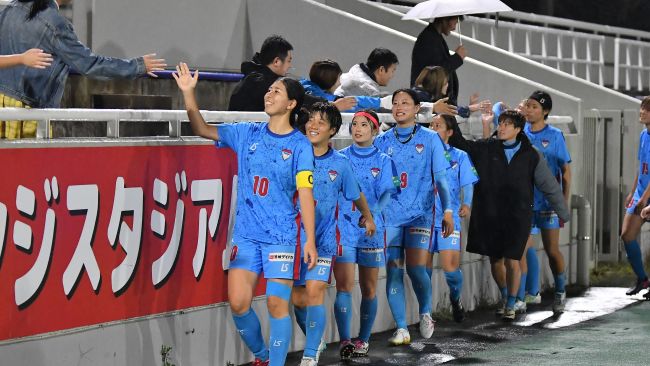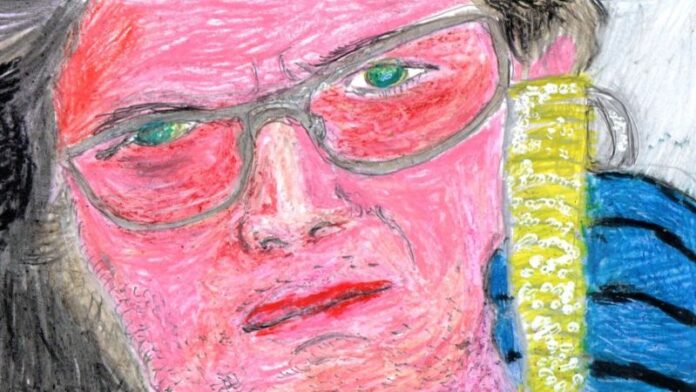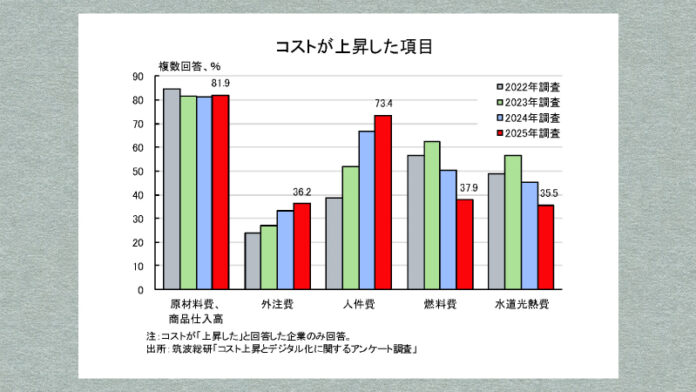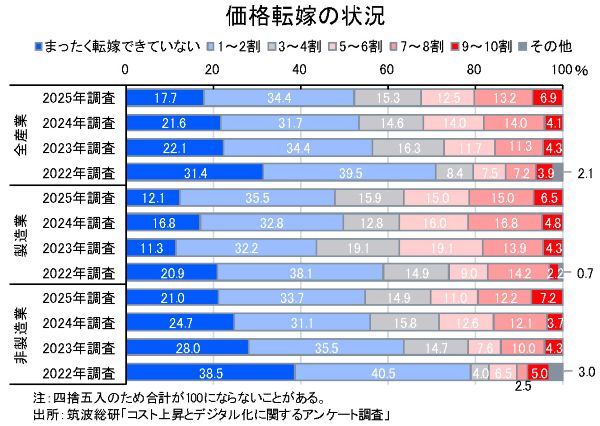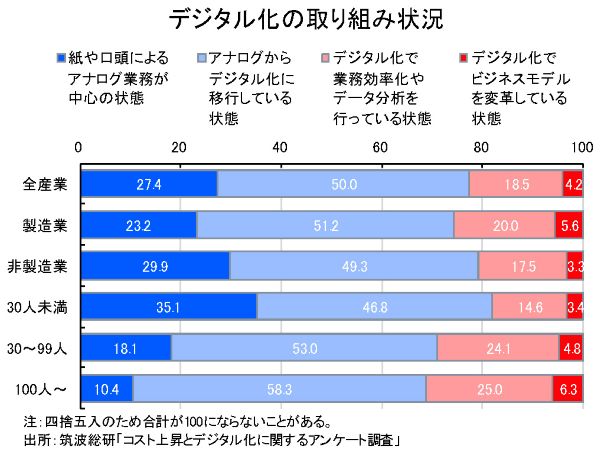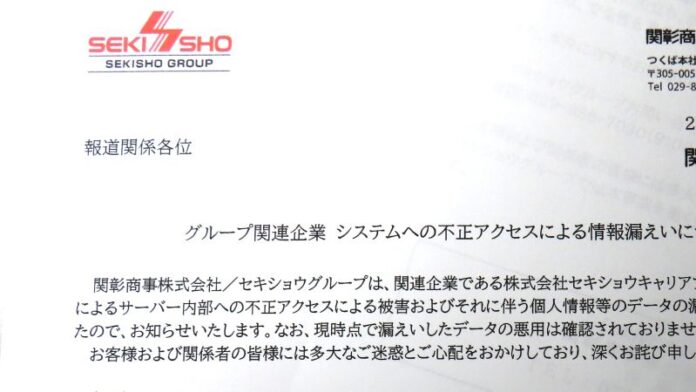【コラム・坂本栄】つくば市の総合運動公園用地は3年前に倉庫業者に売却され、それに反対する有志市民の住民訴訟も敗訴したことで、「もう終わった問題」と思っている方が多いと思います。ところが、酒井泉市議が秋の議会で売却の問題点を追求、今後は「用地買い戻し実現に向けて対市民キャンペーンを展開する」そうです。私もこの欄で売却の問題点をいくつか指摘してきたこともあり、その行方を注目しています。
幻に終わった県南の中核施設
住民投票で実現しなかった市原前市長時代の総合運動公園計画について、私は以下のように考えています。
▼総事業費が300億円に上る財政負担に市民は不安を覚えたようだが、15年の長期計画でやれば、年20億の負担で済んだ。具体的には、高いレベルの3施設(陸上競技場、総合体育館、サッカー場)を各5年計画で順番に整備すればよかった。県南の中核運動施設と位置付け、県や周辺市町村にも経費を分担してもらい、国の補助も受ける計画にすれば、年20億の市負担を限りなく減らすことができた。
▼前市長時代にUR都市機構から取得した用地は45ヘクタールと広く、研究機関が連なる幹線道路沿いの少し奥に位置し、利用者には極めて使い勝手がよい。したがって、つくば市民だけでなく他県民も広く利用できる場所として活用すべきであり、各種施設から成る総合運動公園は県南エリアに望まれるプロジェクトであった。
全用地売却は政治的な選択
ところが、この計画は五十嵐現市長が旗を振った反対運動と住民投票によってご破算になりました。その問題点について、私は以下のように理解しています。結論を先に言うと、運動公園問題は現市長の未解決の厄介事ということです。
▼総事業費300億という数字が反対運動で強調された結果、市民の関心は市の財政負担に向けられ、県南に整備される総合運動公園のメリットに思いが至らなかった。また、住民投票の問いが全計画に賛成か反対かの2択式でなく、「(計画修正も含む)どちらでもない」もある3択式であったならば、この択に〇を付ける市民が一定シェアを占め、当初計画の見直し(整備計画の長期化、3施設の設計変更、1~2施設への縮小など)が可能だった。
▼現市長は、市民運動家として運動公園反対運動を主導し、計画が頓挫した用地をURに返還することを最初の市長選の目玉公約にしたため(結果は失敗)、当初計画の修正という選択肢の採用は政治的に難しくなり、全用地の売却に走らざるを得なくなった。つまり、返還失敗という失政の痕跡を消し去ることが市長就任後の政策テーマになった。
▼用地処分を焦るあまり、反対運動と市長選挙の際に指摘した前市長の行政スタイル(市民や議会の声を軽視して執行部が独走したと批判)を自ら踏襲し、用地売却の議案を議会に提出せず、市民の考えを無作為に聞くアンケート調査(住民投票のミニ版)もせず、倉庫業者による住民説明会の非開催(チラシ配布のみ)を容認した。
開示情報の多くは黒塗り
反対運動で市の財政負担(300億!)を強調したこと、市民の声をきちんと聞き取る調査を実施しなかったこと、議会による議決手続きを無視したこと、周辺住民への説明会を業者に回避させたこと―などを見てくると、現市長の市政運営には疑問符が付きます。
酒井市議が指摘している問題点は多岐にわたりますが、市が用地売却で採用したプロポーザル方式(取得価格と利用方法を購入希望業者に提出させ、それらを点数化し、総合点が高い業者に売却)がきちんと行われたかどうか、特に問題にしています。市が用地取得の条件に掲げた「防災倉庫」の提案内容や審査書類を開示するよう市に要求したところ、開示拒否あるいは黒塗りだったそうです。
こういった市の対応を受け、酒井市議は業者選定に当たり何かあったのではないかと疑っています。近畿財務局管内にあった国有地の不正売却でも財務省が文書開示を迫られ、黒塗りの書類を出して逃げ回ったという事件もありました。(経済ジャーナリスト)
<参考>運動公園問題を扱った最新記事と過去コラム(青字部を押してください)
・「防災拠点27年末完成へ…」(9月30日掲載)
・186「…市民軽視の連鎖」(24年7月1日掲載)
・152「住民訴訟の判決は…」(23年3月6日掲載)
・145「…おかしな行政手順」(22年11月21日掲載)
・137「リコール運動の行方…」(22年7月18日掲載)
・135「…つくば市政の不思議」(22年6月20日掲載)
・129「…なぜか逃げ回る市長」(22年3月21日掲載)
・125「…都合がよい理屈付け」(22年1月31日掲載)