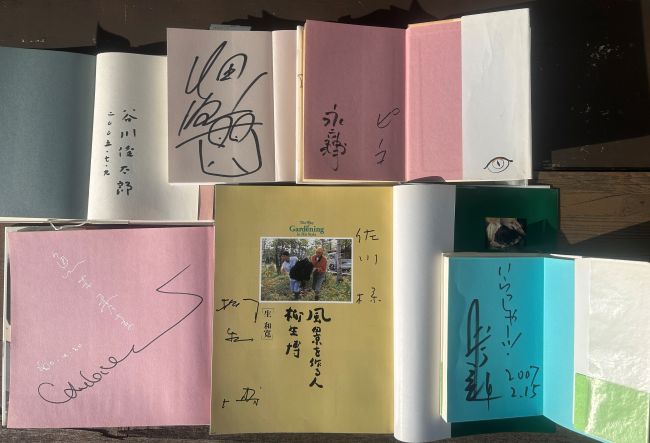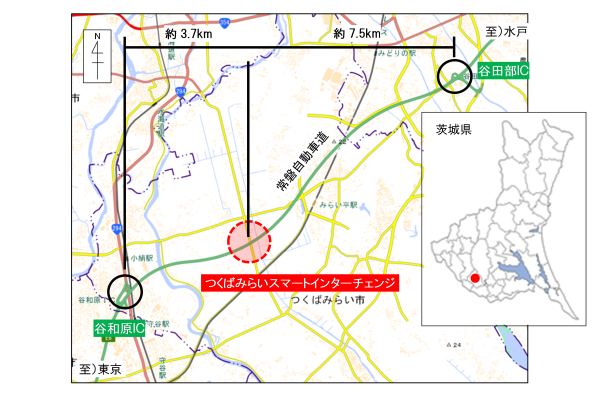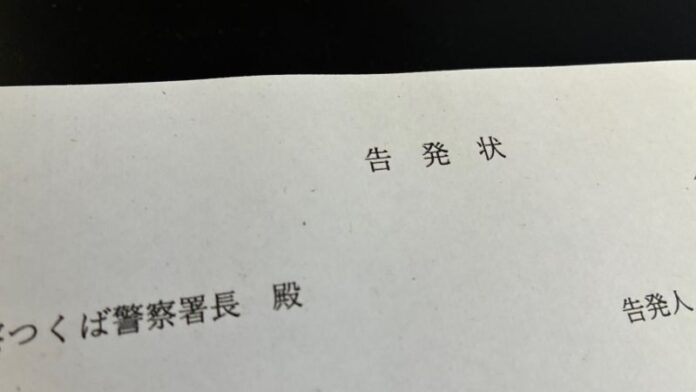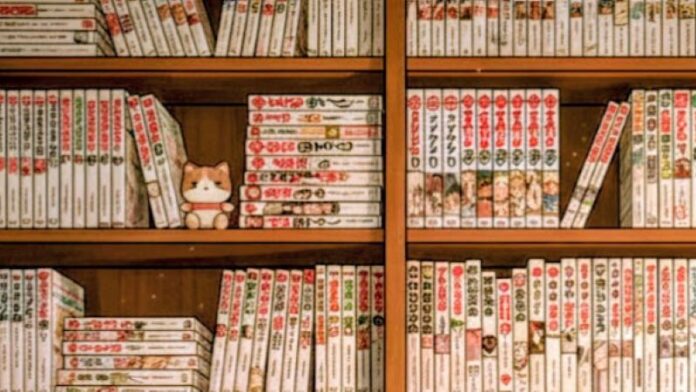【コラム・山口京子】11月中旬、利根町役場のホールで「平和のつどい利根」講演会が開かれました。講師はイスラエル生まれの元空軍兵士で、現在は埼玉県で家具作家をしているダニー・ネフセタイさん。テーマは「武器を持たない勇気と知恵」でした。
イスラエルには徴兵制度があり、高校卒業後、男性は3年間、女性は2年間、兵役に就くそうです。「軍隊がなければ周りの国から攻撃され、生きていけないと思い込まされ、軍隊はすばらしいという価値観を自然に身に付ける。自分もそのように思っていたが、退役後、アジアを旅して日本で暮らすようになり、考えが変わっていった」とのことでした。
そして、「過去のゆがみに縛られるより、今からどうしていくのか、共に生きるのか、共に死ぬのか。共に生きるには、武器を持たない勇気と知恵が求められる」と。
ダニーさんは、戦闘機に乗った若き自分の写真をパワーポイントで映しながら、「これを見てどう感じますか? カッコイイと思う人いますか?」と尋ねます。そして、「戦闘機はある目的のためにだけ優れている。それは物を破壊し、人を殺すこと。その目的って、カッコイイことなのか?」。
「テロは武力では止められない。武力を行使すれば、さらなる憎しみが生まれる。武力によって生まれるのはさらなる武力。憎しみによって生まれるのは憎しみでしかない。戦争は最大の人権侵害であり、環境破壊でもある」
武器が商品に、戦争が商売に
日本の防衛費は年間8兆8000億円。この額を、365日、1日、1時間、1秒に換算すると、1日241億円、1時間10億円。とんでもない金額です。その出所は国民の税金。軍事費に使われるほど生活にしわ寄せが来ます。
ダニーさんは14年前、「原発とめよう秩父人」を立ち上げ、反戦や反原発を訴える講演を各地で行っているそうです。「‘敵’概念はヒトのDNAにはない後天的産物であり、話し合いで解決できないという思い込みは、捨てないといけない。‘敵’とは国が設定するものであり、あおりや脅かしに振り回されないで、お互い、よく見て、よく聞き、よく話すことが必要だ」
東京新聞に「世界の軍需企業24年販売額最高」という記事(12月2日付)が出ました。ストックホルム国際平和研究所によると、上位100社の軍需関連販売額は前年比5.9%増え、6790億ドル(約106兆円)と、とんでもない金額です。武器が商品になる、戦争が商売になる―おかしくありませんか? (消費生活アドバイザー)