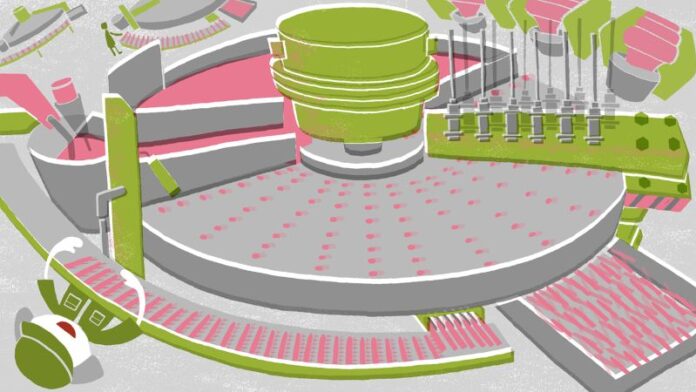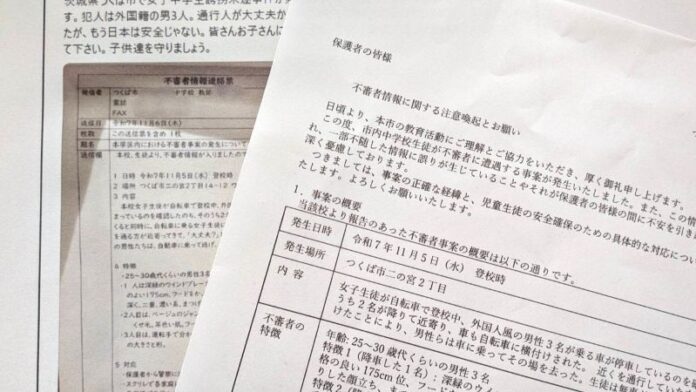【投稿・鳥居徹夫】今年9月の定例市議会で、つくば市保健センター条例から茎崎保健センターの記載が削除され、つくば市地域交流センター条例に「茎崎交流センター別館」を新たに加える議案が同時提出され、審議もなく全会一致で決定となった。
「広報つくば」12月号によると、17日に「茎崎保健センターが新しく生まれ変わり、茎崎交流センター別館としてオープンします」と広報されている。
場所は「茎崎保健センター」があった建物だが、条例に定められていたはずの保健センターの機能は15年前からなく、条例にあった「茎崎保健センター」の字句も、建物の名称も、ついに消滅した。
既存施設の代替を理由に、15年続いた条例違反の異常事態が解消され、つくば市長や市幹部にとっては「のどに突っかかった小骨」が取れてほっとしていることであろう。
市長は条例違反を知っていた
2023年10月14日のタウンミーティングで私は、「つくば市保健センター条例が守られていない状況というのは、やっぱり改善してほしい」と発言した。五十嵐立青市長は「ご指摘の部分はおっしゃる通りの状況で…」と条例違反を自白した。
しかし市長は「建物は存続するが、機能は廃止する」と強弁。条例違反を追認したばかりか、逆に(条例違反の)現実に条例を合わせ、保健センター条例を改悪すると居直ったが、今日まで条例に手が付けられなかった。(2024年4月4日付)
市保健センター条例には、第2条に「名称および位置」として茎崎保健センターなど4カ所が明記されていた。第4条に「業務」として(1)検診等(2)健康相談や健康教育(3)保健指導、栄養指導(4)機能回復訓練(5)衛生知識の普及等ーを明記、第5条で、各保健センターに「必要な職員を置く」となっている。
「茎崎保健センター」では、第4条(1)の検診等は春と秋の2回、茎崎保健センターの建物を使っていたが、貸し会議室のような存在。検診の結果が出ると谷田部保健センターから保健師が来て、会場を借りて、相談希望者に対応している。さらに常駐の保健師がいないので、第4条 (2)(3)(4)(5)は有名無実。また第5条に定める必要な職員は不在だった。
茎崎保健センターから責任者(センター長)と保健師が不在となったのが2010年であり、条例違反が15年も続いていた。
この経過を「NEWSつくば」に投稿したところ、多くのコメントを頂いた。「頼れる福祉」ではなく「頼りにならない市長だった」としたツッコミには、思わず噴き出した。現市長の「公約ロードマップ(工程表)」の5本の柱の3番目が「頼れる福祉」だが、それを皮肉ったコメントであった。
その場しのぎの市幹部、問われる議会のチェック機能
何度も言うが、条例違反の状況は、2010年から15年間も続いていた。「意図的な長期間の違反放置」が、住民や市議会議員が条例空文化に疑問を持たせないための行政側による仕掛けとなってはならないことは言うまでもない。
「茎崎保健センター」から保健師等が不在となり、利活用を検討した当時の担当が公有地利活用推進課だったことは、市が保健センター条例違反を追認していたことになる。仮に「利用者が少ない」としても、条例違反を常態化して良いことにはならない。
その当時、市議会の本会議で、茎崎保健センターの解体問題が取り上げられた。五十嵐市長は「(保健センターとしての)相談件数が減っている」と強弁したが、橋本佳子議員(当時)が「保健師が撤退したから、相談件数が減るのは当然」と反論した。
地域にドラッグストアがあれば、住民は利用するが、ドラッグストアがなければ、住民は利用しない。そもそも利用できない。そして市街地がさびれるという悪循環となる。
しかし、今年9月議会では、市長を追及した会派も含め全会一致で、「茎崎保健センター」の名称削除を決定し、保健センター機能の復活の芽が摘まれることとなった。
ちょうど5年前の2020年に、茎崎庁舎跡地利用に関する住民説明会があった。市から「保健センターの建物を解体し、その跡地を商業施設の用地にする」の提案があり紛糾した。
住民から「保健センターの機能は蒸発するのか」(保健部が担当)、「解体工事中の茎崎窓口センターは、どうなるのか」(市民部が担当)などの質問に対し、都市計画部(公有地利活用推進課)から責任ある答弁がされず、さらに「行政のタテ割りの弊害が問題ではないか」と批判された。
この住民説明会には、事前に内容を知っていると思われていた複数の現職の市議会議員までもが疑問に感じたのか発言があり、意見を述べた。
当時担当課は「40歳以上の集団健診については最悪、谷田部保健センターになる可能性もある」などと説明したが、とうてい納得できるものではなかった。
茎崎保健センターの建物が、都市計画部公有地利活用推進課の担当となったことで、当時の茎崎庁舎の跡地利用問題に対し、商業施設誘致と保健センターの建物と、どちらかを選択せよという誤ったメッセージを、茎崎地区の区長会、住民に与えることになったことになったのではないか(2020年8月7日付)。
結局、茎崎保健センターの建物は、解体は阻止され、現在地でリニューアルとなり、この12月に茎崎交流センター別館としてオープンとなる。また集団検診の会場として利用することにもなった。
そして新たな商業施設は、当初の計画より規模を縮小し、昨年2023年に車の通行量の多い県道沿いにオープンした。
だれも責任をとらないまま
これら一連の動きの中で、茎崎保健センターは、保健師の配置等、条例違反だったという問題はだれも責任をとらないままであった。
この条例違反は、いまの市長就任前からであるが、現市長には再発防止も含めた説明責任がある。とくに①条例違反になったことを知ったのはいつか、②条例違反を知っていたのに、条例を守らず、現状を放任していたのはなぜか、など説明する義務がある。また市議会こそ追及すべきであった。
条例違反を既成事実化し、既成事実をもとに条例改悪を押し付けた市長と市幹部。条例があるのに勝手に無視し、長期に役割を放棄してきた不都合な真実がばれた。ばれなかったら、表沙汰にならなかった。
役所の密室の中で、住民が知らないうちに、いや、知らせないお上(おかみ)体質の中で、住民は口出しするな、批判するなということではないか。
条例違反を15年続けていながら、だれも責任をとらないまま、ある日、交流センター別館に代わるのであった。とりわけ市議会のチェック機能、市民への情報公開の意欲が欠如していると感ずる。
地方政治に関心が高まる流れも
「地方自治は民主主義の学校」と言うが、多くの一般住民は地方行政や住民サービス、納めた住民税の使われ方についての関心が薄い。市長の名前も知らない有権者も相当数であろうし、市行政への提言要望やチェック機能を担う市議会議員も存在感が薄い。
つくば市は、首都圏の通勤圏内にあるTX沿線で若い世代を中心に人口が増加、子供の人口も増えて、学校の新設が相次いでいる。一方、周辺部は高齢化が進み、子供の数が減り人口減少が進んでいる。
いま市内の保健センターは、子供の多い地区など3カ所のみの配置となり、高齢化が進む市内周辺地域には存在しない。
地方政治には国政ほど関心がないし、国政選挙と重ならない地方選挙では、投票率が3割を切るケースも出ている。
ところが昨今、国政では大きな変化がみられる。投票率でみると、昨年の衆議院選挙(53.9%)よりも、今年の参議院選挙(58.5%)の方が高いという逆転現象がみられた。参議院選挙は身近でないと思われ関心も薄く、今年は7月の3連休の真ん中の日曜日であった。
いま18歳選挙権の定着もあって、若い世代が投票に行くようになった。6年前の参議院選挙(48.8%)と比べると、投票率が10%も増えている。ここ数年の国政選挙の投票率の上昇局面は、若者ら有権者の関心の高まりがあり、ニューメディア・オールドメディアを問わず、政治や行政が大きく取り上げられている。
地方自治への無関心は、地域住民の生活や福祉の停滞に、深くかかわってくる。自治体の政治や行政に、国政と同様に関心を強めることは当然である。
この国政への関心の高まりは、地方政治・行政にも押し寄せるのではないだろうか。「世界のつくば」の中身が問われてくる。 (政治労働問題研究者・認定コメンテーター)