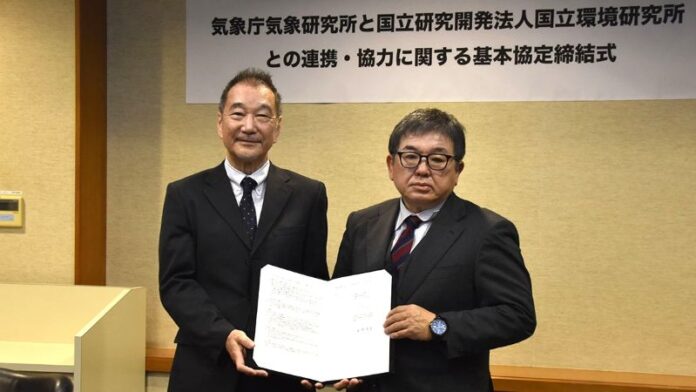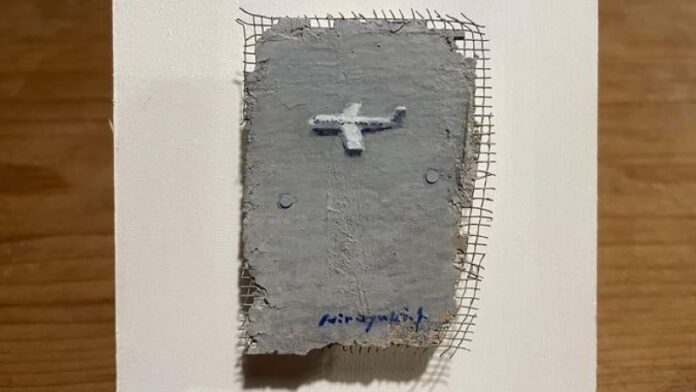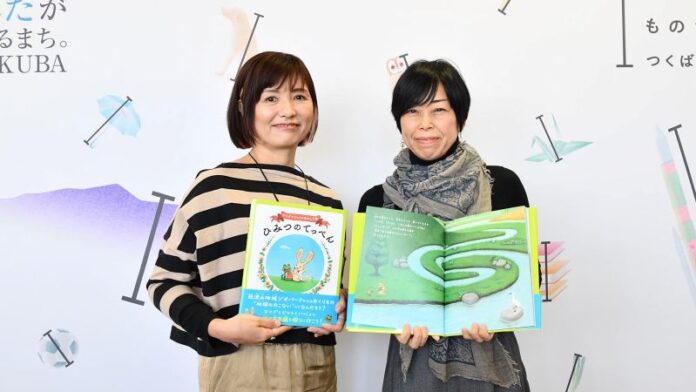【コラム・田口哲郎】
前略
ついに退院の許可が医師から下りた。私は天にも昇る気持ちであった。退院は明後日ということになった。まずは心配している家族にラインを送った。家人が迎えに来てくれるという。ありがたいことだ。
退院できるとなるとソワソワして、昼寝どころではなくなった。個室ではないが、ベッドとベッドの間には、クローゼットとテレビが載っている、引き出しの付いたサイドボードがあり、仕切りの役割を果たしている。
家族が持ってきてくれた本、筆記用具、パソコンや、洗面道具、タオルや綿棒などの衛生用品が引き出しに入っている。短い入院でも、こんなに生活の証しが広がるものだと驚いてしまった。まだ明日1日は病院にいるのに、もう整理整頓と片付けをしてしまう。
読書も手につかず、落ち着かずに過ごしていると、もう夕食が配られ始めた。ゆっくりかんで食べることを教えてくれた病院食も、残すところあと5回となると、食い意地の張った私は急に惜しくなった。
退院後の食事の模範にしようと、スマートフォンで写真を撮った。野菜中心の献立。毎食、魚か肉がメインで付いて、白ごはんはきちんとした量が出る。入院前には考えられない理想的な食事である。私は一口一口を味わって、有り難くいただいた。
病室という守られた空間
食べて寝る。動物としての人間の基本を教わった入院は貴重な体験であった。
会計を済ませて、それなりの大荷物を抱えて外に出た私は、自由を感じたが、それは病室という守られた空間があったからこそのものだとも思った。一度この世に生を受けたら、母の胎内には戻れないように、できれば病室には戻らないほうがよいだろう。
でも、この入院体験を「ふるさと」として忘れないことは、今後の私の生活に必要だと、冷たい空気を吸いながら思ったのである。ごきげんよう。
草々
(散歩好きの文明批評家)