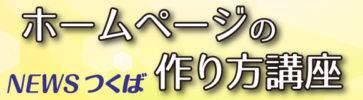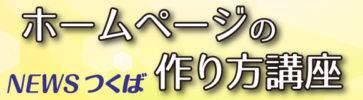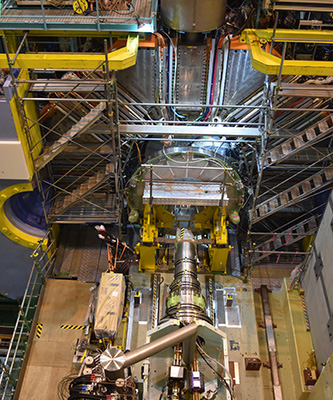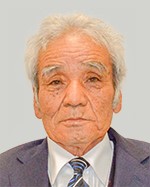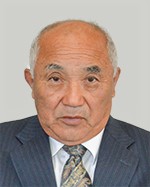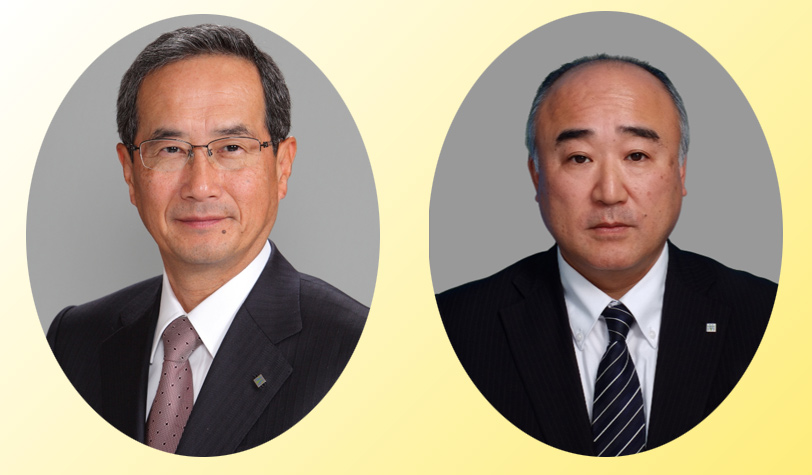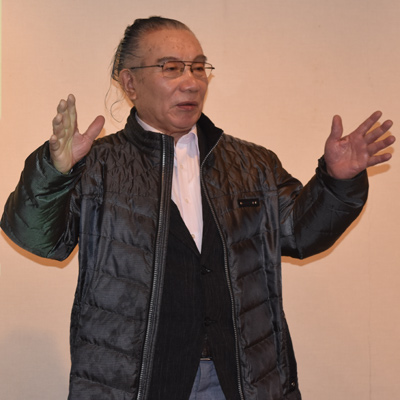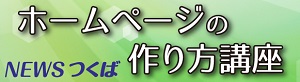統一地方選後半の土浦市議会議員選挙が14日告示され、定数24を7人上回る計31人が立候補を届け出た。内訳は現職20人、新人9人、元職2人となり、各候補は地元などで第一声を上げた。
政党別は公明4人、共産2人、無所属25人。男女別は男性28人、女性3人。現職27人のうち7人が引退した。
投票は21日午前7時から午後6時、小中学校など市内50カ所で行われる。期日前投票は15~20日市役所やイオンモール土浦など4カ所で。
開票は21日午後7時から霞ケ浦文化体育会館で行われる。13日現在の有権者数は11万8806人(男性5万9089人、女性5万9717人)。
4年前は定数28に対し13人超の41人が立候補した。投票率は前回48.43%だった。
 立候補者31人のポスターがずらりと貼られた選挙掲示板=14日、土浦市内
立候補者31人のポスターがずらりと貼られた選挙掲示板=14日、土浦市内
▷土浦市議選立候補者 届け出順
(氏名・敬称略、年齢、職業、政党、現新元の別・過去の当選回数、住所)
 海老原一郎氏
海老原一郎氏
海老原一郎 65 海老原興産取締役 無所属 現④ 真鍋
【略歴】青山学院大学経済学部卒。市議会議長。元市監査委員
 吉田千鶴子氏
吉田千鶴子氏
吉田千鶴子 66 政党役員 公明党 現④ 中村南
【略歴】県立土浦三高卒。公明党県本部女性局次長・副支部長
 柳沢明氏
柳沢明氏
柳沢明 68 会社役員 無所属 現④ 右籾
【略歴】県立土浦工業高校卒
 島岡宏明氏
島岡宏明氏
島岡宏明 60 島岡商事代表取締役 無所属 現① 右籾
【略歴】立教大卒。市教育委員長職務代理者。霞ケ浦自衛隊後援会理事
 矢口勝雄氏
矢口勝雄氏
矢口勝雄 55 マミーやぐち取締役 無所属 新 下高津
【略歴】千葉工業大卒。土浦二小後援会長。下高津1丁目副地区長
 久松猛氏
久松猛氏
久松猛 75 政党役員 共産党 現⑨ 木田余東台
【略歴】中央大中退。神立駅前区画整理事業組合議会運営委員長
 福田一夫氏
福田一夫氏
福田一夫 63 政党役員 公明党 現⑥ 乙戸
【略歴】東洋大学文学部卒。公明党県本部幹事。市議会副議長
 奥谷崇氏
奥谷崇氏
奥谷崇 48 カスミユニオン政治顧問 無所属 新 右籾
【略歴】東京経済大卒。UIゼンセン同盟流通部会組織強化・教育部長
 柏村忠志氏
柏村忠志氏
柏村忠志 75 無職 無所属 元⑤ 中高津
【略歴】日大法学部卒。霞ケ浦導水事業を考える県民会議共同代表
 川原場明朗氏
川原場明朗氏
川原場明朗 81 水道設備業 無所属 現⑤ 中神立町
【略歴】日本農業実践学園卒。土浦・かすみがうら土地区画整理組合議長
 篠塚昌毅氏
篠塚昌毅氏
篠塚昌毅 63 学園ビルメンテ取締役 無所属 現③ 荒川沖西
【略歴】日本大学卒。元市議会総務市民委員長。元市監査委員
 下村寿郎氏
下村寿郎氏
下村寿郎 63 農業 無所属 現① 乙戸
【略歴】日大東北工業高卒。新治広域組合議員。乙戸町内会役員
 目黒英一氏
目黒英一氏
目黒英一 49 会社員 公明党 新 北荒川沖町
【略歴】国際武道大学卒。公明党土浦支部副支部長。元カスミ
 矢口清氏
矢口清氏
矢口清 74 リーダー電機会長 無所属 現④ 田宮
【略歴】県立土浦工業高卒。元市新治商工会長。元土浦法人会副会長
 塚原圭二氏
塚原圭二氏
塚原圭二 57 会社員 無所属 現① 中村南
【略歴】東洋大卒。須沢商事。元日本テキサスインスツルメンツ課長
 田子優奈氏
田子優奈氏
田子優奈 32 政党役員 共産党 新 東崎町
【略歴】県立龍ケ崎一高定時制卒。 元関東墓地サービス副代表
 田中義法氏
田中義法氏
田中義法 49 田中冷設工業社長 無所属 新 永国
【略歴】土浦日大高校卒。亀城太鼓保存会代表。永国成年団役員
 四栗治氏
四栗治氏
四栗治 51 会社員 無所属 新 千束町
【略歴】城西大卒業。NECソリューションイノベータ社員。土浦市千束町区長
 勝田達也氏
勝田達也氏
勝田達也 55 勝田商事社長 無所属 現① 神立町
【略歴】明治学院大卒。元NPO法人まちづくり活性化土浦理事長
 今野貴子氏
今野貴子氏
今野貴子 61 市議 無所属 現① 小松
【略歴】北海道立江南高卒。元県議秘書。元衆院議員秘書
 寺内充氏
寺内充氏
寺内充 66 常陽土地建物社長 無所属 現⑤ 川口
【略歴】日大卒。土浦・かすみがうら区画整理組合議員。土浦土地開発公社理事
 平石勝司氏
平石勝司氏
平石勝司 48 政党役員 公明党 現② 神立町
【略歴】創価大学卒。元常陽新聞新社社員
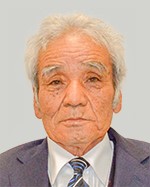 柴原伊一郎氏
柴原伊一郎氏
柴原伊一郎 77 農業 無所属 現③ 藤沢
【略歴】県立谷田部高校卒。新治土地改良区理事長
 小野勉氏
小野勉氏
小野勉 57 家庭教師 無所属 新 小岩田東
【略歴】明治大学政治経済学部卒。家庭教師。元会社員
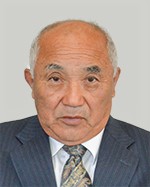 中川敬一氏
中川敬一氏
中川敬一 77 農業 無所属 元④ 神立町
【略歴】土浦五中卒。元市議会副議長。元市農業委員
 吉田博史氏
吉田博史氏
吉田博史 61 吉田衣料社長 無所属 現⑤ 常名
【略歴】土浦一高卒。都和南小よくする会会長。新治都和交番連絡協会長
 内田卓男氏
内田卓男氏
内田卓男 73 会社役員 無所属 現⑦ 中高津
【略歴】早稲田大第一商学部卒。ナカツネ建材監査役
 坂本繁雄氏
坂本繁雄氏
坂本繁雄 70 NPOいきいきネットワーク理事長 無所属 新 真鍋
【略歴】法政大中退。NPO茨城労働相談センター理事。脱原発ネット運営委員
 小坂博氏
小坂博氏
小坂博 62 会社社長 無所属 現③ 生田町
【略歴】大東文化大学卒。小坂タクシー社長
 鈴木一彦氏
鈴木一彦氏
鈴木一彦 55 学習塾経営 無所属 現③ 藤沢
【略歴】日本大学農獣医学部卒。新治学園後援会長。市新治商工会副会長
 石引潔氏
石引潔氏
石引潔 66 会社員 無所属 新 真鍋
【略歴】私立茨城高校卒。周文会副代表