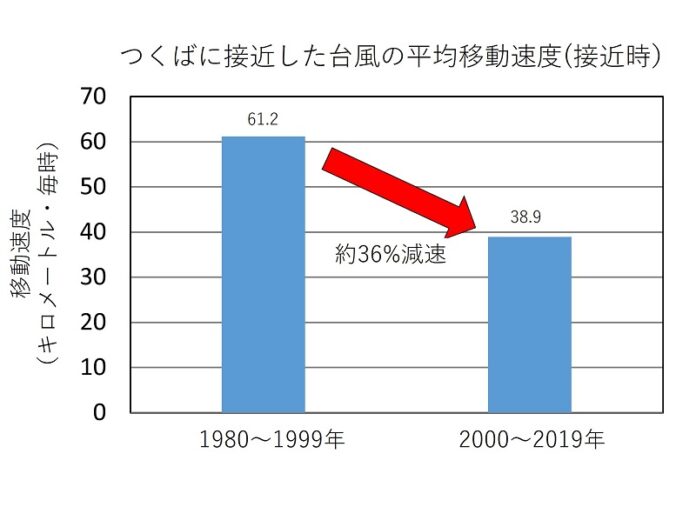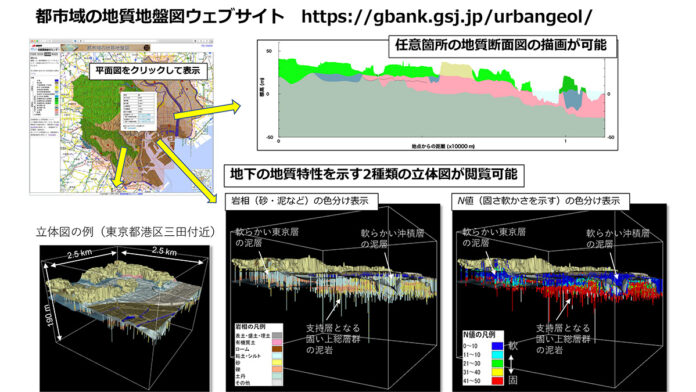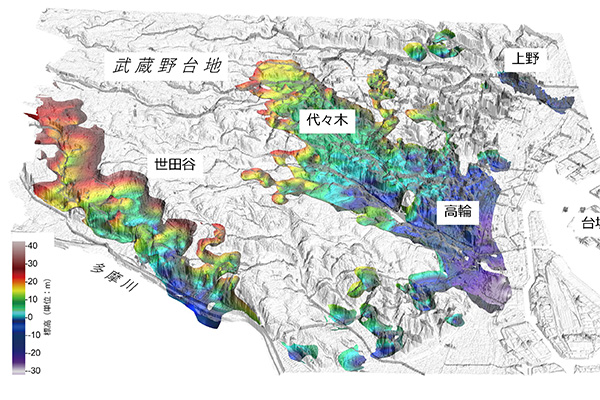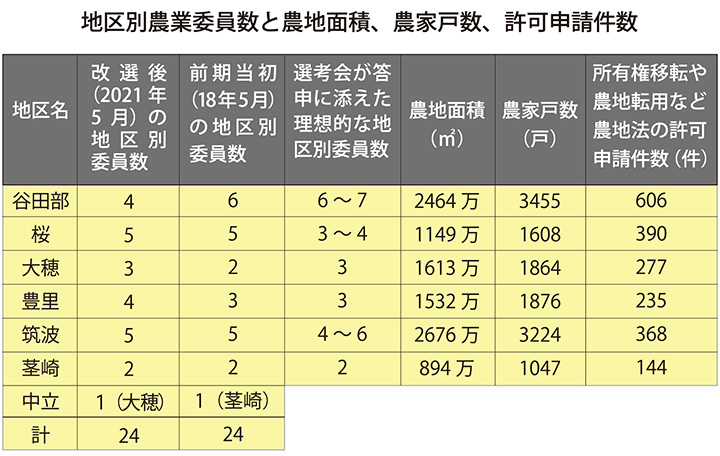4月、NEWSつくばに読者から「絶滅危惧種の『キンラン』がつくば市街地に自生している」というメールが届いた。
その場所は、つくば駅に近いセンター地区の市街地。後日、メールの差出人に案内されると、ある企業の私有地に、黄色く小さな花をつける1本のキンランがあった。一見、どこにでもあるような普通の植物。周囲の雑草と見分けがつかず、探すのに時間がかかった。
「絶滅危惧種」がなぜ市街地に生えているのだろう? 希少な植物に出合ったとき、私たちは一体どうすればいいのだろう? 湧き上がるいくつかの疑問を胸に、専門家に話を聞いた。
キンランとは?
そもそもキンランとはどのような植物なのか。
キンランは、日本に約300種あるとされるラン科の植物の一つ。多年草で、ブナ科やマツ科の樹木の根もと近くに生育し、30センチから70センチほどの高さになる。これらの樹木の根に寄生する菌類が作る養分を、キンランは取り込み生きている。こうした菌類との共生関係を必要とし、単体では生きられないのも大きな特徴だ。
かつて雑木林に群生するキンランを見ることは珍しくなかった。しかし近年、個体数が減少し将来的な絶滅が危惧されることから、環境省は「絶滅危惧II類」に、茨城県も独自に「準絶滅危惧」に指定している。
なぜ「絶滅危惧種」に?
では、なぜキンランは個体数が減ってしまったのか。
県自然博物館(坂東市)で学芸員を務める伊藤彩乃さんは、減少の理由の一つとして、かつて人の暮らしに欠かせなかった雑木林の手入れが行き届かなくなったことを指摘する。
「かつてキンランは、私たちにとって身近な植物でした。雑木林にはコナラやクヌギといった、キンランの生育に必要なブナ科の樹木が多くありました。それらの樹木を、まきや炭として利用するために定期的な伐採や下草の刈り取りを行っていました。しかし、生活の変化によって放置される林が増え、下草が密集し伸びると、背丈の低いキンランに光が届かなくなり、光合成ができず生育できなくなったと考えられます」
 手入れが行き届かなくなった雑木林
手入れが行き届かなくなった雑木林つくば市で環境保全活動をする「つくば環境フォーラム」の田中ひとみさんも同様の指摘をした上で、「キンラン以外にも絶滅の危機に瀕する動植物が、人との関わりが停止した雑木林を含めた『里山』に多く存在している」と話す。
「里山」とは、農林業など人の生活を通じてつくられた、農地や集落を含めた広い生活圏のことを指す。かつて日本各地で見られた環境だ。「里山」の減少がキンランだけでなく、キキョウやオミナエシなどいくつもの植物を絶滅の危機に追いやっている。環境省は植物以外にもメダカ、タガメ、クロシジミなどの動物も、里山減少による絶滅危惧種として挙げている。
環境保全の意味
「絶滅しそうな里山の動植物を保全するには、人による再生が必要」だと、田中さんは話す。
ではなぜ私たちは里山を保全し、動植物の減少を防ぐ必要があるのだろうか。田中さんはこう説明する。
「実感しづらいかもしれませんが、人が自然の恵み(生態サービス)によって、その命を繋いでいるからです。自然界は、多様な生物のバランスによって今まで持続してきました。絶滅危惧種が急増しているのは、そのバランスが崩れてきている証拠ではないでしょうか。自然界のバランスが崩れると、生物種のひとつである人類にもいずれ生存の危機がくるかもしれません」
生活する人間と、その環境に適応する多様な動植物の関係が長い年月をかけ育まれた。人の暮らしも、そのバランスの上に成り立ってきたのだ。
再び増えつつある個体数。都市部に適応する生命力
今回キンランが見つかったのは、つくば市の中心市街地という「自然」と離れた場所だった。そこにキンランが咲く意味を、どう捉えればいいのか。質問に対し、県自然博物館の伊藤さんはこう話す。
 茨城県自然博物館学芸員、伊藤彩乃さん
茨城県自然博物館学芸員、伊藤彩乃さん「私たちにとっての『(自然の)豊かさ』とは、原生林など人の手が加わっていない場所を想像するかもしれません。しかし、生き物の視点から見た時に、意外と都市の中にも、彼らにとって『豊か』な場所はあるのです」
「キンランが生きるために必要な条件は、ブナ科やマツ科の樹木、そこに寄生する菌類、適度に人手が加わり、光が届く場所。意外かもしれませんが、都市部にも、こうした植物にとって『良い』条件が整う場所が少なくないのかもしれません」
「街路樹や公園など、植栽された林が市街地には多いと思います。昔ながらの雑木林ではなく、街をつくった時に新たに木を植えたところです。そこにブナ科やマツ科の樹木を選んで植えることがあります。そうした場所に生えるキンランを、最近見るようになりました」
つくばの中心市街地で今回見つかったキンランを振り返ると、近くに松の木があったし、周囲の雑草は適度に刈られていた。伊藤さんがこう続ける。
「はっきりとした理由はわかりませんが、元々あった雑木林から飛んできた種子が発芽した可能性もありますし、植えられた樹木の根についてきた可能性もあります。キンランは、菌類との共生関係が必要です。持ち込まれた樹木と共生する菌類が活発であれば、キンランが発芽する条件は整います」
「人が作った環境に適応するキンランの姿を見ると、生き物としてのしたたかさを感じます」
見つけた人はどうすればいいのか?
希少動植物の中でも特に保護が必要とされる「国内希少野生動植物種」は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」に基づき、個体の捕獲や譲渡が原則禁止され、違反すると罰則が適用される。しかし、キンランは法的な保護の対象には含まれていないものの、県は「茨城県希少野生動植物保護指針」で県民に対し、「自主的かつ積極的に取組みを進めること」を求めている。
では具体的にキンランに遭遇したとき、私たちはどうすればいいのか?
今回つくば市でキンランが確認されたのは、吾妻1丁目、NTT東日本茨城支店つくばビルの敷地内だった。NEWSつくばの問い合わせに同社は、こう回答している。
「キンランが生育している場所の状況から、囲い込み等の保護は行わず(囲い込みを行うことにより、かえってイタズラ等にあう可能性もあるため)、自然体で見守っていきたい。除草作業等時はキンランの花弁が落ちていたことを確認したうえで、球根を傷つけないよう配慮しつつ、来年以降も対応をとっていきたい」
茨城には、キンランの他に、キンランの一品種である「ツクバキンラン」もある。珍しさも手伝い、思わず自宅に持ち帰りたくなるかもしれない。それに対して伊藤さんはこう話す。
 県自然博物館の敷地内に自生する「ツクバキンラン」
県自然博物館の敷地内に自生する「ツクバキンラン」「(キンランの)数が減ってしまった要因に、花がきれいなために採集されてしまったということもあります。キンランは、樹木と菌類との共生関係が必要なので、持ち帰って鉢に植えても育つことはできません。それだけでは生きることができないのです。樹木や菌を含めた周囲の環境が整ってこその生き物です。なので、むやみに採ることはせずに、林のなかで咲いている姿を楽しみましょう。周りの環境と共に見守ってほしいと思います」。(柴田大輔)




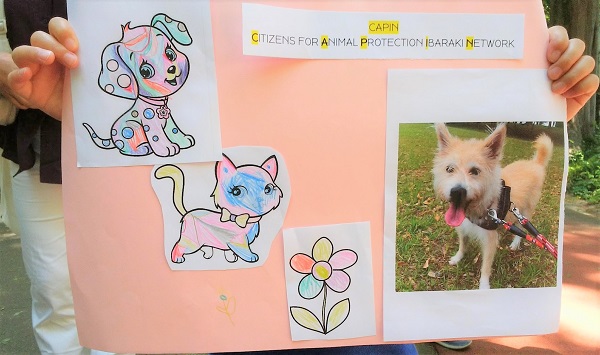






![斉藤裕之86[3486]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/05/a92033595b7af0c7b36323d80b9bb3cb-696x392.jpg)