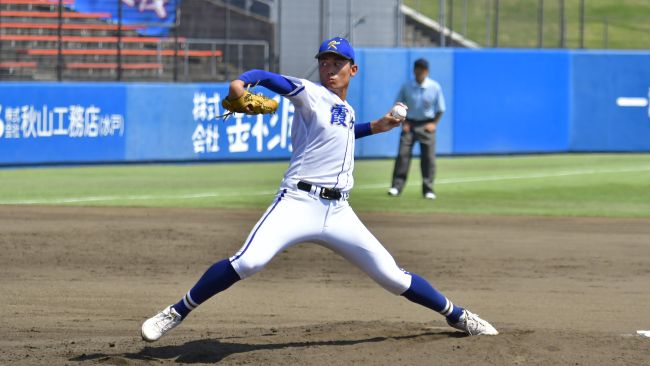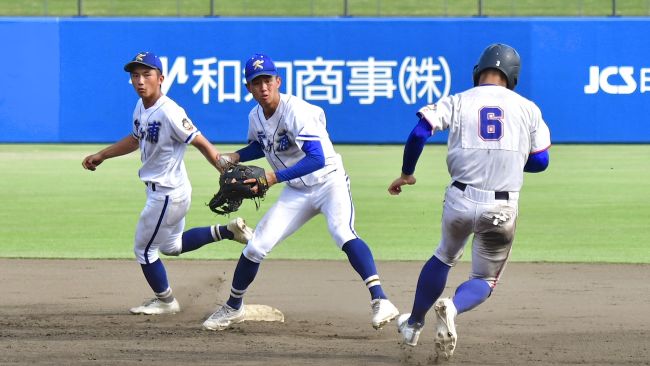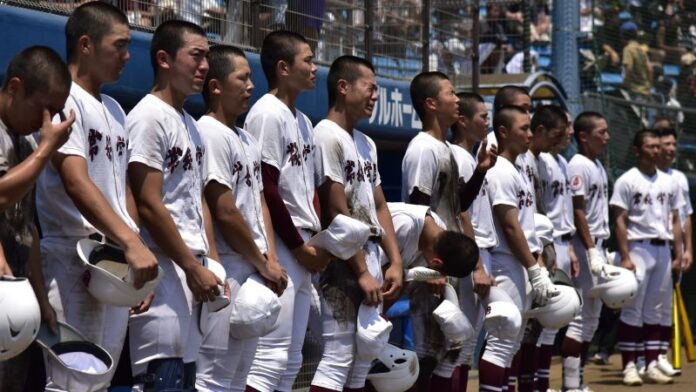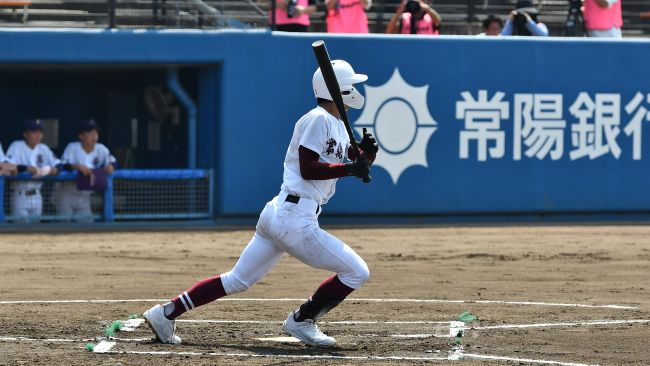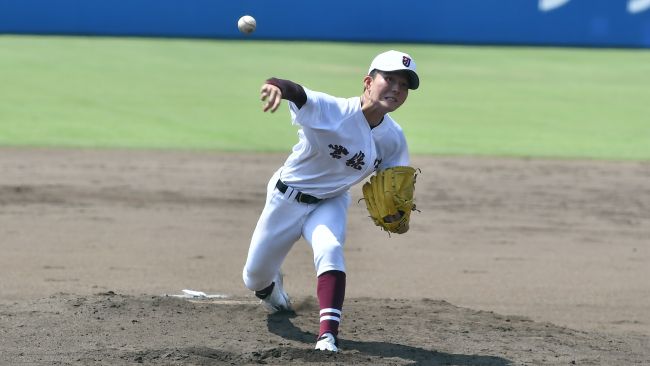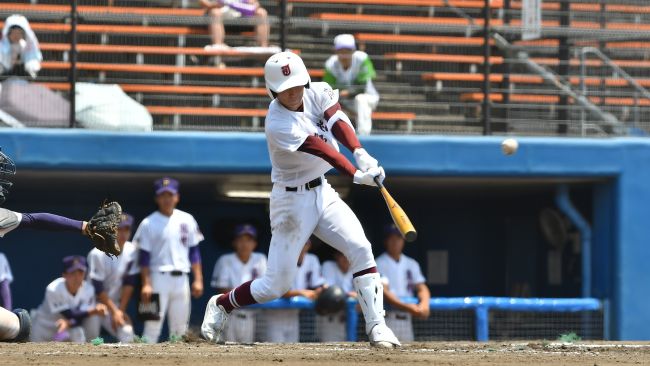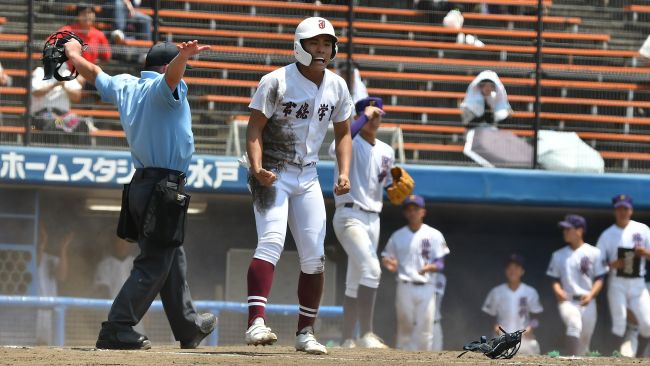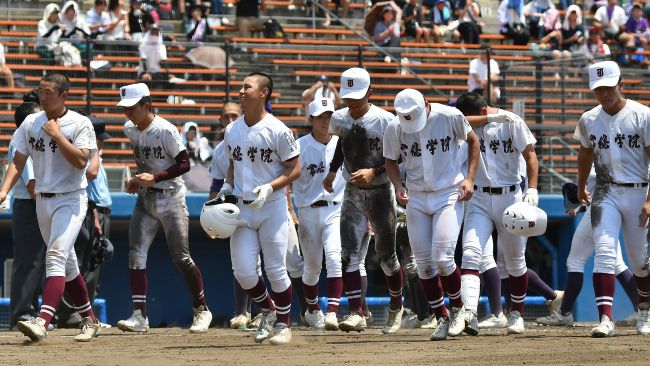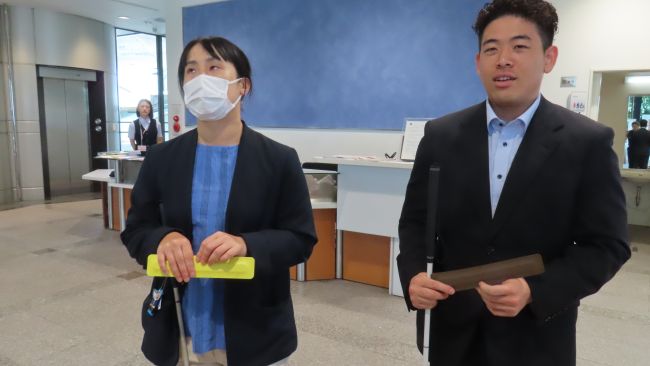救急車不搬送事案で
高熱を出したつくば市の3歳男児(当時)が2023年4月、救急車を呼んだが病院に搬送されず、その後、重い障害を負った事案で(3月26日付)、つくば市は1日、市消防本部トップの青木孝徳消防長が当時、男児の家族の顔写真の提供を個人的に第3者の知人に求めていたことが分かったと発表した。
実際には写真を入手しなかったが、青木消防長の行為は公務員としての自覚を欠き、消防本部の長として不適切なものだったとして、市は7月28日付で消防長を訓告処分とした。訓告は懲戒処分ではなく厳重注意に当たる。
市消防本部によると青木消防長は、不搬送事案発生から約1カ月後の2023年5月中旬ごろ、男児の家族を知る知人に、家族の写真があったら送ってほしいと求めた。当時、不搬送案事案について家族から市消防本部に問題提起があり、家族と意見の食い違いがあったことから、どのような人物像か個人的に知りたかったためだと青木消防長は釈明しているという。
今年4月、男児の家族から、写真を入手しようとし、公務員及び消防長としてふさわしくない、などの申し出があり発覚した。
申し出を受け市人事課は青木消防長に聞き取りを実施、7月7日、市職員分限懲戒委員会を開催し、同28日、訓告処分とすることを決定した。市消防本部によると青木消防長は、軽率だったと反省しているという。
五十嵐立青市長は「今回発覚した行為は誠に不適切なもの。ご家族に対し心からお詫びすると共に、消防長の任命者としての責任を痛感している。消防長に対しては職責を再認識し、日ごろの業務を通じて市民及び職員からの信頼回復に努めるよう強く指導した」などとするコメントを発表した。