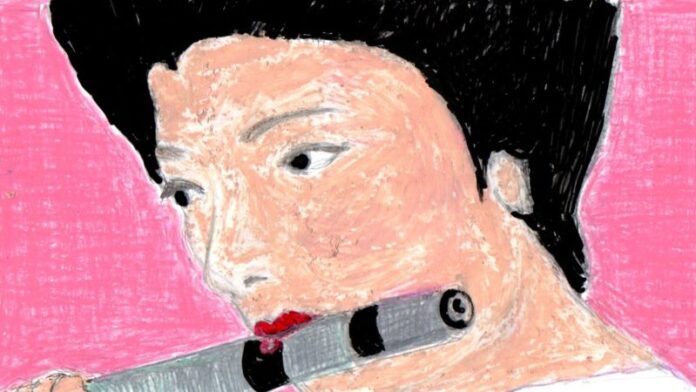12日の成人の日を前に、つくば、土浦両市で11日、「二十歳のつどい」がそれぞれ催され、20歳を迎えた若者たちの門出を祝った。
手荷物検査など今年も厳重警備 つくば
つくば市の式典は同市竹園のつくばカピオで催された。出身中学校別に午前と午後の2部制で行われ、合わせて計1950人が出席した。
同市では2017年の成人式で逮捕者を出したのを契機に、翌18年から手荷物検査をはじめ多数の警備員や警察官が厳重警備を実施。会場近くの道路はバリケードを設置して通行止めにし、会場に隣接する大清水公園などを警備員や制服・私服警察官が巡回した。名前入りのぼり旗を掲げた10人前後の若者の一団が現れたが、市職員らの指示に従いのぼり旗を一時預かり所に預け、大きな混乱は見られなかった。
 会場に集まった新成人たち=つくばカピオ
会場に集まった新成人たち=つくばカピオ
式典では、新成人代表の長谷川莉生さんが誓いの言葉を述べ「違いを受け入れ、互いの価値観を尊重しながら未来を描き築いていくこと、それが二十歳を迎えた私たちに求められる姿勢だと感じています」と話した。
五十嵐立青市長は、つくば育ちの宇宙飛行士、諏訪理さんが、宇宙飛行士の選抜試験に一度は落ちながらも苦難の末に夢を成就させたエピソードを語り「今日の日をきっかけに、皆さんが幸せな人生を歩み続けていくことを心から願っています」と式辞を述べた。
その後、出身中学校の恩師からのビデオメッセージが放映されると、参加者からは感嘆の声が上がった。
式典自体は約30分で終了、終了後は出身中学校ごとに係員が誘導して参加者を退場させた。参加した大学生の中崎遥香さんは「一つひとつの行動に責任を持っていきたい」と、20歳の抱負を述べた。
千葉ロッテ・木村投手がサプライズ 土浦
 土浦市出身の千葉ロッテマリーンズ・木村優人投手のビデオメッセージ=クラフトシビックホール土浦
土浦市出身の千葉ロッテマリーンズ・木村優人投手のビデオメッセージ=クラフトシビックホール土浦
土浦市の式典は、同市東真鍋町のクラフトシビックホール土浦(市民会館)で開かれ、847人が出席した。
会場前の広場は、参加者らが滞留しないように入場規制が敷かれ、市職員や警察官らが酒類やのぼり旗の持ち込みを警戒した。時折のぼり旗を掲げた改造車が会場付近に数台現れたが、大きな混乱は見られなかった。
式典で安藤真理子市長は、新成人が中学・高校の頃はコロナ禍で、部活動や学校行事などが制限された件に触れ「これまでの難局を乗り越えてきた皆さんは、すでに壁を打ち破る力をもっているはず」「どうか自分の力と可能性を信じて、未来を築き上げていってください」とエールを送った。
出身中学校恩師からのビデオメッセージの後、同市出身で千葉ロッテマリーンズの木村優人投手から「20歳になり、自分も含め自覚と責任を持ち、子どもたちの模範となり、夢を与えられるように共に頑張っていきましょう」とのビデオメッセージがサプライズとして流された。その直後、場内にいる木村投手が紹介されると、場内から歓声が上がった。
代表謝辞で長田舜さんは、コロナ禍での辛い学校生活に触れ「困難な状況だからこそ、支えてくれる人がいることの大切さやありがたさに気づかせてくれました」と感謝の意を示し「今度は私たちがここ、土浦で受けた愛情をこれからの世代へ伝えていく事を約束します」と誓いの言葉を述べた。
 謝辞を述べる代表の長田舜さん
謝辞を述べる代表の長田舜さん
参加した、両親がスリランカ出身で同市生まれの大学生、サケンタ・ペレラさんは「将来は科学の分野の仕事を目指している」と語った。専門学校に通う知久心愛さんは「将来は美容師になっていっぱい稼ぎたい」などと抱負を述べた。(崎山勝功)