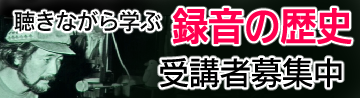【コラム・室生勝】在宅医療が必要となる主な原因は、内閣府の2016年調査によると、男性で脳血管疾患(脳卒中)が23.0%、女性で認知症が20.5%と最も多く、ついで男性では認知症15.2%、女性では転倒・骨折15.2%、関節疾患12.6%と、認知症が男女ともに多い。原因疾患を特定できない「高齢による衰弱」が男性で10.6%、女性で15.4%を占める。
後期高齢者になると認知症が増えると言われているが、厚労省の資料では年齢階級別にみた出現率が見当たらない。埼玉県立大の川越雅弘教授が某市で調査した結果では、「70~74歳」3.3%、「75~79歳」9.2%、「80~84歳」20.3%、「85~89歳」37.8%、「90~94歳」57.1%、「95歳以上」72.8%と、80歳から出現率が急上昇している。
介護が必要となる目安である、要支援・要介護認定者の割合を厚労省の2018年7月の資料から見ると、65~69歳は3.0%、70~74歳は6.0%、75~79歳は12.9%、80~84歳は28.0%と、倍々ゲームで増え、85歳以上では60.1%となる。長寿社会では80歳からの在宅医療が大きな課題である。
診療所医が長年診てきた人が歳を重ね、脳血管障害(脳卒中)、認知症、骨折、関節疾患などで通院できなくなれば、外来診療の延長線上で在宅医療を行うのが自然の流れであろう。長年の付き合いで、その人の仕事、性格、嗜好、趣味、家族関係などを知っているので、食事、歩行、運動、生きがいづくり―などへ適切な助言ができる。
認知症家族への対応 誇りを傷つける?
さらに、それらの助言は認知症の場合に大きな役割を発揮する。認知症には専門医の診断と治療の助言が欠かせないが、周辺症状といわれる行動・心理症状(BPSD)への対応は、これらの情報をいかした「かかりつけ医」の家族や介護サービス提供者のケアの指導に役立つ。
認知機能が低下して、記憶障害や年月日、時間、季節、場所、人物などの認識の混乱、理解・判断力の障がいが出ると、日常生活に不安や不都合が起き、それらが不穏、妄想、徘徊などのBPSDの原因や引きガネになることが多い。自分がそうなったときを想像してみよう。不安になり、いらだつ気持ちがよく理解できる。しかし家族介護者にとっては、肉親が認知症になったことを認めがたく、本人に注意してしまう。それが本人の誇りを傷つけ、さらに心をいらだたせる結果になる。
アルツハイマー型認知症には進行を遅らせる薬はあるが、他の認知症も含め「治す」薬はない。周辺症状に対しての薬であり、副作用が起きやすく、専門医とかかりつけ医の協働が必要だ。薬よりもかかりつけ医の、家族介護者や介護サービス提供者への助言などが何よりのクスリである。
認知機能の低下には個人差があるが、加齢が大きな要因で60歳を過ぎると、少しずつ進む。加齢以外に認知症を起こすアルツハイマー型認知症、レビー小体病、前頭側頭型認知症、脳血管障害(脳梗塞、脳出血)などがある。慢性硬膜下血腫、正常水頭症や甲状腺機能低下症などによる認知症は適切な治療で完治する場合もある。
つくば市で内科の看板を出し、外来診療している診療所は在支診以外に約30カ所ある。高血圧、狭心症、糖尿病、腰痛症、膝関節症、骨粗鬆症などの病気の診療に長年携わってきているが、できる範囲の在宅医療に関わってもらいたい。団塊の世代が75歳以上になる2025年まであと6年。そのころには在宅医療を必要とする高齢者が増えてくるからだ。(高齢者サロン主宰)
➡室生勝さんの過去のコラムはこちら