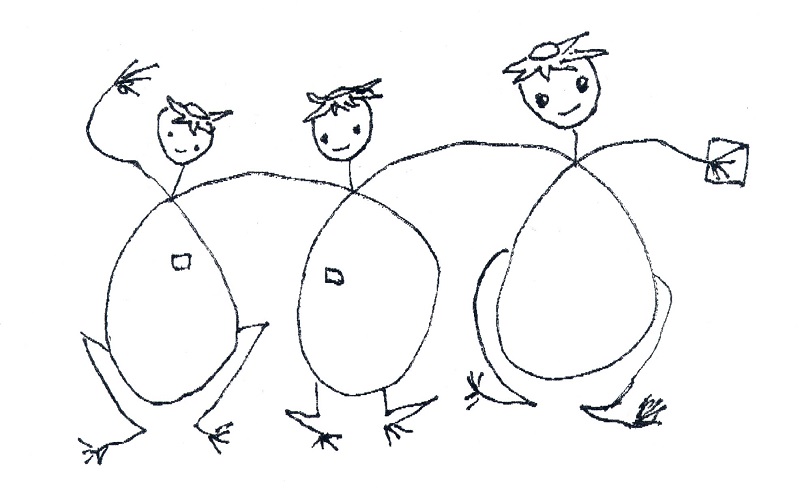【コラム・奥井登美子】我が家は明治28年生まれの昔からの薬局。お客様も昔からの付き合いのご老人ばかりである。ある日、Aさんがやってきた。元気がない。「歩くと息苦しいので、病院に行って診てもらったら、心臓がもう、へとへと、なんだと…」。
「今日の処方箋、フランドルテープが入っている。これはテープだけれど、心臓の薬(経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤)だから、間違えないでね、1日1回、忘れないように、胸か、おなかの上あたりに貼るの」
「絆創膏なんだろ。足か腕に貼ってもいいべな」「心臓の近くに貼らないと、意味がないの。ほら、このパンフに貼り方の絵が書いてあるでしょ。絵の通りに貼ってみてちょうだい」「心臓の薬で貼り薬なんかあるのか」「あるわよ。心臓は大事ですもの」
少しシツコイかなと思ったが、ものがものだけに間違えたら大変。3回も、心臓の近くに貼ることを説明した。
1週間経って、再びAさんがやってきた。「きょう病院に行って、足に貼ったと言ったら、先生に怒られちゃったよ」「この間、よく説明したはず。パンフにも、心臓の薬と書いてあるのに」「目が悪くなっちゃって。読むのが、なんだかオックウなんだ」。
多分ドクターは、調剤した薬剤師の説明が不十分だと判断したに違いない。私としては、何回も念を押して説明したはずなのに、残念至極。
老人にありがちなことだけれど、家に着いたとたん、直前のことはすべて忘れてしまう。絆創膏状の貼り薬は足か手に貼るものという、昔からの慣習がむくむくとよみがえる。
薬剤師も、その人の思い込みを取り除き、理解できる言葉を選んで、ゆっくりと大きい声で、間違えないように何回も説明し、拡大コピーしたパンフを渡す。
医療の進歩とともに、町の薬剤師にも、患者さんの「理解できる言葉を選択する」という、思いがけない問題が降りかかってきたと思う。(随筆家)