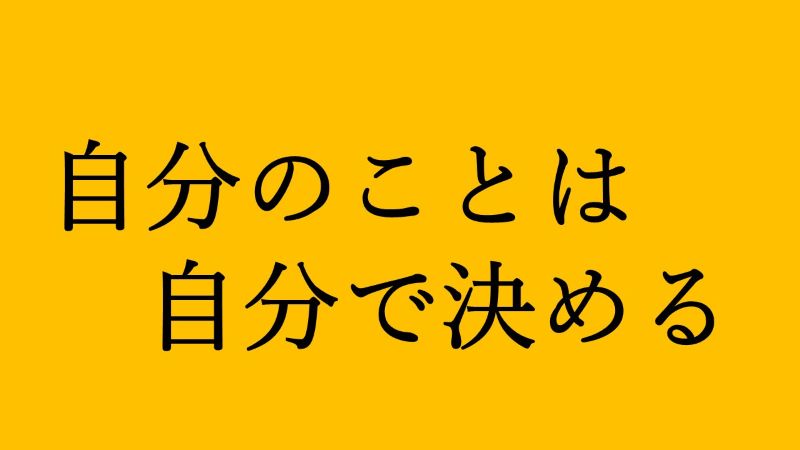【コラム・川端舞】前回のコラム(9月14日掲載)で、1970年代、旧・優生保護法の改正案に経済的理由による人工妊娠中絶の禁止が含まれたとき、フェミニズムの運動に関わる女性たちが主張した「産む・産まないは女が決める」という言葉を紹介した。この言葉は、「胎児に障害があれば中絶する」という障害者にとって恐ろしいメッセージにもなり、障害者と女性の対立を生んだ。
しかし、この言葉の根底にある「自分の体のことは自分で決める」という考えは、障害者運動にも通じるもののように思う。
前回も引用した荻野美穂の「女のからだ―フェミニズム以降」(岩波新書)によると、明治以降、中絶は犯罪とされてきたが、戦後の食糧難の中で、優生保護法が成立し、中絶を認める条件が大幅に緩和された。結果、中絶件数は急増し、出生率は低下した。しかし、高度経済成長期に入り、労働力不足が問題視され始めると、今度は国会で中絶を規制しようとする動きが出てくる。
人口政策のため、母胎に負担をかける妊娠・出産や、女性に負担が偏りがちな育児を、国が管理することに抵抗し、自分の体に対する女性の自己決定を尊重したものが、「産む・産まないは女が決める」という主張だった。
これは障害者運動が大切にしている「自分のことは自分で決める」ことにも通じるのではないか。長年、入所施設の中で生活リズムや外出機会などを他者に管理されてきた重度障害者が、施設を出て、必要な支援を受けながら、どこで誰とどんなふうに生きていくかを自分で決められるよう、介助者などの社会制度を整えてきたのが障害者運動だ。
自己決定が尊重され、誰もが自分らしく生きられる社会にしたいという原点に立てば、障害者運動と女性運動はもっと連携できるのではと、最近考える。
トランスジェンダーも同じ
「自分のことは自分で決めたい」のは、出生時に割り当てられた性別と性自認が一致しないトランスジェンダー当事者も同じだろう。
現行の法律では、戸籍上の性別を変更するためには生殖腺を取り除く手術をする必要がある。これは、自分らしい性で生きたいと願うトランスジェンダーに手術を事実上強制するもので、国連も日本に手術要件の撤廃を勧告している。手術を受けることで、自分らしく生きられると感じる当事者には、公的医療保険の中で受けられるようにすべきだが、本人が望まないのに、健康な身体を傷つけるよう求めるなど、絶対にあってはならない。
全ての人が、必要な情報提供や支援を受けつつ、自分のことは自分で決められる社会を、多様な人たちとともにつくっていきたい。(障害当事者)